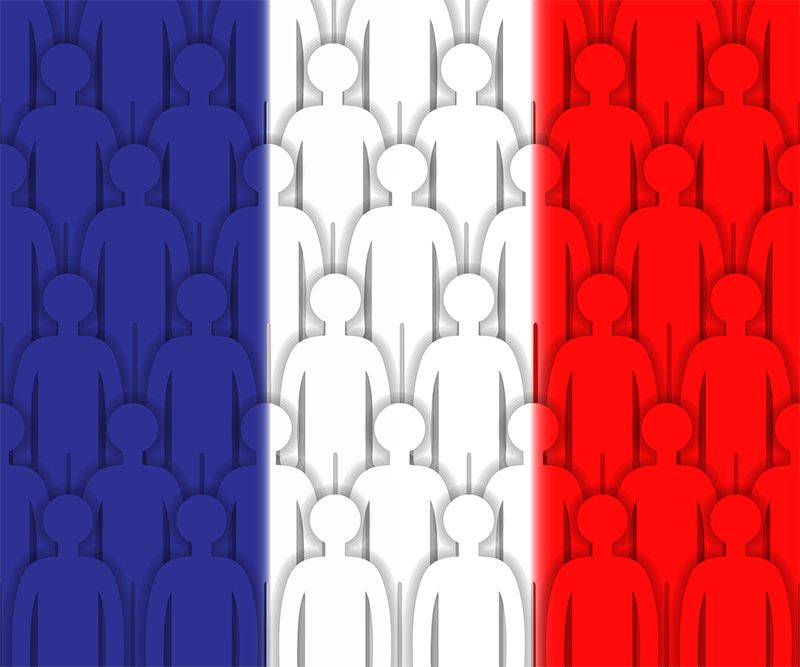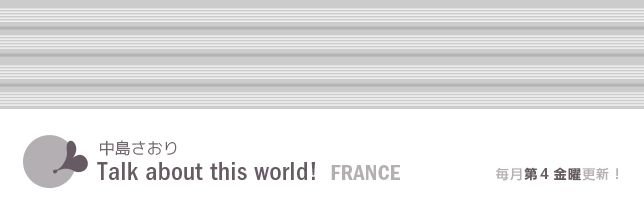
フランスの2015年は、週刊紙『シャルリー・エブド』襲撃事件、モンルージュの女性警察官射殺事件、ヴァンセンヌのユダヤ食料品店襲撃事件という3日に渡り17人の犠牲者を出した連続テロで血生臭く幕を開けた。
イスラム過激派のテロだったことから、たちまち、フランスのムスリム系住民が嫌がらせを受ける事態が頻発した。政治家や識者は、「テロリストとイスラム教を短絡させて混同しないように」と盛んにメッセージを送っていたけれども、モスクへの襲撃や往来での暴言や挑発的は多発した。
テロが起こったとき、フランスのムスリムたちからは、「これでまたムスリムに風当たりが強くなるのか」という憂慮の思いが聞かれた。
日本では、『シャルリー・エブド』のマホメットの風刺画が、「イスラム教徒の気持ちを害するのは当たり前だ」と理解を寄せられたり、「差別されているイスラム系住民が不満からテロに走るのはフランスの政治の失敗だ」というような反応がよく見られたが、フランスに住んでいる私は、そう簡単にテロリストと一般のイスラム教徒を一緒にされるのには大きな抵抗を感じた。
フランスにはおよそ500万人のムスリムがいる。全体を統一するカトリック教会のような組織はなく、イスラムを代表するべく政府によって作られたCFCM(全仏イスラム会議)も多様なイスラム教会全部の把握にはほど遠いが、はっきり言えるのは、ムスリムの圧倒的多数は、テロに走るような過激分子ではないということだ。
フランス共和国の非宗教の原則とイスラム教が原理的に相容れないということはたしかにあるし、問題になるべき問題だ。けれども現実には、共和国原則を受け入れているムスリムもフランスには沢山いる。つまり、フランス共和国では、宗教は個人の私的な領域にあっては自由なのだが、公の場で主張してはいけないことになっている。そのため、例えば職場で宗教義務の祈りをしようとしてもできない、というようなことはある。しかし、職場では祈らない、という妥協をするイスラム教徒はいくらでもいるのだ。
私がこの連載で書くことになっているテーマは「フランスの女性」なので、ムスリムの女性のことを少し書こう。ムスリムの女性たちはたしかにフランスの一般の女性と同じには語れないところがある。ムスリムのコミュニティーには家父長制が強く、女の子が自由に進学したり職業選択したりできなかったりする。性行動もフランス全体の女の子と比較して一般にはずっと慎ましいが、その裏返しとして避妊や中絶ができずに悲劇に至る若年女性も多い。宗教の印を身につけていてはいけない公立高校に被って行って大事件となったイスラムのスカーフ、あれを身につけている女性も沢山いる。フランス人には「女性抑圧の象徴」と言われているスカーフだ。しかし、こうしたことも、すべてのムスリム女性にあてはまるわけではない。ムスリムは一色ではなく、フランスへの適応と宗教の遵守とのバランスの取り方は様々で、フランスと軋轢を起こさない人もたくさんいるのだ。
そういうムスリムたちにとって、テロを行うような過激分子は「同じムスリム」ではない。むしろ「迷惑な者」である。自分たちが「本来のイスラム教をちゃんと伝える」ことによって、過激な原理主義に走る若者を抑えることができると考えたりする。テロリストにイスラム教を名乗られることに違和感を抱く。
週刊新聞社襲撃はイエメンのアル・カイダに、他の二件はアル・カイダと反目するテロ組織「イスラム国」に繋がっているということだが、実際に犯行に及んだのは、アルジェリア系フランス人のクアシ兄弟とマリ系フランス人、アメディ・クリバリで、彼らの間には面識もあり、連携したという説もある。ということは、組織が厳格に組織したものではなく、ゆるい枠組みのなかで犯人たちが自発的に動いたものと考えられる。
国際的なテロ組織を背景にしているとはいえ、この事件は、テロに走ってしまう若者を生み出したフランスの国内問題と考えるべき部分が大きいのではないだろうか。
クアシ兄弟やクリバリのような若者をフランスは育ててしまったし、育ててしまっている。しかしそれは「ムスリム」だからなのだろうか? 彼らの家庭の貧しさや学校からの落ちこぼれや、軽罪で入れられた刑務所のことを、まず最初に考えてみるべきではないだろうか。