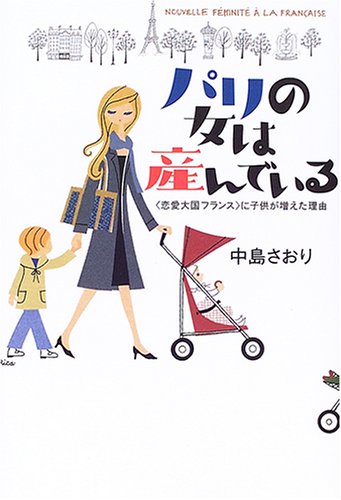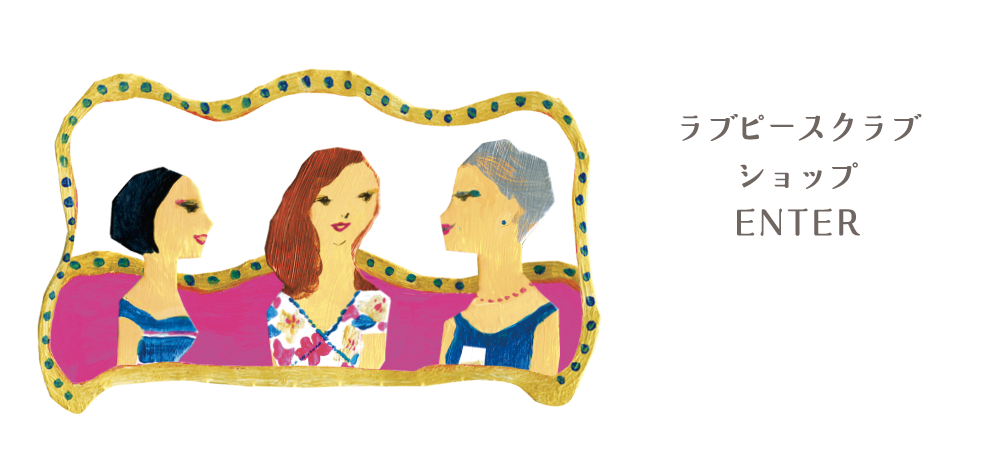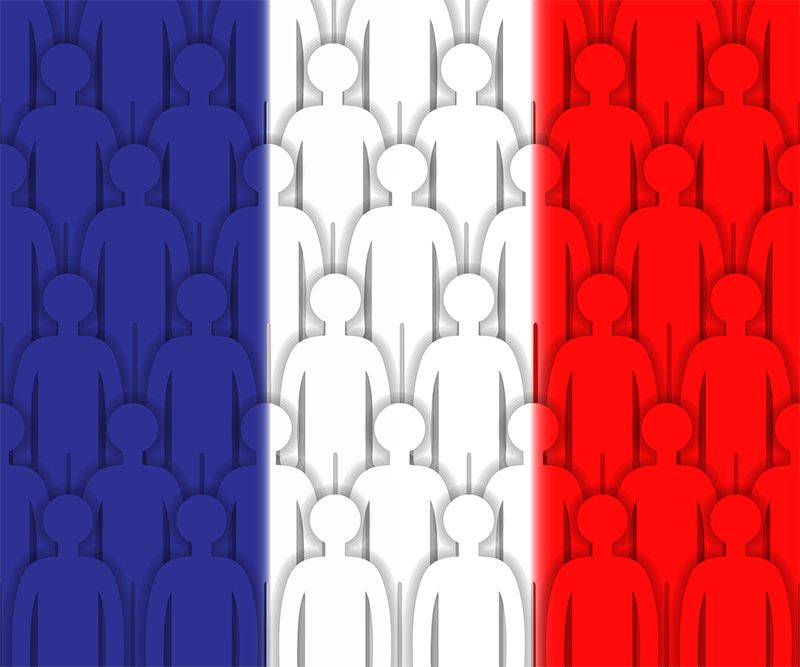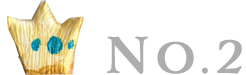TALK ABOUT THIS WORLD フランス編 『パリの女は産』まなくなった?
2025.02.05
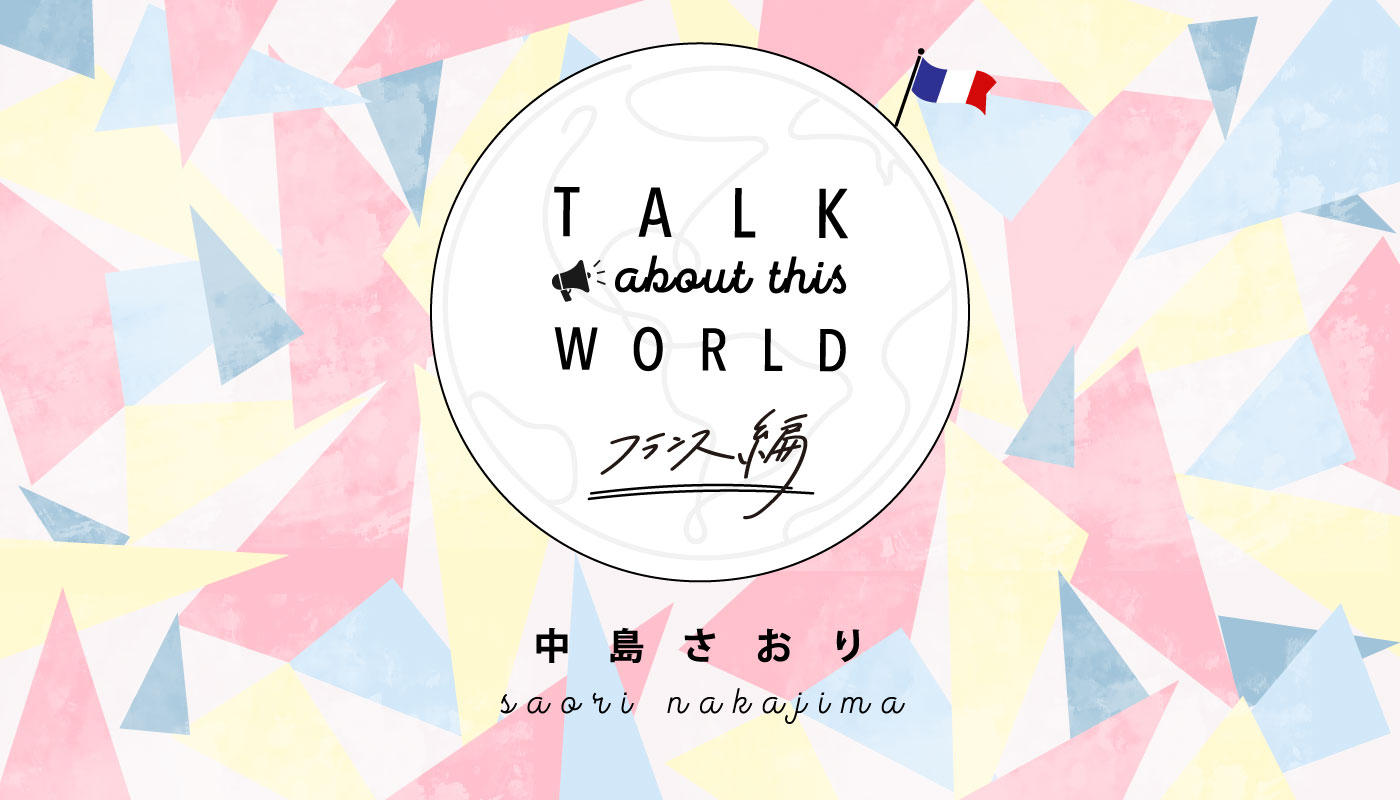
フランスは長いこと、出生率に関して、「例外」の国だと認識されていた。低出生率に悩む先進国の中で突出して子どもが生まれる国。そう自他ともに認めていたのだが、このところその栄光に翳りが差している。
この1月にINSEEが発表したところによると、2024年の出生数はおよそ663,000人で2023年に比べてマイナス2.2%。そもそもその2023年が前年比マイナス6.6%と大きく落ち込んで衆目を驚かせたのだから、この傾向がダメ押しされたのは意味深い。ピークの2010年に比べると、出生数はなんと21.5%も減っているのだそうだ。フランスもいよいよ少子化国家の仲間入りかと心配する声も漏れる。
私は1999年にフランスで出産し、その頃みるみる子供の産まれる国になって行ったフランスのことを『パリの女は産んでいる』という本に書いた。1人の女性が生涯に持つ子どもの数を算出した合計特殊出生率は2010年には人口再生産に必要な2%を超え、それを頂点に減少し始めたが、10年代を通じて1.9あたりの高水準を保っていた。2020年代に入ると、コロナで増減しつつ漸減したが、2022年には1.79と、それほど低くない水準を維持していた。それが2023年に1.66に急落して、第二次世界大戦後最低を記録したと騒がれた。驚いたマクロン大統領が「出生軍備強化(この人は何かと言うと戦争関係の語彙で比喩表現を使う)」をすると言ったが、ご存知のようにその後の政治の混乱もあって具体的には何の対策もなしで現在に至った(なんせ大統領が突然議会を解散してしまって総選挙をした後、何ヶ月も新しい首相が任命されず、ようやく任命された首相は数ヶ月で内閣不信任案可決で辞職し、2025年の予算案も通らずに年を越したのだ)。2024年は1.62と最低値を更新し、「第一次世界大戦直後以来」まで一気にその記録を遡らせてしまった。
子どもを持つ持たないはとても個人的な問題なので、その選択に何が関連しているのか、検証してみることはなかなか難しいが、こうまではっきりした変化があると、みな原因はなんだろうと考える。
私がすぐに思いつくのは、若い人たちは環境問題に敏感で、地球温暖化が進んで何がどうなるかわからない地球に暮らす次の世代を生み出すことに躊躇するからではないかということだ。これはそうだと言う人もいるが、あまり関係ないと言う人もいる。
それよりも、今現在の経済状況が原因だという意見の方が強い。若者のマジョリティは子どもを持つ意志はあるが、物価の高騰、雇用の不安定で、安全に子どもを育てられる基盤がないので踏み切れないという説だ。そうであるなら、出生率向上のために政治の介入はまだ有効かもしれない。
面白いのは、フェミニズムが進んだせいだという説だ。フランスの女たちは仕事を続けながら子どもも育て、キャリアと母性を両立させて来たと言われているけれども、そこには妥協もあった。女性は仕事が続けられて家庭生活も両立させられることに満足して、キャリアの追求はほどほどにして諦めていた。
子どもの数と男女の給与差という統計があって、それによると子どもがない場合は14.9%、子ども一人の場合は21.72%、二人の場合は29.2%、3人以上になると42.8%の差になるという。
私も実際に、私の子どもたちと同年代の子どもの母親たちを何人もインタビューしたが、「子どもを持ったことに後悔はないけれど、もしいなかったらキャリアはもっと上まで行けた」と言う人が何人もいた。だが、下の世代、今、親になるような世代の女性は、もっと平等意識が強い。「夫よりキャリアが下でも子どもがいるから構わない」とはもう思わない女性たちは、育児の負担が真に平等にならないならば子どもを持たない選択をする方が自然なのかもしれない。
かつてフェミニズムが高まり、女性が大挙して仕事を始めた時、フランスの出生率は下がった。その後、託児制度や子育て家庭への経済支援などを整えることで女性は仕事を辞めずに子どもを持つことができるようになり、出生率は上がった。しかしここへ来て、現在の制度ではもう不十分になって来た、本当の男女平等が実現されなければ、女性は産む選択をしないということだろうか。
実際、子どもを産まなくなっているのははっきりと経済的に中間層の女性であって、最も富裕な層と最も貧しい層では子どもの数が減っていないのだそうだ。富裕層は子育てを乳母などにアウトソーシングでき、仕事を持たない女性は自分で子どもの面倒を見る。産まなくなっているのは、その中間にある、普通の働く女性たちだという。
だとすれば政治は、彼女たちの負担を減らすべく、質量ともに保育園の拡充を図ったり、子育て支援の経済的扶助を増やしたりすることを対策として実行すれば良いことになる。
ブルターニュの小さな町の町長さんは、毎年20人くらい生まれていた赤ん坊が14人に減ったのを嘆いて、今までぬいぐるみだった出産の贈り物を2025年から金塊にすると年始の挨拶で言って物議を醸した。これは「冗談だった」とのことで、どうも実行されないらしいが、そのくらいやったら、もしかしたら産もうという人もいるかもしれない。
しかし実際のところ、お金の問題だけなのだろうかと私は思う。子育ての負担をアウトソーシングして、男女ともにキャリアを追求できればうまくいくのだろうか。そもそも子どもが生まれないのは、子どもを育てることを決心するだけの安定したカップルが減っていることが問題なのだと指摘されているが、安定しないのは経済的基盤だけが理由なのだろうか。
私は、子どものあるカップルが二人で同じようにキャリアを追求したら、保育園が充実しても、家庭はあまりうまくいかないのではないかと思う。子育てと仕事は、両方することはできるが、両方とも全力投球することはできない。それでもいいと思う人がいなければ、家庭は成り立たないだろう。その負担が女性にだけかかるのは理不尽で、やりたくない女性が無理をするべきではないけれど、その分、子育てを仕事より優先したい男性がいればいいのではないか。会社での仕事や出世に汲々とするより、子どもの成長を見守ることの方に意義を見出す人が、女性だけでなく男性の中にも、いるのではないだろうか。ベビーカーを押したり、学校のお迎えに行ったり、保護者会に出席したりする男性を目にするのはごく普通のことになった。それを見ていると、男女の力関係や役割分担が変わることが、安定して子どもを育てられるカップルを作る最も現実的な方法のような気がしてくる。
自分より妻の収入が高いことが耐え難い男性や、キャリア志向の女性が自分よりさらに高収入の男性でないと一緒になれないと感じたりするような、古い感受性が一掃された時には、もう一度、出生率は上向くのではないかなどと思ったりする。
合計特殊出生率1.62は、日本の1.20よりずっと高いし、この数値でもヨーロッパではいまだに高い方に位置している。また、移民受け入れによってフランスの人口そのものは増加しているので、フランス人たちがどこまで心配しているのかよくわからないが、何もしなければしばらくは出生率低下が続くだろう。