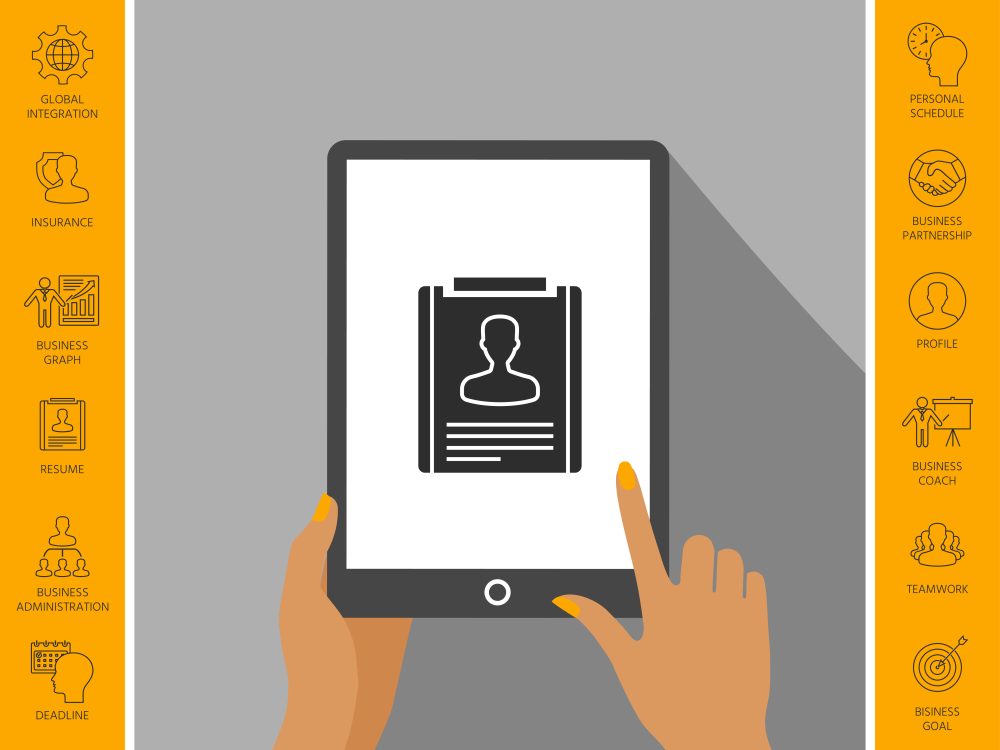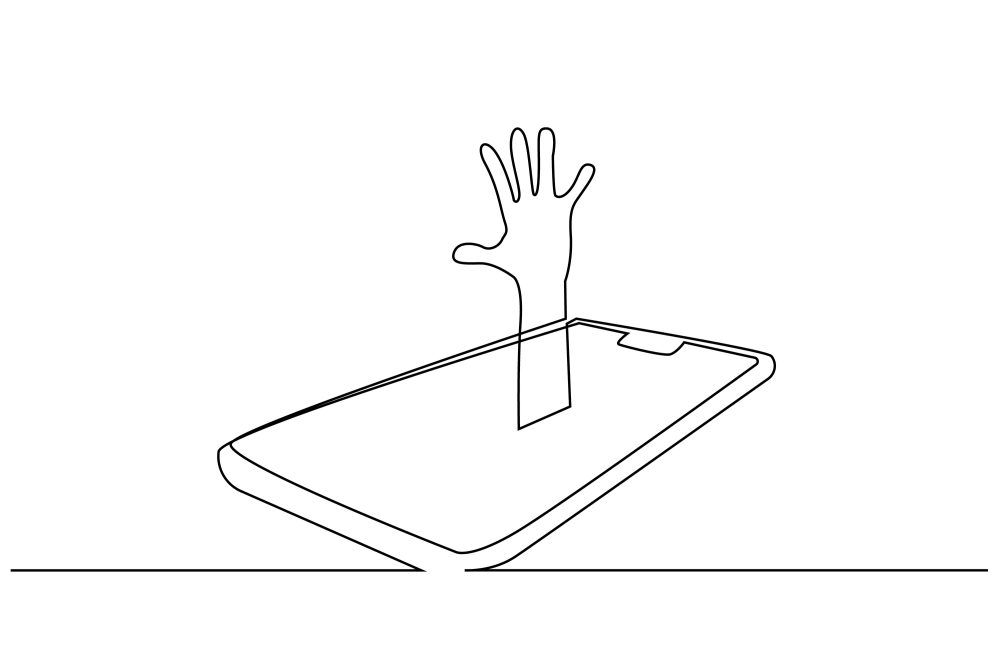10月11日は、「国際ガールズデー」だった。東京でも「国際ガールズデー」にちなんだイベントがいくつか行われていた。参加可能なイベントに行ってみたが、イマイチ盛り上がりに欠けていた印象を受けた。まだまだ「国際ガールズデー」自体が知られていないのだろう。もっと盛り上がるイベントになるといい。ハロウィンの、一部常軌を逸した騒ぎ方をするエネルギーを、「国際ガールズデー」に向けられないものか。
日本の伝統でも何でもないハロウィンが、これほどまでに活況を呈し、いまやクリスマスを上回る売り上げとなっているらしいが、私が子どもの頃は、仏教の行事に「おせったい」と呼ばれるものがあり、子どもが家々からお菓子をもらっていた。
「おせったい」は、漢字で書けば「お接待」。「お接待」は、四国巡礼でも巡礼者に対して行われているようだが、私の地元では、お参りに来た子どもにお菓子をあげる風習のことを「お接待」と言っていた。小学生の頃、年に一度、「お接待」をしている家に小銭を持ってお参りに行き、お菓子をもらったことを思い出す。いまでもこの風習が残っている地域もあるようだが、消えゆく行事ごとの一つだろうか。
お菓子と言えば、道徳の教科書で「パン屋さん」が「和菓子屋さん」に変えられた話があったが、「和菓子屋さん」は、このハロウィンを商機に繋げているのだろうか。ハロウィン商戦では、洋菓子屋さんに軍配が上がりそうな印象を受けるが、どうだろう。
この「和菓子屋さん」、いま使っている現代文の教科書にも登場していることがわかった。いまさらながら「わかった」のは、現代文の教科書は二年間使用する扱いで、内容は第一部と第二部に分かれていて、昨年度の第一部は別の担当者が授業をしていたからだ。和菓子屋さんの話は、第一部に入っていた。教材研究として、年度当初に全ての教材を通読しておくべきだったが、昨年度の第一部の授業では、和菓子屋さん教材を扱っておらず、読み飛ばしていた。
和菓子屋さんが登場するのは、『芋ようかん』という内海隆一郎の小説だ。「おばあちゃん」が頑張って続けてきた和菓子屋さんの定番の和菓子「芋ようかん」を、採算が合わないからと息子の代になってやめてしまうが、「芋ようかん」の根強いファンがたくさんいて、「おばあちゃん」が奮起。息子には内緒にして再び芋ようかんを作って売り始めるが、そのことに気づいた息子が激怒して、やめさせようとする。それに対して「おばあちゃん」が、息子に向かって久しぶりに大声で怒鳴る。以下数行、本文を引用する。
(息子が)「それじゃ、お母さんが元気なうちだけだぞ。」
ようやく威厳を保って、言い渡した。
そこでまた、嫁がすかさず言った。
「お母さんの次は、私が作るわ。」
すると、孫娘まで胸を張って叫んだ。
「そのまた次は、私が作るう。」
おばあちゃんは、二人を眺めてほほえんだ。
いやぁ、「伝統文化の尊重」教材がここにもあったかと、今更ながら驚いた。
三世代同居の和菓子屋の伝統美(?)。家父長制の名残もほのかに感じさせる息子の言動の描かれ方。実は、いま第二部で扱っている小説にも、「伝統文化の尊重」教材(?)なのかと、違和感を禁じ得ない思いで授業に臨んでいるものがある。それは、『破船』という吉村昭の長編小説だ。
この『破船』、江戸時代の北陸(新潟の佐渡あたり)の伝統漁法「さんまの手づかみ漁」とその歴史に着想を得た小説らしい。全文を通読すると見えてくる主題は、教科書に掲載されている一部分だけだと、見えては来ないという。それでも、教科書収録の部分で読む価値はあると、教員用の指導書は説く。いったいどんな場面が掲載されているかというと・・・。
「海辺の村は貧しかった。時に難破する船から、村人たちは生活の糧を得ていた。伊作の父は、生活のために年季奉公に出ていて、三年は帰ってこない。十歳になろうとする伊作は、家族の中で年長の男となった。」
冒頭の場面説明の教科書の文章だ。「時に沖で難破する」と記述されているが、実際の小説では、村人が灯をともして船をおびき寄せ、わざと座礁させて積荷を奪うことになっている。年季奉公の父親は、実は「身売り」をしての年季奉公だ。
小説本文に入っていくと、十歳に満たない主人公の伊作が、母親、弟、妹のために、伝統漁法である「さんまの手づかみ漁」で何とかしてさんまを手に入れようと奮闘する姿が描かれる。貧しいが故、「他の者に漁法を教えるゆとりなどない」村人。
十歳に満たないのに、「他人のあわれみにすがらねばならぬ立場に身をおきたくはなかった」という主人公、伊作。
「頼りになるのは、従兄の太吉だけであったが、所帯を持った彼が、自分に漁の仕方を教えてくれるかどうかは疑わしい」という状況にあって、「しかし、伊作は家族を飢えにさらすわけにはゆかず」、太吉に教えを請う。
この太吉に対して伊作は、「十七歳の太吉がすでに一人前の漁師になっていることを感じた。母を養い、さらにくら(妻の名)の夫になった彼は、戸主としての責任感も強いのだろう」というまなざしで見つめる。
太吉に教えを請うてはみたものの、さんまは一尾も取れず、伊作は漁から帰宅。そんな伊作に対して母親は「黙ったままだった」「母は漁についてはいっさい口にせず、薄めた雑炊を作って弟と妹に食べさせていた」。その後、試行錯誤を繰り返し、ようやく一尾のさんまを捕まえることができた伊作。母はそのさんまを四等分にし、串焼きにする。
「母が頭の部分を突き刺した串を彼(伊作)に渡し、他の三本を弟妹と分けた。伊作は、頭を渡してくれた母が自分を家の働き手として認めてくれているのを感じた。熱いさんまは、うまかった。肉を食べつくし骨をしゃぶっている弟や妹の姿に、今後もさんまを家に持ち帰らねばならぬ、と思った」。で、教科書本文は終わる。
この小説、主人公伊作の心の変化をつぶさに追っていくことに加えて、指導書に書かれている教えるポイントの中に、次のような項目がある。
・伊作の太吉を見つめるまなざしの「一人前の漁師」「戸主としての責任感」という言葉に注目させる。
発問例には、
・母が漁についていっさい口にしなかったのはどうしてか考える。
その部分の指導書の解説はこうだ。
「母が漁についていっさい口にしなかったのは、漁は男の仕事であり、女が口を出すところではない。期待はしているが、さんま漁がそれほど簡単なものではないこともよくわかっているから。女である自分が男の仕事である漁のことにいちいち口出しすべきではないという気持ちが働いたから。『いっさい』口にしなかったのは漁が『男』の領分だからである」。
こんな「模範解答」を板書すれば、生徒たちは素直にノートに書き写すだろう。それがこの本文を掲載した教科書会社のねらいか、いや、文部科学省のねらいか・・・。実際、初読の感想を生徒に書かせたところ、「なかなかさんまが取れなかったが、最後に取れてよかった」「十歳にも満たない伊作が、家族のために頑張っているのだから、自分も高校卒業後、頑張ろうと思った」などといった感想が出された。
やはり・・・と思って、「では、この小説を批判的に読んだり、いまの時代と比べたりしたら、どのような見方ができるか。いまの時代に繋がるところはないかなど改めて考えてみよう」と投げかけたところ、かなりしばらく考えた後で、「いまの時代なら、児童虐待じゃないか」「母親は何をしているんだ」「伊作はもう十分がんばった。大人に甘えていい」「いまなら、生活保護などの社会福祉に頼る方法がある」といった発言が出てきた。
十歳にも満たないのに「年長の男である」というプレッシャー、いまも、自殺に追い込まれるのは弱音を吐けない男性に多いこと。東京医科大学などの入学試験で行われていた「男子に加点する伝統」。女子も生活力を持つ必要があること。伝統の中には、受け継いでいくべきものと、変えた方がいいものがあること等など、話題は多岐にわたった。教科書「を」教えるか、教科書「で」教えるか。「伝統文化の尊重教材」がてんこ盛りの教科書で、いまの教育は日々行われている。