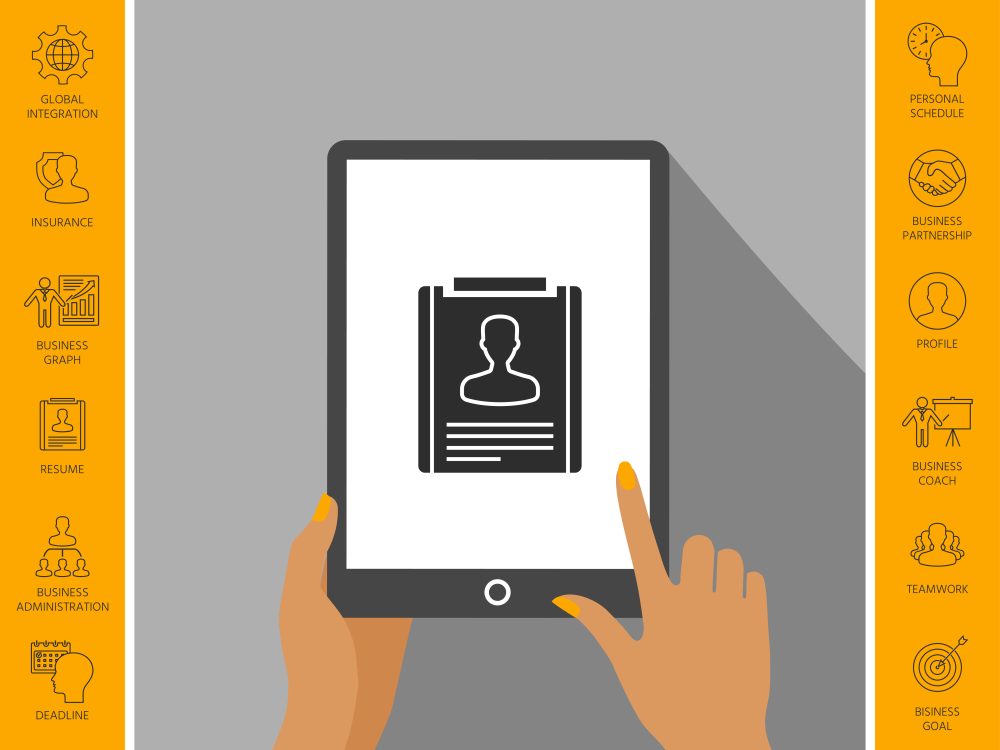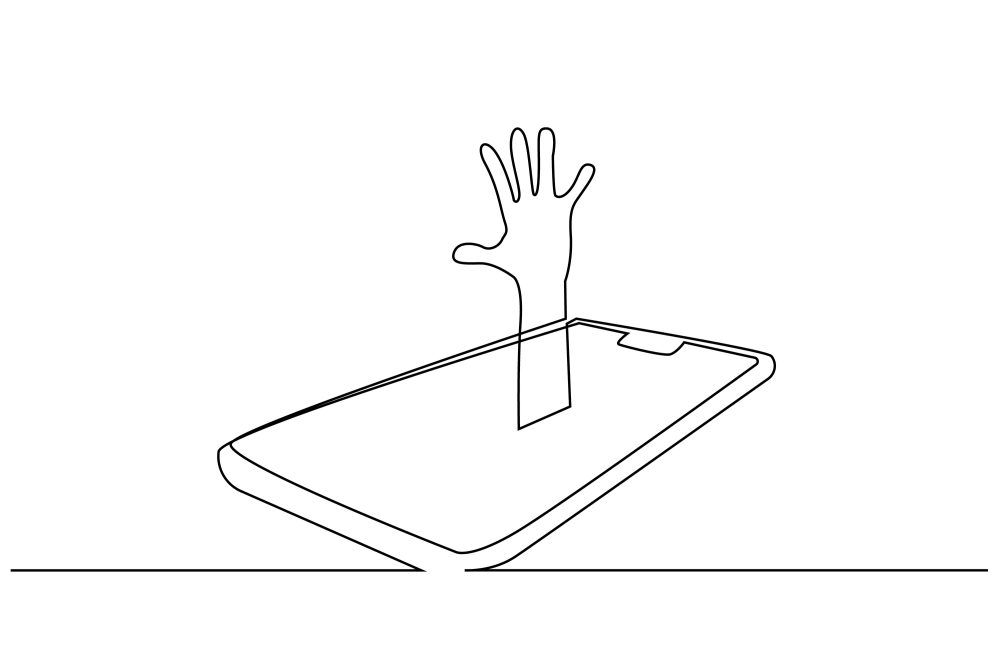『言えないことをしたのは誰?』(上下巻 さいきまこ著 2024年7月10日 現代書館発行 定価各1900円+税)を読んだ。保健室・図書館におきたい一冊だ。子どもたちにも読んでほしいし、教職員も読んでおくべき内容だ。この漫画は、ウェブでも大反響だったらしい。
同業者として腹立たしいが、スクール・セクシュアル・ハラスメント(以下「スクールセクハラ」)は根絶されていない。被害に遭った生徒のことを思うと、いたたまれなくなる。職場でスクールセクハラ防止の服務規律研修は年度末、年度始め、各学期と毎年複数回行われているが、スクールセクハラの被害はなくなっておらず、そのたびにスクールセクハラ防止のための緊急職員研修も入ってくる。
スクールセクハラなんて絶対にしない人にとっては、「またスクールセクハラ防止研修か…。」と思ってしまいがちだろうが、数カ月ごとに研修を行うことによって、スクールセクハラ防止が常に意識されることにつながるから、被害者・加害者を出さないために必要な研修だろう。
冒頭に紹介した『言えないことをしたのは誰? 』は、スクールセクハラが起きる背景・状況や加害者、被害者のことをわかりやすく描いている。
スクールセクハラが起きる背景には、教員と生徒との権力関係がある。当然のことながら、教員は生徒に対して圧倒的に立場が強い。教員は生徒を支配する側になる。教員の言うことを正しいと思っている生徒も多い。教員から言われたことを、生徒が信じて疑わない傾向にあるのだ。
その立場を利用して、加害者は生徒を自分の思うように操り、スクールセクハラ=性加害をする。性加害を受けた生徒は、加害者の言いなりになり、「二人だけの秘密だ」などと言われると誰にも言えず、スクールセクハラが発覚するのが難しくなる。
スクールセクハラが起きる場所は、生徒と二人きりになれる密室であることが多い。だから、教員が生徒を自家用車に乗せることを基本的に禁止している。車以外でも、放課後や週末等、進路指導や部活動の個人指導と称して二人きりになる時間を、加害者は意図的に作ろうとする。
スクールセクハラ防止の職員研修では、面接指導等で生徒と二人きりにならないよう、また、生徒とSNSでやりとりしないよう注意喚起している。生徒と教員の一対一対応でなく、複数対応を要求したり、二人になる場合はドアを開放したままで指導したりするよう促している。
こうした注意事項は、教職員にだけ伝えるのではなく、生徒自身にも情報提供する必要があるだろう。密室で教員と二人にならない。二人きりで指導を受けるときはドアを開放する。そうした意識をさせるだけでも、加害をしようとする教職員の行動を止める可能性が出てくる。
そのためにも日ごろから、生徒に教職員を批判的に見る視点を育てていきたい。批判的に見るのは教職員だけでなく、教科書やマスコミ、SNS等に溢れる情報も含む。「本当かな?」「それは正しいことなのかな?」と立ち止まって自分で批判的に考える習慣を身に付けさせておきたい。
次に、スクールセクハラの加害者についてだが、加害者は「まさかあの先生が、そんなことするとは思えない」というような、一見人当たりの良さそうな、いわゆる「いい先生」であることが多い。DVもそうだが、あんなに優しそうな人が」「あんなに立派な人が」と言われるような人も、加害者であることが多々あるのだ。
筆者の父もDV男だったが、近所の人からは「優しくて世話好きの、いいお父さん」というイメージを持たれていた。その正体が酒に酔って母に暴力を振るう男だとは、近所の人は誰も気づいていなかったし、信じてもらえなかった。
スクールセクハラの加害者も、教育熱心で指導力があって生徒から慕われている教員であることが多い。教育熱心な教員だからといって性加害をしないとは限らないし、生徒から慕われる教員だからといって性加害をしないとは限らない。
そして、スクールセクハラの被害は誰にでも起こりうる。スカートが短いからとか、隙があったからとか、かわいいからとか、そんなことは関係ない。ジャニーズや宗教施設での加害の実態を見れば分かる通り、男女問わず被害に遭うおそれがあるのだ。被害者に落ち度はなく、悪いのはあくまでも加害者だ。被害者の心身の傷は深く、治るのに長期間かかる。フラッシュバックや希死念慮、解離性人格障害などにさいなまれる被害者もいる。
『言えないことをしたのは誰? 』の作者と斉藤章佳さん(『子どもへの性加害』著者)との巻末のスペシャル対談も非常に参考になる。加害者の意識に「そこにあるから、する」「加害者に被害者のことを想像してみてくださいと言うと、のっぺらぼうの顔になる」というのが特に印象に残った。相手をモノとして扱う加害者意識だ。被害者に対して、一人の個人として人格があり、家族があり、生活があり…との思いは、加害者にはない。
このことは『性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うなかれ』の共著者、にのみやさをりさんも『週刊金曜日』1495号(2024年11月1日号)で語られていた。にのみやさんは、性暴力被害者として加害者と対話し、往復書簡を続けている。にのみやさんによると「加害者は被害者をモノ化してしまうというか、加害をゲームのように感じていたりして、被害者を『ひと』と思っていなかった」「『ひと』ではないから加害行為ができた」と。
相手のことを人格ある一個人として認めて想像力を働かせること。そのことが、性加害をなくし、暴力をなくし、ひいては戦争なくしていくことにつながっていくと信じている。