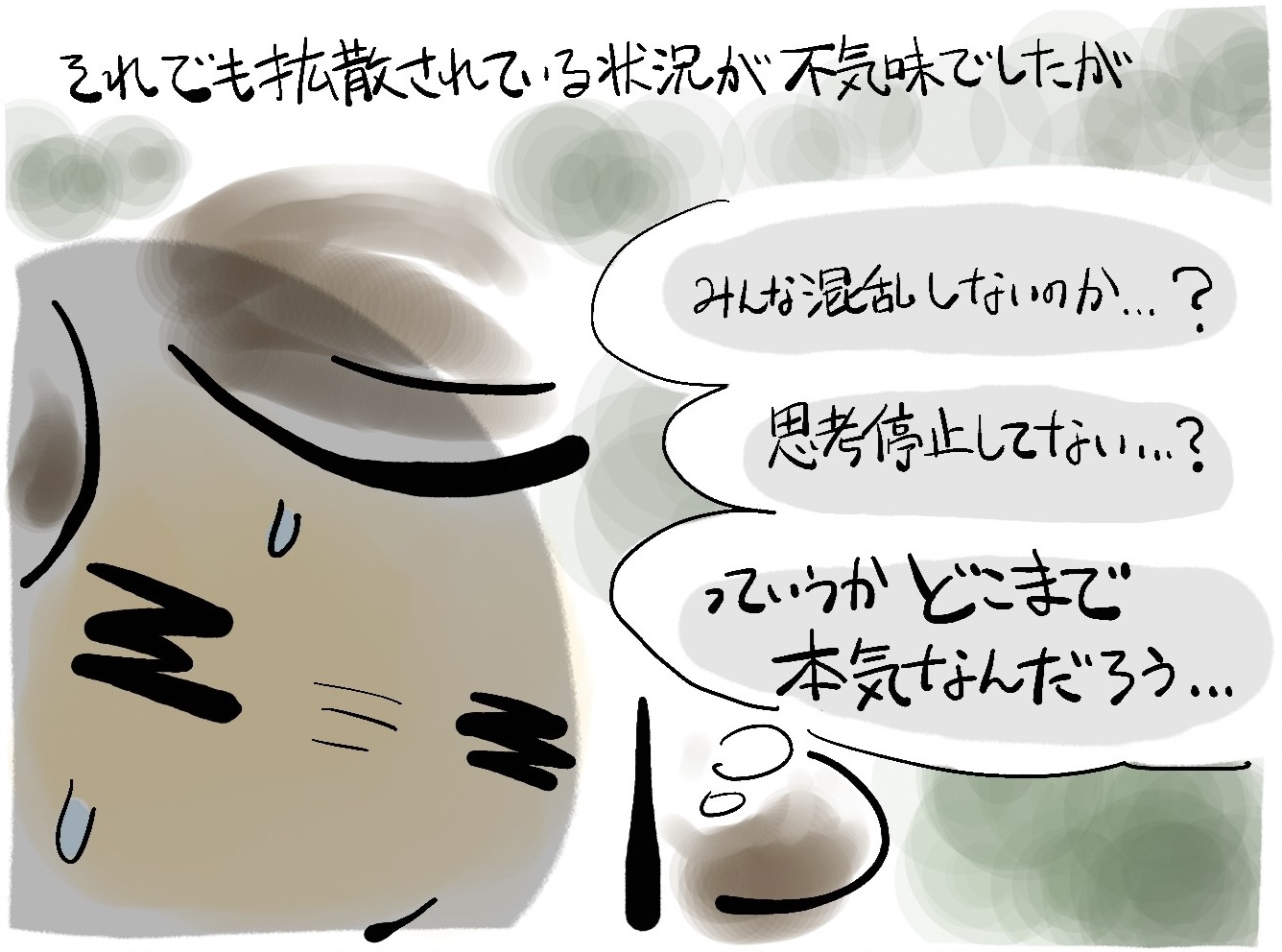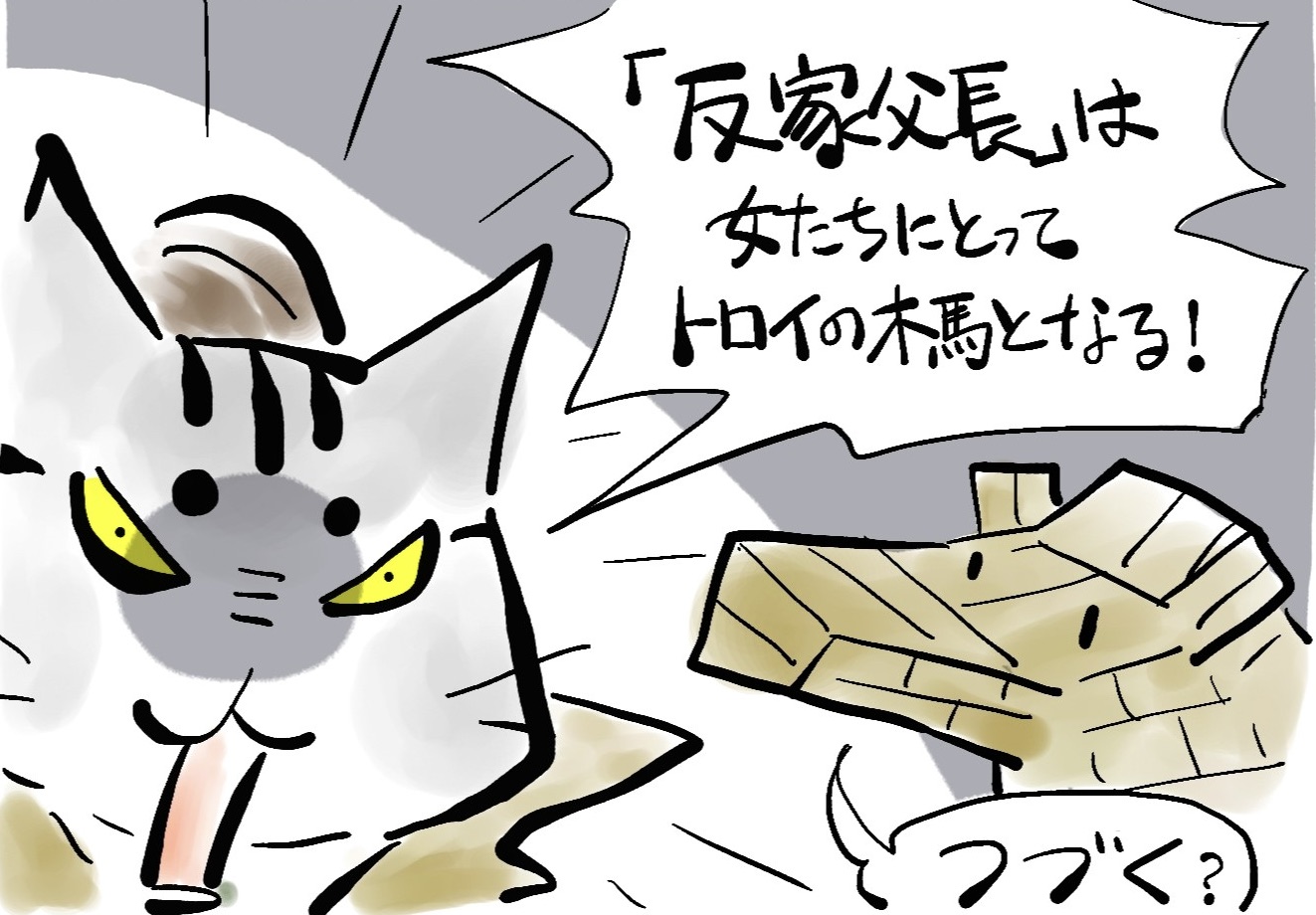TALK ABOUT THIS WORLD ドイツ編 守られなければならないもの
2024.11.25

10月21日付の報道で、伊藤詩織さんが監督し、イギリスやアメリカなどで劇場公開が始まった新作のドキュメンタリー映画「Black Box Diaries」の中で使用した一部の映像や音声について、彼女の性被害事件の裁判で代理人だった弁護士から訴えが出ていることが明らかになったことは、おそらく多くの人に衝撃や疑問を与えただろう。まだ伊藤さん本人のコメントが公表されていないので、落胆とまではまだ言いたくない。
事のいきさつはここでは書かない。まだ知らない人は、各所で報道されているのでそれらの記事を読んでほしい。私自身は、伊藤さんの性被害の裁判の際に代理人であった西廣弁護士の会見内容の他、実際にこの映画をみた評論家たちの批評やコメントも2つほど、読んだ。すでに今年初頭から日本以外の国の映画祭などで上映されてきたこの映画作品そのものへの評価は大変高く、次回のアカデミー賞のドキュメンタリー部門のノミネートの可能性もあるという。実際に観た評論家いわく、まさに今回問題となっている映像や音声が使われたシーンがこの映画にインパクトと説得力を与え、全体の構成を支えている重要なシーンなのだそうだ。未見なのでそれがどのようなものかは私からは書けないけれども、映像の世界に片足を突っ込んでいる私も知っていることはいずれにしても書いておきたい。
映像の力というのはしばしばとてつもない暴力性を伴う。それはフィクションであってもドキュメンタリーであっても、映像の中の登場人物はさることながら、映像の外側にいる観客も共に、心を傷つけられ、ときにそれはそれぞれの人生を揺るがしかねないことすらある。そもそもの映像の力がそれだけ暴力的になる危険性の上に、映画が公開されて多くの目にさらされることになれば、さらには関わる人のブライバシーの侵害という暴力も加わり、そして一旦外に出された情報は二度と回収できない。それは映像作品のみならず、どのジャンルやメディアであっても、何かを作り公表する立場のものが知っておかなければならないことである。すでに何本かの映像作品を制作し、自身もメディアに出て国際的に活動するジャーナリストである彼女がそのことを知らずにいた、気づかずにいたとは思えない。
だから私の推測として、彼女は作り手としての立場において、人を傷つけ、自分が訴えられるリスクを承知でそれらの映像や音声を使用する決断を貫いたのではないかと思う。それほどの危険を冒してまでも彼女がこの映画で伝えたかったのは何なのか、それはこの映画を見ていないから私には語ることはできない。それでも、その作り手としての情熱や執着のあまり、その「誘惑」や「エゴ」に負けたのだろうかとも思う。
#Me Too運動がこの何年か、有名な映画の制作現場で過去に行われてきた性犯罪を暴き、告発してきた中で、本当に残念だけれど、今回伊藤さんが監督として行ったことは、種類は違えど、相手の権利を侵害する、という意味では同じことになってしまった。映画に限らず、創作において作り手のエゴで周りが傷つくことがあっても、その結果が全てとされる作品至上主義は歴史の中でしばしば起き、容認されてきた。そして悲しいかな、そんな背景があっても作品としては高い評価を得たり、実際、心を打たれるものがあるのもまたしばしば起きることだ。#Me Too運動で告発された映画の関係者の名前があがるたび、ああ、そういうこともあったんだろうなと想像にたやすいと納得しつつ、作品とその背景の残酷な事実に挟まれて考え込んだのは私だけではないはず、女性男性問わず、多くの映画ファン(またはそのほかのジャンルのファンでも)にもいただろうと思う。
今回の伊藤さんの件は、西廣弁護士の言うように、彼女自身の問題だけではなく、今後将来的に、同じ被害状況にいる人たちへの救済を難しくしてしまう点でも、彼女は大きな責任を背負わなければならなかったはずだ。西廣氏の会見では、傍聴側から「ジャーナリズムにおけるプライバシーの侵害の許容」についての質問も出たという。申し訳ないが、そんな質問を投げるとはジャーナリスト自身がジャーナリズムをわかっていないのではないかと呆れてしまう。確かにその問題は例えばジュリアン・アサンジュの勾留や著名人の犯罪事件についてもたびたび聞いたキーワードだ。しかし今回の件において、本来だったら守られるべき、多くの一般の被害者たちの権利が、伊藤さんの行動によって危険にさらされかねないという点においては、アサンジュの件とは全く違う。
ジャーナリズムやドキュメンタリーというジャンルではなおさら難しいのかもしれないが、しかし何か伝えたいメッセージがあるとして、それを届けるための手段は一つではない。真実を語るために事実の記録を使うことは必要かといえば、必ずしもそうではない。つまり、直接的に記録映像を使うという手法以外にも、他の手法を試みてほしかったと思う。それは映画監督、作り手としてのクリエイティビティの問題でもある。他人の権利を犯すリスクを知っていながらも伝えなければならなかった思いとは何なのだろうか。彼女自身の体験を訴えることは尊重すべきだが、しかしそれを表現する際に他の被害者たちの権利を無視してもよいということになれば、それは表現者としての彼女のエゴと捉えられてしまいかねない。(もっとも、前述のように、そんなエゴゆえに人を惹きつける作品があるのだから厄介なのだけど…。)きっと自らが抱えてきた熾烈な怒りや悲しみ、苛立ちを記録し、表していたのはそれらの記録映像だったのだろう。気持ちはわからないでもない。でも伊藤さんにはやってほしくなかった。表に出て戦ってきて、同じ苦しみを抱える人たちを勇気づけたであろう彼女のこれまでの行動が、ここにきてその人たちを困難に陥れてしまうリスクを作ってしまった。本当に残念でならない。

©︎: Aki Nakazawa
写真は、かかりつけの歯科医のトイレのドアに貼ってあった、家庭及び市民社会連邦局が発行しているドメスティックバイオレンスなど暴力を振るわれている女性のためのSOSの電話番号のポスターです。「匿名、無料で24時間、各言語で対応」と書かれており、電話番号をちぎって持っていけるような仕組みで、ドイツ全国の街中のカフェなど、様々なところで見かけます。差し迫った危険の中でも人に助けを求めるというのがいかに大変なことであるか、このポスターを見るたびに思います。匿名であるゆえに告発できる事もある、それを考えると、やはり今回の映画の問題について西廣弁護士が訴えているのはそうした背景が現実にはあるからだと思うのです。
創作における他人の権利の扱い、という、私自身もたびたびジレンマを感じたり、直面する問題で、思わず筆を取り上げました。伊藤さんの気持ちはわからないでもないです。しかしやはりやってはいけないことであったと思う。これが前例とならないよう、すべてのジャンルにおける作り手たちが再考するするべき機会だとも思います。一つ、付け加えたいのは、直接的な情報はインパクトがありますが、本来、人間には想像力というものがあって、いかにこの想像力の効用を信じて作るか、それこそクリエイティビティです。ただジャーナリストでも映画監督という肩書きでも創作という立場に立つ以上、そのクリエイティビティは問われるべきと思います。