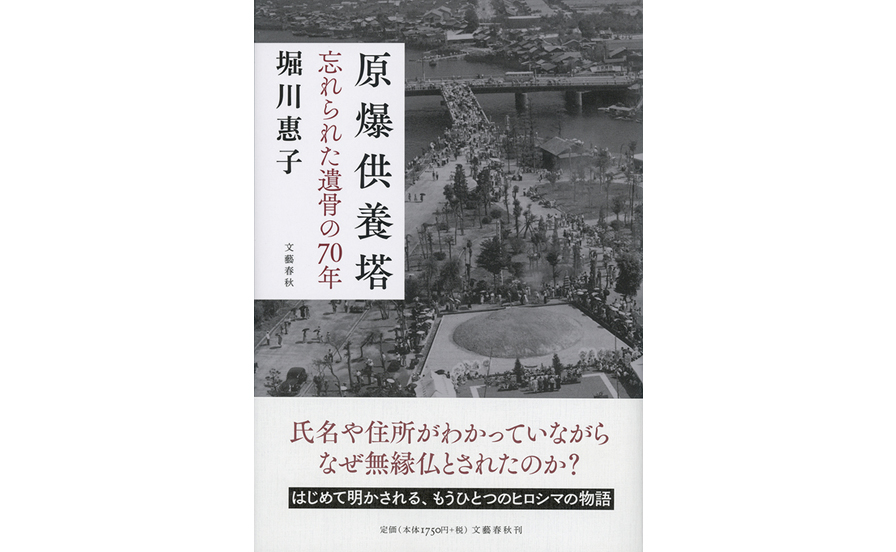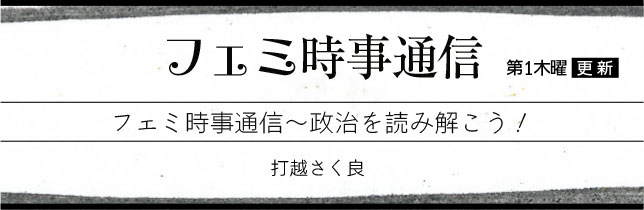
「配偶者控除」とは
政府税制調査会が9月9日に総会を開き、配偶者控除の見直しなどを議論し11月にも提言をまとめると報じられている(毎日新聞2016年9月1日21時15分(横山三加子記者))。
専業主婦ないしパートの妻がいる世帯主の税負担を軽減する配偶者控除。今を去ること55年前の1961年に導入されたこの制度は、高度成長期は主流と目された「夫はサラリーマン、妻は専業主婦」という世帯を支える―裏返せば、共稼ぎ世帯や単身世帯より有利扱う―仕組みである。
半世紀以上も続くこの制度は所与のものと疑問に思わない人もいるかもしれない。しかし、決して当然でない。各国は、世帯の形態が変化しても、個人の収入が変わらない限り同額の税負担となる個人単位課税に改正している(オーストラリア、カナダ、イタリア、デンマーク、スウェーデン、ニュージードなど)。
なぜ、このような制度があるのだろうか。迂遠なようだが、所得税法の歴史を復習してみよう。
戦前の所得税法では、同居の家族の所得は、戸主の所得に合算しなければならないとされ、「イエ」を単位とした課税が行われていた。敗戦後、1946年の日本国憲法の公布を受け、民法が個人の尊厳と両性の本質的平等(憲法24条2項)にのっとって、イエ制度を廃止した。所得税法も1947年に「戸主」の後を抹消したが、代わりに「同居親族」という語を登場させ、実質的には世帯単位の課税制度が残されたままであった。
しかし、1949年のシャウプ税制使節団による日本税制報告書が世帯単位の課税制度を廃止し原則として個人単位の課税制度とすることを勧告したことを受け、1950年に所得税法が改正され、明治以来の世帯単位課税から個人単位課税にシフトした。しかし、いくつか世帯として課税される例外が残された。その例外は廃止されたり、新たな制度がもうけられたりした。世帯単位の例外のひとつとして、事業所得者が家族従業員に支払う給料を必要経費とされることのバランスから、サラリーマン世帯の妻の「内助の功」を評価するとの立法趣旨のもとに、1961年に創設されたのが、配偶者控除である。
高く評価する意見もあったが、早々に批判にもさらされた。たとえば、「内助の功」を評価すといっても、世帯主の所得から控除を差し引くので、所得の高い人ほど減税される金額が多くなる。しかし、世帯主の所得の高低と、家事育児介護などの労力の大小は全く関係ない。しかも、減税されるのは、世帯主である夫であり、直接「内助の功」を果たした妻自身ではない。
そして、「片働き」世帯、「共働き」世帯、「単身者」世帯の税負担のバランスの問題。「片働き」世帯を選択するほうが税金の負担が有利になる(他の世帯を選択するほうが不利になる)、というのは、公平ではない。
廃止によって世帯間の公平が図られればいいように思われるが、「片働き」世帯にとっては負担が増えるように感じ取られる。また、「男が外で働き、女が家庭を守る」という固定的な性別役割分業こそ「日本の美しい伝統」と思い描く層からの反対もあった(女も男と一緒に家業を担っていたりしたので、専業主婦はごく最近の、地域的にも限られたライフスタイルなのだが)。
そうして、繰り返し繰り返し配偶者控除見直しの声が上がっては消えて、イマココ。たとえば、1996年7月の男女共同参画審議会の答申は、政策提言のトップに「性別による偏りのない社会システムの構築」という施策群を置き、具体的な取り組みとして、税制の見直しを提案した(が、同じく提案された選択的夫婦別姓と同様、改革は見送られた)。保守的な層からの人気が高い一方、「女性の活躍」「働き方改革」などを掲げる安倍政権が見直しに着手するとしたら、興味深い。
「配偶者控除見直し」は女性支援?
配偶者控除は、女性を年収103万円以下に仕事に押しとどめる要因になっていた。この控除の恩恵を夫が受けられるよう、「あと何時間」と働き方を調整してきた女性たちがいる。
また、「女性は103万円の壁にこだわって働いているものだ」ということが、時給を低く抑える要因ともなっていた。単身や女性自身が世帯主だったりして、低い時給に甘んじてはいられない女たちもが、低い時給の仕事を掛け持ちすることでサバイバルしている、という事態もあった。
だから、各紙は「女性支援」「女性の就労後押し」といった論調をとるのだろう。
しかし、その論調に対しては、すぐさま「働く女がえらくて専業主婦が悪いというのか?」といった「女・女対立」としてとらえようとする言説があらわれがちだ。女性の働き方・生き方への制約は、男性の働き方・生き方への制約でもあり、こんな言説はあたらない。「男は仕事、女は家庭」という固定観念は、男たちには、職場では時間の制約があたかもないかのようにオーバーワークを強い、家庭その他での時間を極端に制限してきた。そして、専業主婦と働く女も固定的ではなく、実際には行き来してもいる。「女・女対立」は実際の投影というより、一種の演出ではないか、という指摘(ニッセイ基礎研究所生活研究部主任研究員松浦民恵「配偶者控除は見直しを―「女・女対立」の演出や先延ばし論を超えて」)は頷ける。
女性だけ働く時間を長くすることができたところで、育児や介護などのケアの時間を専ら女性が費やすのなら、女性個人が消耗するのみならず、女性が倒れでもしたらどうする(平成18年という古いデータだが、共稼ぎでも、家事の時間は夫1日あたり平均わずか25分、これに対し妻は3時間3分との結果がある!)。誰もが幼いときも、老いるときも、病気をしたり障がいをもったりして、ケアしたりされたりするときがある。特段病気などがなくても、身の回りのことをし、家事炊事もしなければ、生活が成り立たない。配偶者控除が廃止されても、結局女性のみがケア責任を負うなら、女性が過労死するか、結局は仕事をセーブするかしかない。配偶者控除は、男性の働き方の見直しをも迫る。いや、迫るというとネガティブか。男性もケアを負担しても奇異な顔をされなくなる。あまりに仕事に偏ったライフスタイルを修正しやすくなる(育休をとる男性に冷たいまなざしが向けられ、パパハラが横行する…なんてことがなくなる)。男性にとっても、生きづらい社会を変えるチャンスでもある。
ライフスタイルの選択に中立を目指していたはずが
と、意気揚々となりつつあったが、ん?配偶者控除見直しは、「夫婦控除」を軸に検討される、と各紙が報じている。ちょっと待った。思い出してほしい。上述のように、配偶者控除への批判は、どんな世帯、どんなライフスタイルを選択するかで有利不利となるのは公平ではない、ということでもあったはずだ。単身者世帯には不利で、「片働き」世帯+「共働き」世帯には有利、というのは、やはり同様の問題が残る。
ネットで検索すれば、家族の解体を促すような税法改正はいけない、「家族の絆」を強化するような、世帯課税制にすべし、という見解がヒットする。上記のような、世帯の形態にかかわらず、個人単位課税をとるようになり、家族のかたちに中立的な国が増えてきたというのに、だからこそ危機感が募るのだろうか。復古的な家制度的なものに郷愁を感じる層にも支えられる安倍政権は、結局、夫婦控除という中途半端なものを生み出すのだろうか。それは結局、ライフスタイルに中立的でも公平でもない。
教育等に比べて、課税ときくと、理念やイデオロギーとは遠く、無味乾燥なお金の計算のようなイメージがあるかもしれない。しかし、国がどのような家族形態こそあるべし姿として推奨しようとしているか、「家族のかたち」の理念化と密接に関係している。キラキラ報じられるとあたかも前進かのようにほっとしてしまいかねない。しかし、復古的な価値観の新たな押し付けや、家事育児などケアも引き続き女ばかりが担って仕事もして税金も負担しろという結果を漫然と生じさせないよう、注意深くウオッチしなければならない。
参考文献
全国婦人税理士連盟編『配偶者控除なんかいらない!? 税制を変える、働き方を変える』日本評論社、1994年
http://www.zsk.ne.jp/zeikei524/ronbun5.html