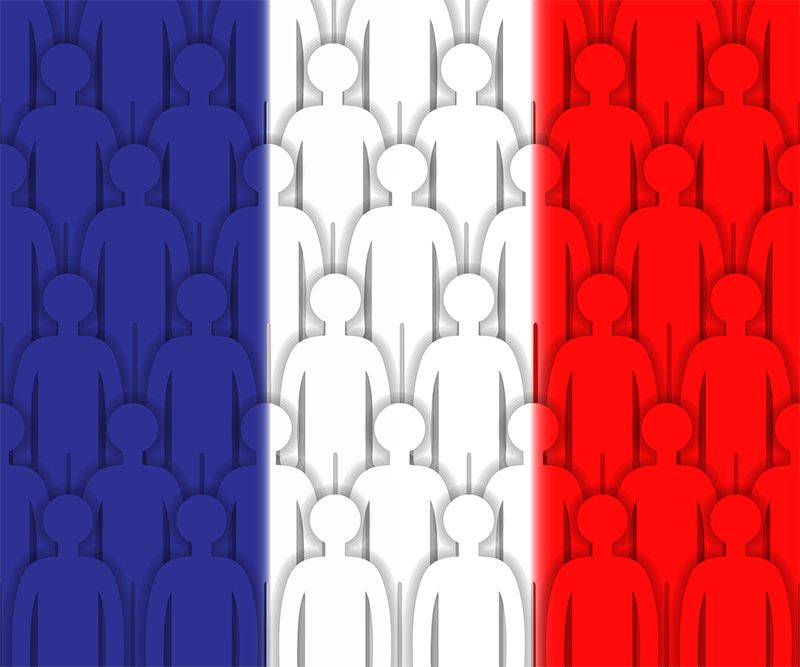TALK ABOUT THIS WORLD フランス編 映画『バービー』とフランス
2023.09.07

公開6週間で世界累計収益が13億6千万ドルを超え『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の記録を塗り替えた『バービー』。前回は『オッペンハイマー』について書いたから、というわけではないが、今日は『バービー』について書く。世界一有名なファッション人形をフェミニスト監督が取り上げた映画というのだから、「ラブピースクラブ」のコラムで素通りはできない。フランスのフェミニストたちが『バービー』をどう評価したか。
批評をざっと通覧した感じでは絶賛している人は多くない。
セットは素晴らしく、マーゴット・ロビーとライアン・ゴズリングの演技は良かったし、I’m just Kenの歌とダンスは爆笑ものだったけれど、映画自体はマテル社の巨大広告であったと言う意見が多い。
フェミニズムに関しては、評価する人は、「家父長制 (パトリアルカ)」という言葉がブロックバスターで10回以上も発音されるということ自体が注目に値することだと言う。深みはなく、不十分であるにしても、議論を喚起する役目は果たしたという。
しかし全てのフェミニストがそう肯定したわけではない。あるジャーナリストは、フェミニズム映画かどうかをはかる目安としてよく挙げられる「少なくとも二人の女性登場人物が、男性に関するのとは別の議論をしている」という基準に照らすと「映画の半分以上がこのテストをクリアできていない」と言っている。
「家父長制 (パトリアルカ)」のパロディはユーモアがあって楽しめたけれども、家父長制の害悪は、マンスプレイニングや女性を見つめながらギターを弾くなどという可愛らしいものではなくもっと暴力的なものなので、それが扱われなければ批判にはならないという真面目にもっともな意見もある。
また、レズビアンのバービーが出てくることはなく、へんてこバービーの扱いなどに、多様性を謳いつつ、限界があることなども大真面目に指摘されている。
こうした意見は批評家に留まらないようで、観客動員数は桁外れだけれども、一般にも評価はそれほど高くなかったようだ。映画のサイトで☆が三つちょっと。私の個人的感触では、日本での方が評価は高い。
とはいえ、評価に特別、フランスらしい特徴があるようには思われない。「男性との対立を表立たせるアメリカ流のフェミニズムに対して、フランスでは男性を味方にしたフェミニズムを展開する」とかつてものの本で読んだのだが、そういう見地からの批判は探してみてもほとんどないので、自分の持っていた知識の方が間違っていたのだろうと考えを修正しているところだ。時代が変わったのかもしれない。わずかにひとつ、「ケンでない唯一の男性があまり活用されていなかった」という批評を見たけれども、これをもってフランス的評価というわけにはいかないだろう。たしかに、ケンがバービーランドに持ち込んだ父権主義 (パトリアルカ) について行けず、逃げ出そうとして失敗し、バービーたちと一緒になってケングダムになってしまったバービーランドを取り戻す手伝いをするアランは特異な存在だが、その割にスポットは当たっていない。あれは何者だったんだろう、と見終わった後に疑問が残る人物だった。
登場人物で言えば、個人的にはフランシーが出てこなかったのも不満だった。フランシーは初期の頃のバービーのいとこで、きつい表情とグラマラスなボディの初代バービーに比べて親しみやすい可愛い顔立ちとスレンダーな体を持ち、私はバービーより好きだった。たしかフランス人だったはずだが、映画に出て来ないばかりか、フランスの批評に一度も登場しない。ひょっとしてあの人形は日本限定で売られていたのだろうかと疑問が湧いて、調べてみたら「イギリスからやって来たいとこ」という説明があった。服もモッズ・ファッションだとネットには書いてある。私の持っていたフランシーは、思い切りディオールみたいな服を着ていたのだが・・・
まあいい、映画『バービー』ともフェミニズムとも何の関係もない話に脱線してしまった。フランシーは、バービーに比べてセクシー度が落ちるというだけで、フェミニズム的には特にステレオタイプ・バービーと隔たるものはないので、登場させる意味もなかったのだろう。あるいは、多様性バービーたちが活躍する現在、とうに消えてしまったキャラクターだからなのかもしれない。
最後に、若いフランス人たちの意見の一例として私の子どもたちの感想を記しておこう。Z世代の彼らは10代の時からフェミニストを自称しているが、二人とも『バービー』は面白くなかったと言う。問題はバービーランドに女性が君臨していることのようだ。
息子が言うには、「バービーランド」では男女のステイタスが現実世界の反対で、バービーに見られることでしか存在を確認できないケンの方が、現実世界における女性のような立場にある。そのケンが外の世界に行って、自分にも別のあり方ができることに目覚めるのは、父権主義の強い国の女性がフェミニズムの強い国に行って目覚めるのと同じ。自国に帰ってきてフェミニズムを広めようとするも権力に押しつぶされて反乱は失敗する、という筋立てだと考えるなら、なんとも反動的な映画ではないか、と言う。「フェミニズムって、男が威張る代わりに女が威張っていればいいってもんじゃないだろう」と娘もプンプン怒っている。あれは人形遊びの、女の子の夢の世界だからあのようになるのであって、フェミニズムの理想郷を描いたものではない、夢の世界が現実に出会ってヒビが入り、ステレオタイプ・バービーには居場所がなくなる物語だと私は思うのだけれども、女の子の夢の世界と現実とを、隔絶したものと捉える私の感覚と、子どもたちの感覚はどこか違うのかではないかと思った。彼らには、馬鹿げているにしても理想として考えられるほどには、女性独裁世界がリアリティを持って感じられているということだから。
私自身はミュージカル仕立てであったり、パロディであったり、様式化された演出が面白くて楽しめる映画だったし、コミカルながらフェミニズムを扱った映画が世界的にメガヒットすること自体に現代を感じた。例えば女性がセクシーなボンド・ガールとしてしか登場を許されなかった昔の007シリーズなどと比べて隔世の感がするのだが、一方でいつかきっと、この映画もかなり古くさく感じられるようになるのではないか、そしてそれはそれほど遠くない将来かもしれないとふと思った。