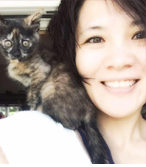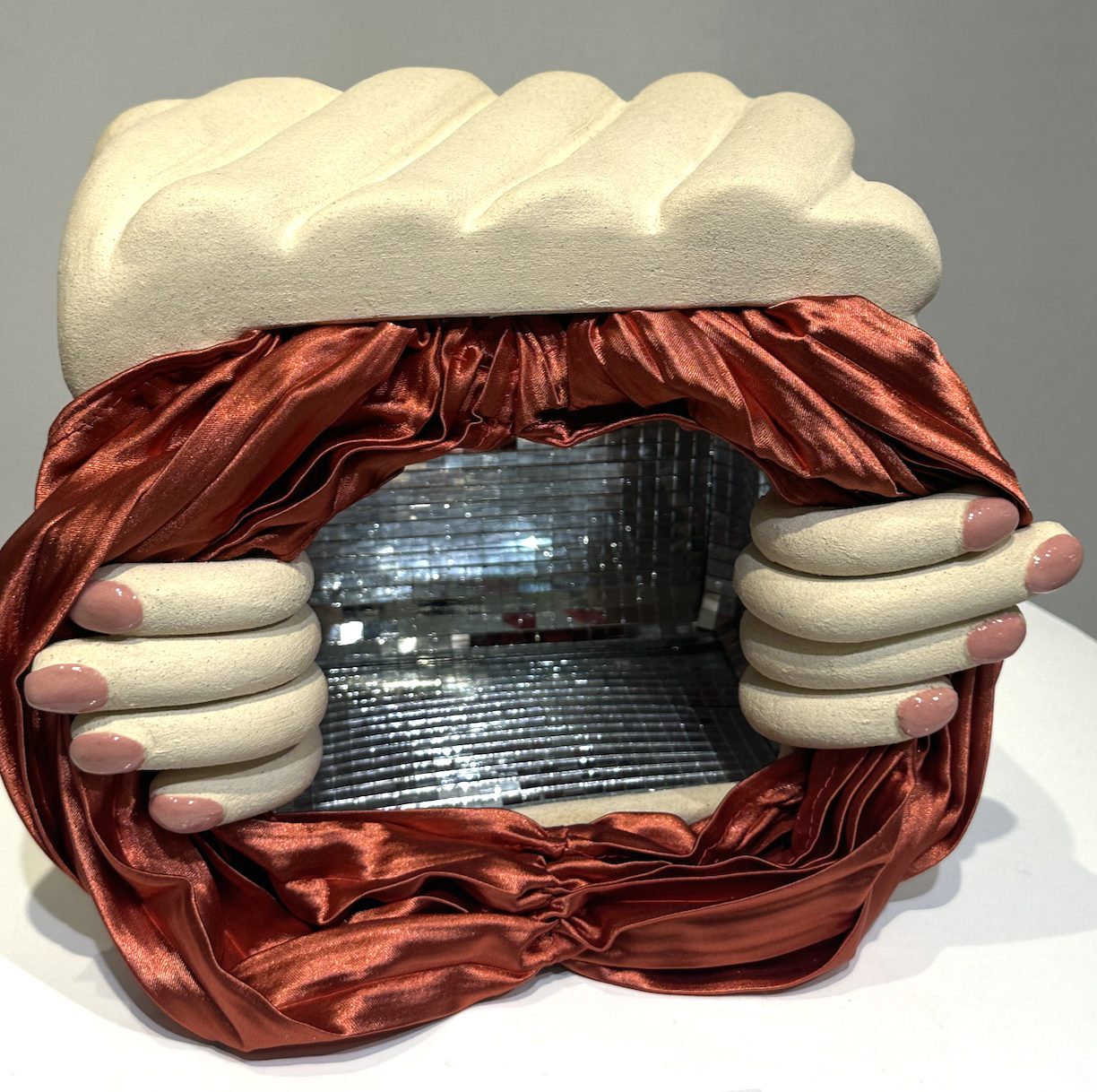このテキストは、今年4月に急逝された川田文子さんのお別れ会で読んだものです。
奇しくも遺作になってしまった『女たちが語る歴史 上下巻』(「戦争と性」編集室)の書評をお別れ会で読むという役をいただきました。
当初のこの本は分厚い一冊になる予定だったそうです。それを川田さんが「そんなことしたら、(本が重くて)寝ころがって読めないじゃない!」と猛反対し、出版社は(多分、仕方なく)上下巻に分けることにしたそうです。というエピソードは知らないまま、いつも本を読む時はそうするようにソファーでごろごろと寝転がりながら読んでいたのですが、途中で、寝ている場合じゃないと前屈みになるような姿勢で夢中になりました。
川田さんは、フェミニズムには距離をもっていた人でした。川田さんにはどこかクールなイメージがあるのですが、それはフェミニストを自称する私に対する距離感だったと思います。日本のアカデミアフェミニズムへの不信もあったように思いますし(私もあるのに!)、実際にフェミニズムの運動に不快な思いをされたのかもしれません。川田さんのご自宅に行ったり、様々な運動の場で親しく話すような関係になっても、どこか「深まらない」距離を私は感じていました。
ですから先日、『女たちが語る歴史』の編集者である「戦争と性」編集室の谷口和憲さんからこんな話を伺って、ああもっと話かけるべきだったのにと後悔しています。
谷口さんは、「フェミニズムに距離がある」という川田さんに、私が編者となった『日本のフェミニズム』(河出書房新社)を送って下さったそうなんです。その後、川田さんは「この本は私にとって画期的なものになると思う」と仰ったそうです。それ・・・私に早く言って!!!と心から叫んでしまいましたよ、谷口さん!
地獄とは一線を引いた、きれいないフェミニズム・・・ではなく、女のリアルとと尊厳をただひたすら求めるために歩き、書き続けた川田文子さん。川田さんと私はもっと話すべきだったのだと思います。
以下、お別れ会当日に読んだ原稿をそのまま掲載します。

「女たちが語る歴史」は、1979年出版『つい昨日の女たち』、1982年出版『女たちの子守唄』、1983年出版『琉球弧の女たち』の三冊がまとめられたものです。ここには30代の川田さんが、文字通り全国を歩き、自分よりずっと年上の女性たちに出会い、彼女たちの声を聴き続けた記録が残されています。多くが明治生まれの”老女”たち。大変な時代を必死に生き抜いてきた女性1人1人の人生の記憶を、壮大な女の歴史として紡いでいった川田さんの若い情熱と、真剣な思いが貫かれています。
川田さんが女たちに出会う旅をはじめたのは70年代後半から80年代にかけて、高度成長期の最中、日本の歴史上、かつてないほどに女が専業主婦であることを求められた時代でした。男は24時間外で働き、女が公的空間から排除されていく時代。全てにおいて「合理化」が求められていく社会のスピードに、川田さんは強烈な違和感と抵抗を感じたのでしょう。『女たちの子守歌』のあとがきで、川田さんはこのように記しています。
「多くの女たちが子を産み、育て、生活を引き受け始めるのに、私は20代半ばから後半にかけて、例えば団地の静かな路上を腹をせり出してゆっくりと歩く妊婦や、また、団地の広場とか公園等で女たちの群れが子供たちを遊ばせているけだるい風景を白々とした想いで見ていたのは、いわゆる“生活”の中に自分の身を滑り込ますことを恐れていたからかもしれない。いや、子を産むため、あるいは子を育てるために労働から離れ、けだるそうに時を過ごす女たちの像は、私の思い描く“生活”からは遠かった」
女たちが集う昼真の公園を「けだるい風景」として切り取り警戒する感性を持つ川田さんには、そこにいる女たちを白々した想いで見る一方、「こんなはずじゃない、女はこんなはずじゃない」という確信にも近い、女たちへの深い信頼が底に貫かれています。1943年生まれの川田さんが受けた戦後民主主義教育は、戦前の封建的なもの、古いものをあっさりと全否定しましたが、否定することでなかったことにされかねない、その時代を生きた女たちの言葉を、文字通り、川田さんは取り戻すために彼女たちに出会っていきます。そしてここには聞かれることのなかった女たちの人生が、30代とは思えない重厚な筆圧で、質感をもって蘇るのです。
戦前、沖縄からパラオに移住し、戦火が激しくなるなかパラオから故郷の慶良間諸島座間味島に戻るまで2年半ものあいだを難民として暮らし、幼い子を失い、戦後はたった1人で子を3人育てあげた女性の話は、こんな風に始まります。
「話し相手でもいればいいが、自分1人で思い詰まってですね。あと泣く。泣くんですよ」小さな家のとこのなかで寝付かれない夜、これまでたどってきた半生が走馬燈のように頭の中に去来し、自らの半生に押しつぶされて泣く、と老女はいった。身体もガッシリし、どちらかといえばいかめしい表情のこの老女を襲うひそかな慟哭、私はその悲しみの深さを受けとめられない」
語られる話は、あまりにも惨いものばかりです。残酷な時代に振り回され、過酷な労働に追われ、切迫した生活者としての女たちの人生です。それは例えば、幼い身で無償の労働力として嫁ぎ、休む間もなく孕み、「死んでければいい」と念じながら子を産み、何人をも育てる人生。出稼ぎから戻る夫に梅毒をうつされ、11人の子供のうち7人が死んで生まれ、自分自身も梅毒のため口がきけなくなって死んでしまった女の話。息子たちを兵隊に取られ、身が壊れるほどの激しい労働を生き抜いた貧しい女たちの物語。
1人1人のその声が、次第に大きな大きな1枚の画のように迫ってきます。そこで描かれているのは一流の国の顔をして他の国を侵略し、女たちの性を踏みにじり、「国史」を紡いでいった男たちが決して描かなかった「女たちが語る歴史」です。川田さんの自宅に遺された大量のテープを見たことがありますが、川田さんの聞き取りは、女性たちが過去を旅し、その時の情景、心象風景を語り出すまでに長時間をかけます。そしてその聞き取りは、その女性がどのような息づかいで川田さんの前に座っているのかが目に浮かぶような迫力で文字化されていきます。物語は細部に渡るまで色彩鮮やかで、まるで映像のように女性たちの話が川田さんの脳裏に浮かんでいるのがわかるのです。
子育てに追われる農家の女たちの話では、このようなことが丁寧に記されます。農作業の間、まだ1人にはしておけない赤ん坊をどのように置いておけるのかの具体的な話です。
「女たちは激しい労働の中で子供を育てるための実に多様な知恵を出し合っていた。なおさんの村ではえじこの底に灰を入れて次に藁のクタダを一式、その上におしめを1枚ぐらいあてて赤ん坊のお尻をピタッとつけて入れておく。赤ん坊の着物は腰から下の部分はまくりあげてボロを敷いて濡れないようにした。おしめは麻でつくったから、水分は下の方にとおる。また、しっちきという葦草を扇形に編んだものをえじこに入れることもあった。扇形の要の部分だけを編んでおり、サクサクとしているところに座らせておけば、水分は下の灰が吸い取る仕組みである。このしっちきを二つ、三つ交替に使えば、一年ぐらいはもった。しっちきは水ですすぐだけで汚れが落ちた」
畑仕事につく女たちが、おむつを変えることもできず、産まれたばかりの赤ん坊を安全に1人でほっておけるようにできる工夫の一つ一つ、その細部を、川田さんは見逃さず、生き生きと記述します。まるでその場にいて、母親を求めて火のついたように泣く赤ん坊の声を聞きながら、農作業に向かう女たちの背中が見えるように描くのです。女たちが何に振り回され、何に泣き、何に痛み、何に笑い、何に苦しんだのか・・・必死に生き年を重ねた女たちに向き合いながら、彼女たちがどのように赤子のおつむを変えていたのか、または変えられなかったのか、そんなことまでも聞き出す、そんなインタビューがどのように可能だったのか、読者として、そして同じ物書きとしても、ただただその細部の鮮やかに圧倒されるのです。
ここにいる、誰もが実感することですが、日本軍「慰安婦」運動で川田さんが果たした役割はあまりに大きいものでした。それは、1977年にペポンギさんと出会ったこと、そしてのこの旅、本書で出会った数多くの女性たちの人生を、彼女たちの暮らす家で聞いてきたその経験があってからのことだったと実感します。92年、日本に暮らしていた宋神道さんの被害を、真っ先に聞きに行ったのは、川田さんでした。性被害を聴くことを、多くの人は躊躇するものです。聞いてはいけないものと、目をふせてしまうものです。それでも、その躊躇は、被害者に、沈黙と諦めを強いるものでもあります。そのことを、川田さんは女たちの語りの中で知っていったのでしょう。川田さんは、女性たちとの語りの中で、きっと確信したのだと思います。女たちは聴かれることを、待っているのだと。そして私たち女には、語るべきことが無数にあるのだと。
1970年代、国鉄がはじめたディスカバ−ジャパン。日本の隅々にまで若い女たちがかつてない勢いで1人旅を始めた時代でした。ビニール袋に入れられ捨てられたコインロッカーベイビーが社会問題にもなっていました。そういう時代のなか、川田さんが、10代の頃から孕み産み続け、そして地に這うように働き続けた老女たちの人生に向き合うために電車に乗ってきました。女性たちに会いに電車に乗る川田さんの、静かな胸の高鳴りが本書から響きます。
あまりにも濃厚な本でした。聞かれなければ、女たちは語らないでしょう。そして、語られないことは忘れられていくでしょう。女ならば当たり前のこととされてきた、たくさんのこと。女だから仕方ないとされてきたたくさんのこと。女たちが、命をかけて子を産むその瞬間の思い。子供たちが寝静まった後に焚火のわずかな灯りのもと、指の感覚を頼りにカラムシを積む時間。刺すように冷たい春の海に潜る臨月を迎えた海女の意地。17歳ではじめて客を取った辻の女の、その晩の恐怖。雑居ビルの火事で逃げ場を失い、重なるようにして亡くなったホステスたちのこと。そのホステスの殆どがシングルマザーであったこと。
川田さんは2000年に『女という文字、おんなということば』という本を出されています。そこにこんな一文があります。
「女という文字に、気の遠くなるような長い年月、女たちに受け継がれてきた悲しみ、怒り、誇り、気概、喜びが塗り込められている」
女であること、女にされること、女として生かされることに徹底的にこだわり、そして女だからこそ受けた痛みを、女として共に引き受けようと生き、書いてこられました。無数の女たちの強い横顔を誇らしく見つめ書き続けてこられました。本来私たちにある誇りと尊厳を信じ、取り戻すために、川田さんは記録し続けたのだと思います。
『女たちが語る歴史』、歴史の証人となり続けた川田さんが留めた女たちの歴史。そこに貫かれるのは、女の尊厳です。
川田さん、この本を遺してくださり、ありがとうございました。
(2023年6月18日日本キリスト教柏木教会にて)
【川田文子(かわだ・ふみこ)】
1943年生まれ
ノンフィクション作家
代表作「赤瓦の家〜朝鮮から来た従軍慰安婦」(1987年)日本軍「慰安婦」として沖縄に連れられ、戦後、放り出され、ただ独り沖縄で生き続けた裴奉奇(ペポンギ)さんの半生をまとめた。宋神道さんの裁判支援に関わり、日本軍「慰安婦」問題運動に深く関わる。「希望のたね基金」理事。2023年4月2日死去。