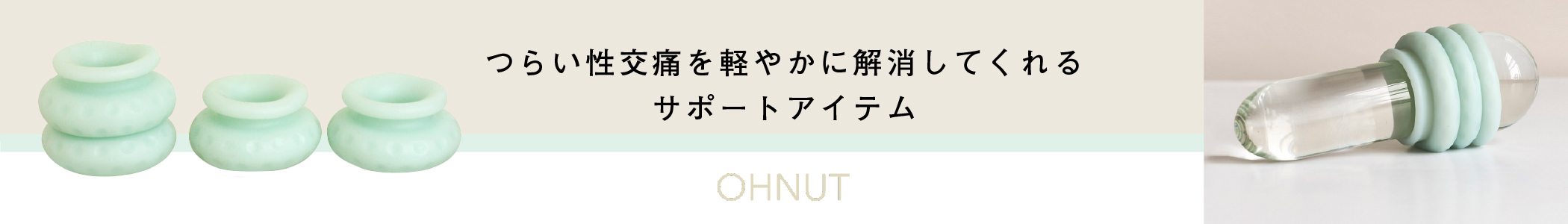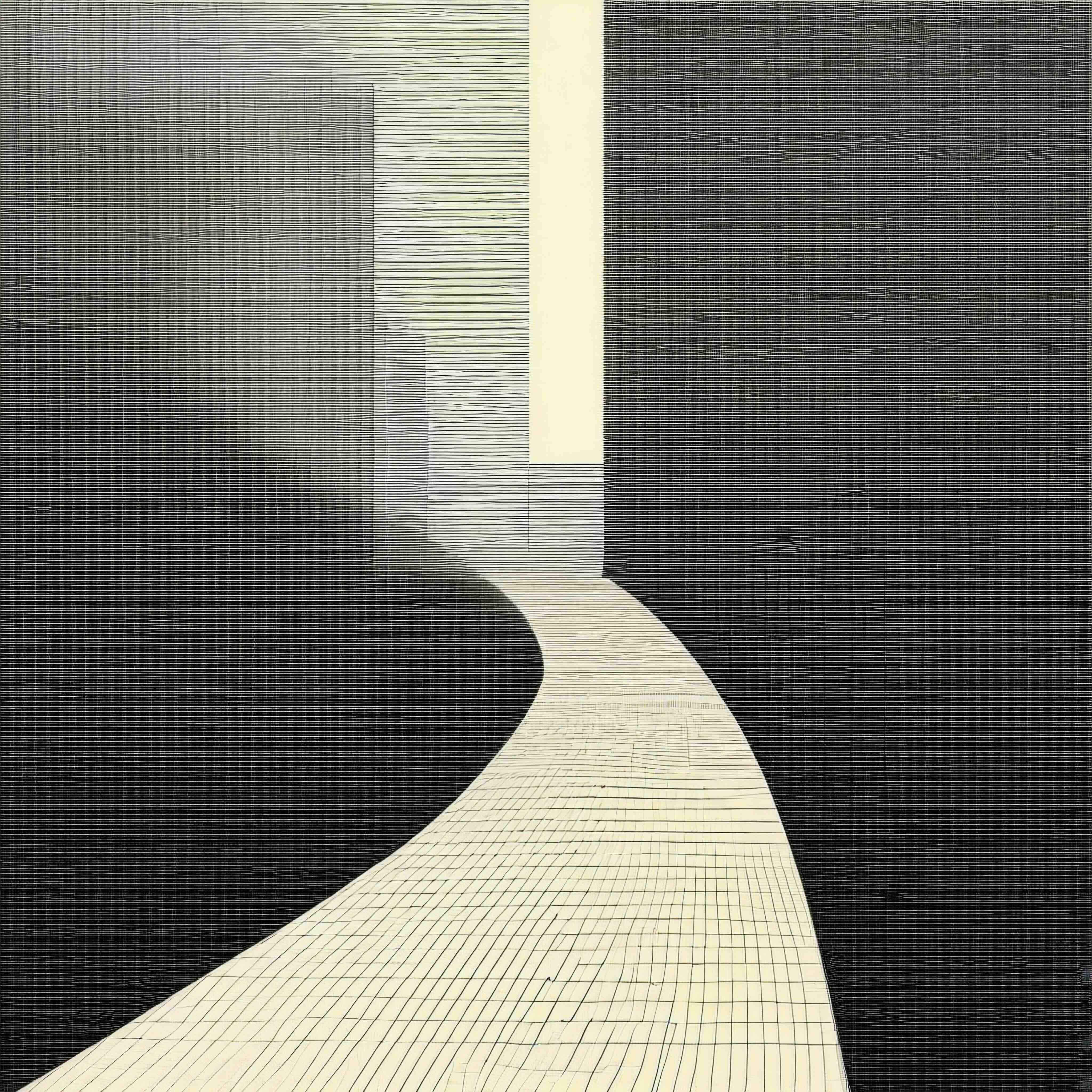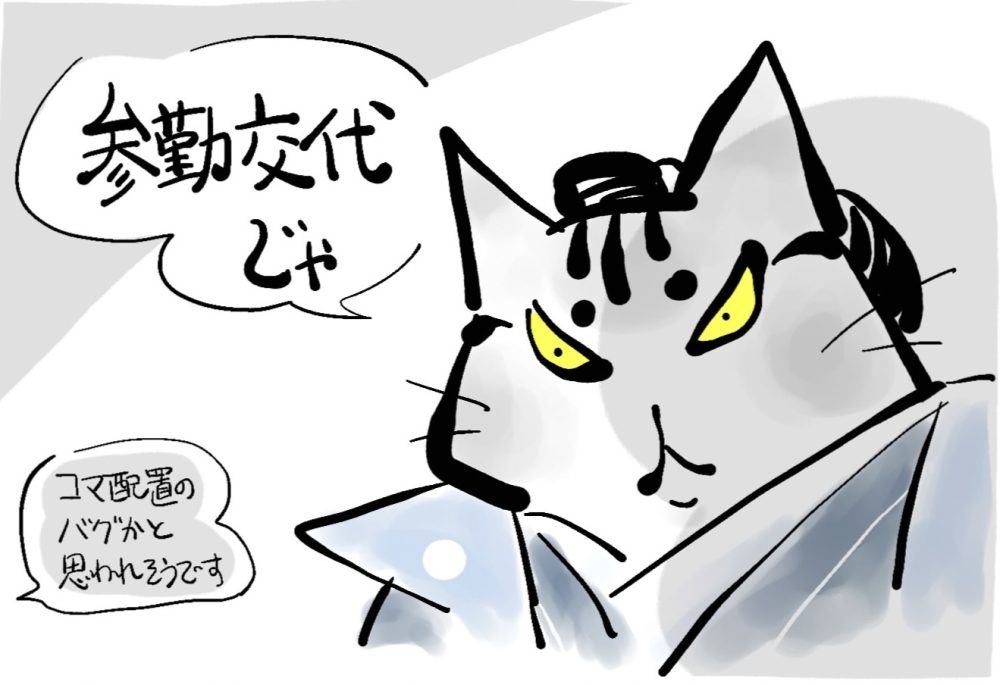ワールドカップの騒ぎの陰で、集団的自衛権を容認して「戦争のできる国」に向かっているこの国。そのうえ、集団安全保障もなんて、話はエスカレートするばかりで、「何だかよくわからない」と感じている人も多いのでは?そういうふうに戸惑っているうちに進めようという作戦なのだとしたら許し難いです。
この件に限らず、政治って、ホントは生活に身近なことのはずなのに、「何だかよくわからない」遠いことに見えがちじゃないですか?そのひとつの理由は、やってる人たちが縁遠く見えるからではないでしょうか?政治のニュースが流れて国会や閣議の様子が映るたびに、そこにいるのはいつも中高年の男性(オヤジとジジイです、はっきり言って)。東京都議会でのセクハラ発言にも、発言当事者もそれを笑ってみていたという周囲の議員たちもほとんど男という背景があります。政治家は「女には向かない職業」だとでもいうのでしょうか、いやいや、そんなわけはない。
シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、女性解放を論じた現代の古典として名高い『第二の性』(1949)で「人は女に生まれない、女になるのだ」と言明し、いかにして女が「作られて」いくかを論じました。女性はリーダーシップに欠ける、権力志向が無い、だから政治家には向かない・管理職には向かない、などともっともらしく言われたりしますが、それは、幼い時から、女の子は優しく素直にと、従順でつねに他者を自分より優先するようにしつけられ内面化していくから。このことが、女性が政治家になりにくい要因の一つを作っているのは明らかでしょう。
1960年代後半から70年代にかけて花開いた女性解放運動(第二波フェミニズム運動)の女性たちは、ボーヴォワールのこの考えを、「ジェンダー」という概念で表現しました。生まれつきの性別(セックス)が女・男の「らしさ」を決めるのでなく、生れ落ちてからの社会環境と文化の中で人は、らしさを刷り込まれていく。「母性本能」ということばに典型的なように、妊娠や出産をする身体をもっていれば誰もが母になりたがり子育てが自然にできるかのような思い込みが、いかに女性を縛ってきたことか。そのウソをあばいたのがジェンダーの語でした。
この意味でのジェンダーは、今では日本でも一般に知られるようになりました。ジェンダーにとらわれない生き方ができる社会を作り上げていくことは、現在進行形の重要な課題であるのは言うまでもありません。
しかし、1990年代以降のポストモダンフェミニズム理論は、ジェンダーにはもっと深い意味があると大胆に発想しました。すなわち、社会的性差は作られたものであるというのはその通りだとしても、その考え方の背後には、男女の生物学的性差は「自然」なものとして存在しているという暗黙の前提があるのではないか。そこで自明とされている「自然」な性差、「セックス」とはいったい何なのか、という問いを投げかけたのです。
ジュディス・バトラーは「セックスは、つねにすでにジェンダーである」と言います(バトラー、1999、29頁)。肉体的・所与のものと見える性差すら、時代によってさまざまな「科学」的知識の名の下に、二分法的に男/女の記号を付されてきたものである、セックスそのものがジェンダー化されたカテゴリーであると。
これを聞くと、おそらく多くの人がそれはおかしい、と思うでしょう。女と男では体つきが明らかに違う、おっぱいや膣は女性にしかないし、ペニスがあるのは男性。ホルモン分泌も、DNAも異なる。それは、どんな文化・時代でも変わりがないはず、それなのに、セックスがジェンダーだなんて非合理もいいところだ、と。
でも、バトラーは、そういった身体的な差異が無い、と言っているのではないのです。人には、身体的差異はいろいろある。肌や眼の色、人種、性的指向、老若の違い、もって生まれた気質や性格、体格もさまざまです。それなのに私たちは、男/女の身体的差異がほとんどまったく意味を持たない状況や場合ですら、人を認識するのにまず、男/女という区切りを考えてしまう。そうした認識のあり方が、セックスすらジェンダーであるということの意味なのです。
実は、このように男/女を絶対的な区分として考える考え方は、近代以降もたらされたものです。なぜかといえば、近代以降、「人はみな平等」となったから。身分差が絶対のものだった前近代社会では、人の違いは、まず、身分。身分内での男女の差はそのあとから。身分が低い者、低階層の者は男でも教育機会も自由もないが、身分が高ければ、女性は教育も財産も持てる。それが、近代以降、平等の概念が登場したからこそ、女/男の区分が強調されるようになったのです。帝国主義・植民地主義の時代には、「人種」が人を分ける「自然」なカテゴリーであるとする思考が、黒人を人間以下の扱いをする奴隷制を正当化したように、男女を異なるものとしてまず発想する思考は、近代以降の女性差別を正当化してきたのです。
このように考えると、「男女平等」という概念にも、違う意味がみえてきます。フェミニズムは、発祥以来、男女間の格差を解消し「男女平等」を実現することをめざしてたたかってきたわけですが、「男」と「女」の平等をめざす、というのは、そもそも、「男」「女」という別々のカテゴリーが存在するという前提に立ってしまっているのではないか。そのこと自体が、人間をまず性の区分で認識するという、近代以降つくられ女性差別を正当化してきた考え方そのものなのに。江原由美子が、「『男』『女』という『ジェンダー化された主体』が最初にあって、その両者の間で支配-被支配の関係がうまれるのでなく、『男』『女』としてジェンダー化されること自体が、権力を内包している」と論じている通り(『ジェンダー秩序』勁草書房 2001、25頁)、「男」「女」とあたかも人間が二種類であるかのように考えること自体が、抑圧を作ってきたのです。そもそも、「男」「女」は対称でもなんでもないし、「女」と、ひとくくりでくくれるような「女」はどこにも存在しないというのに。
こうしてみると、あたかも、男女を対等にするというフェミニズムの原点自体が、間違っていたということになりはしないか、それではアンチフェミニストの思うつぼなのでは、と心配にもなるかもしれません。
でもだいじょうぶ、そうではないのです。
フェミニストたちは(自分がフェミニストだとは考えない女性も)、現実に存在するさまざまな女性差別に怒り抗議をするとき、いつも、「では男女の性差がなくなればいいのか」「男女がどのような扱いを受ければ平等なのか」と問い返され、答えられるはずのない「差異か平等か」の二者択一を迫られてきました。そして、女性たちの中での対立をも生んできました。まさにこれこそ、「罠」だったのではないでしょうか。この罠を見抜き、「男」「女」のジェンダーカテゴリーをひらいていくこと(脱構築)で、私たちは新たな未来を構想できる---これがポストモダンフェミニストの提言なのです。
女たちはさまざま。「女」とひとくくりされるわけにはいかない。しかし他方、現実に私たちは、「女」としてくくられて明白にも暗黙にもいろんな不利益を受けている。だから私たちは、女性差別に反対しながらも、めざすべきなのは、すべての女たち、さまざまな女たちの自由と尊厳、そして権利。それは、決して画一的なものではないし、ましてや「男」と一緒でいいなんて、そんな薄っぺらなものじゃない!
こんなふうに現代のフェミニズム理論は、ジェンダーをめぐる新たな地平に私たちを招待しています。なんだか刺激的じゃないですか?
本の紹介
 ジュディス・バトラー(19990=1999)『ジェンダートラブル---フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(竹村和子訳)岩波書店1999年
ジュディス・バトラー(19990=1999)『ジェンダートラブル---フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(竹村和子訳)岩波書店1999年
解剖学上の男女差、ホルモン・染色体の性差など、「セックス」の自然な事実のように見えているものは、じつはそれとは別の政治的・社会的な利害に寄与するために、さまざまな科学的言説によって作り上げられたものにすぎないと看破した刺激的な書。ジェンダーは決して与えられた属性としてあるのではなく、自分たちが能動的に選択して構築する行為である(パフォーマティビティ performativity)というのも、私たちの目を開かせてくれたところです。
バトラーは何度か来日しており、私もお目にかかったことがありますが、その折、かつて彼女が女性の恋人をはじめて母親に紹介したとき、相手が同性であることを咎めるどころか、「で、その人はユダヤ人なのかい」と母親が尋ねたというエピソードを話してくれました。激烈なユダヤ人差別の時代を生きた母親にとっては、性別の区分よりもユダヤ人であるかどうかの区分のほうが重要だったのですね。