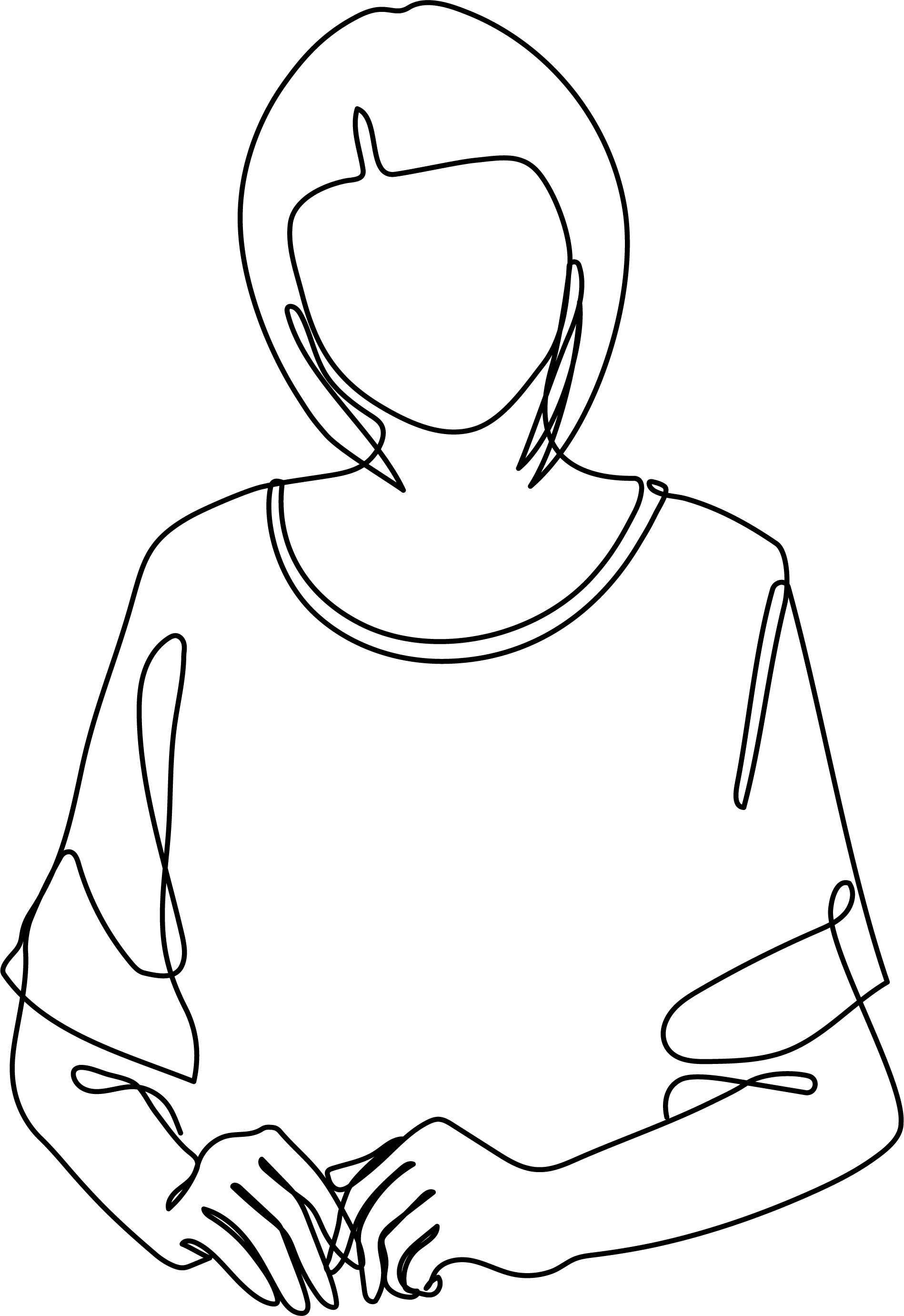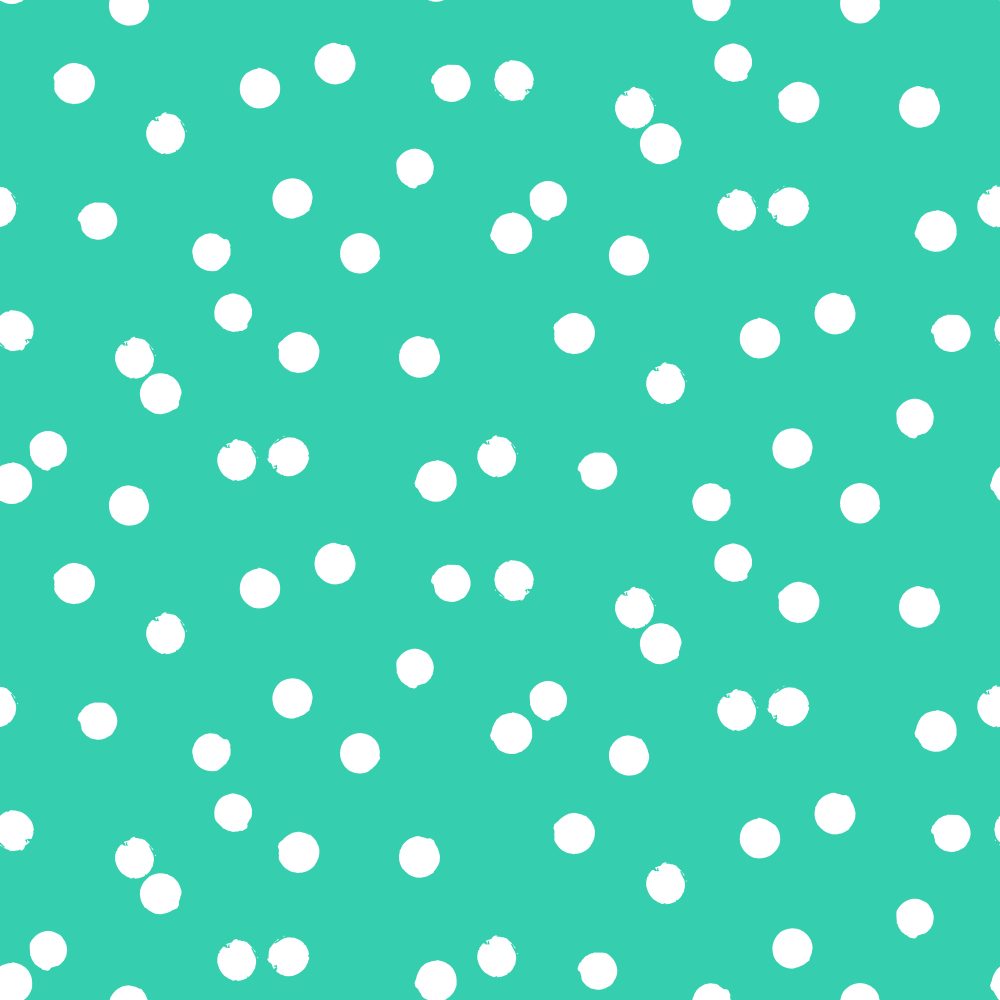私は大学生だった20代の初めに人工妊娠中絶と稽留(けいりゅう)流産を経験した。それが心の傷になり、20代から30代にかけてずっと苦しんできた。30代の終わりに娘を授かった時、この子には自分と同じような思いをさせたくない、日本の中絶医療は変わるべきだと考えた。特にカウンセリングや心のケアがないことが一番の問題だと思っていた。
娘が2歳になった時、中絶問題を研究するために大学院に入ることを決めた。当初は母性研究の第一人者の先生のところに通う予定だったけど、家族の転勤で地方都市に引っ越すことになった。その都市の大学を調べたら、「中絶」にまつわる授業をしていたのは男性の法哲学の教授だけだった。その先生に相談をしに行き、すすめられるままに、当時、すでに出版していた数冊の翻訳書などを「業績」として提出することで、大学から「修士相当」の認定をもらった。「英語ができるあなたの場合は、社会人入学ではなく、一般入学で受験したほうが有利だ」と言われ、英文和訳だけだった大学院の後期課程を受験し、無事に合格した。
修士課程を通らなかったことで、ちょっと恥ずかしい思いをすることにもなった。法学部の福祉・労働系の先生方が合同で開いていたゼミで初めての発表を行った時、私の発表が終わったら、参加者全員が一瞬しーんと黙り込んでしまった。沈黙を破ったのは最も若い(つまり私よりも若い)教員で、「こんなゼミ発表は初めてだ」と言われ、「ゼミ発表のお作法」を全く知らない自分にはっとした。ようするに私は、「もろ主観的な経験談」を話してしまったのだ。いま、思い出しても頬が熱くなる。
ゼミ発表にもようやく慣れた大学院2年目に、日本ではいまも「そうは法」と呼ばれる19世紀に開発された古い中絶手術が使われていることを知って私はショックを受けた。海外の文献では、1970年代にD&C(頸管(けいかん)拡張そうは法)から吸引中絶に置き換わったと常に書いてあるのに、世界では危険だとされている「そうは法」が21世紀に入っても日本では使われていた。しかも、国内では中絶の技術に関する研究はほぼ皆無。この問題を先に解明しなければならないと、私はフェミニズムの視点で中絶について医療、法律、倫理の観点から切り込む学際研究に乗り出した。
せっかく後期から入った大学院だったのに、休学を挟みつつ最大在籍年数の6年間をかけて博士論文を書き上げたのは2009年の春だった。その後、子連れ単身赴任などの紆余曲折を経て、2014年に博論を直した『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ フェミニスト倫理の視点から』を勁草書房から出版して、中絶問題研究者と名乗るようになった。以後、チャンスがあるたびにリプロダクティブ・ヘルス&ライツと中絶問題について、社会的に発言するようになった。
2013年2月、長年、女性や少数者の権利を実現するためにアドボカシー活動を展開しているすぺーすアライズの麻鳥澄江さんと鈴木ふみさんに誘われて、タイのバンコックで開かれた第2回IWACという安全でない中絶に関する国際学会に参加した。それが思わぬ転機になった。この時の会議のテーマは「安全な中絶」で、経口中絶薬の話題でもちきりだった。
国連は2003年に『安全な中絶』というガイドラインを発行しており、そのガイドラインの第2版が、この国際会議の前年2012年に出ていた。それらのガイドラインでは、外科的に行う中絶と並んで、ミフェプリストンとミソプロストールという2種類の薬を順次服用する「薬による中絶」で人工的に流産を引き起こす方法が推奨されていた。麻鳥さんと鈴木さんがボランティアで訳したこれらWHOのガイドラインでは、古い「そうは法」は否定され「中絶薬」と「吸引」が安全な方法として推奨されていた。
2013年のバンコックでの会議で、私は海外の著名なアクティビストたちと知り合った。Women on Webのレベッカ・ゴンパーツもその一人で、彼女の紹介でオランダのアムステルダムを訪れ、Women on Webの事務所や病院の産婦人科、若いカップルの避妊や中絶のために情報やサービスを提供するユースセンター、中絶カウンセリングを提供している相談所などを訪問した。
この時、産婦人科医である早乙女智子さんと対馬ルリ子さんにもお声をかけてご一緒した。対馬さんはこの旅で手動吸引器の有用性を知り、ほどなく自院で採用したと伺っている。早乙女さんには2016年の第3回IWACへの参加を強く勧め、彼女はこの国際会議に参加した初めての日本人産婦人科医になった。早乙女さんも衝撃を受けて帰ってきたが、私は「中絶カウンセリング」を行えるようになるために、別の大学院に入りなおして臨床心理士の資格を取ろうとしていたので、社会的な活動を行う余裕はなかった。
2019年2月の第4回IWACに、早乙女さんと一緒に参加したことで、再び転機が訪れた。驚いたことに、この年の会議では「中絶薬の安全性」はもはや揺るぎのない事実になっていた。経口中絶薬は安全で有用であるという確立した事実を前提に、この優れた薬をどう広めていくのかと、教育や制度や法律を改善するための方策に関するセッションが数多く開かれていた。この会議で初めて、私は日本の中絶状況について口頭発表をした。
「日本ではまだそうは法が妊娠初期の中絶の多くで使われている」と言った時に、会場の人たちが目を丸くしてこちらをまじまじと見つめてきたことが忘れられない。壇上から降りると、大勢が私の周りに集まってきて、「日本の医者はどうして中絶薬を使わないのか」「手動吸引も導入してないのか」「日本はハイテク国家ではないのか」「日本の女性たちはなぜ黙っているのか」等々と、質問攻めにあった。
「ぼくが教えに行ってあげようか」と、2013年の時にすでに知り合いになっていた気のいいマレーシア人の医師から言われたことも忘れられない。「日本国内で先生が中絶してみせるわけにはいかないでしょう?」と言ったら、「パパイアさえあればいい」と言う。ちょうど子宮と同じくらいの大きさ、柔らかさのパパイアを使って吸引の練習をするというのが世界の常識であることを、その時初めて知った。
その会議に参加してきて、早乙女さんと私は、日本の「中絶」も変わらなければならないという強い思いを新たにした。3月に報告会を行った時には、狭い会場に数十人が押し寄せ、世界の中絶医療の現状と、そこから日本があまりにも立ち遅れていることを早乙女さんと私が報告すると、出席者は衝撃を受けていた。それ以降、北原みのりさんのLOVE PIECE CLUBの1室を借りて何度か定期的に勉強会を重ねていくうちに、何かをしなければという思いが強まっていった。
9月28日が国際セーフ・アボーション・デーだと知り、その2週間ほど前に、私たち3人は京都で集会を行うことを決めて、強行した。閉会後、スウェーデンに留学していた福田和子さんから「観ましたよ」とメッセージが送られてきたのに、私は面食らった。その時初めて、Facebookに動画機能があることを知った。北原さんがオンラインで中継していたのだ。
私たち3人は、翌年の国際セーフ・アボーション・デーはもっと大規模なイベントを行いたいと考え、知り合いの学者や1980年代から中絶問題にコミットしているSOSHIRENの大橋由香子さんに声をかけ、2020年の9月に備えることにした。そのさなかに、コロナ禍が訪れた。
コロナ禍があったからこそ、私たちの活動は大きくなれたのだと思う。9月28日に予定していたイベントはオンラインで行うことに決め、様々な立場から中絶を語る企画を練っていった結果、全部で13のパートをもち数十名の女性たちが関わる6時間の一大イベントになった。その動画の再生回数は今や7000回を超えている。
日本国内で、これほど熱気に満ちた「中絶」に関する長時間のイベントが行われたのは初めてだったのではないだろうか。
https://youtu.be/6m5SDcoYPbg
このイベントにスタッフとして関わった人たちから、「もっと続けたい」、「何かやりたい」や、後付けで動画を観て、「エンパワーされた」と仲間に入ってきた人たちもいる。海外在住の日本人や外国人アクティビストとつながれたのも、オンラインならではだと思う。
国際セーフ・アボーション・デーJapanプロジェクトと名乗って、私たちが活動を始めてから約半年後の2021年の4月、英国ラインファーマ社が日本で初めて経口中絶薬の承認申請を行うとメディアが報じた。このことで私たちの活動は注目を浴びるようになり、12月に承認申請が行われると、私のところにも中絶問題研究者として取材や執筆の依頼が舞い込むようになった。2022年、前記のプロジェクトは「#もっと安全な中絶をアクション(ASAJ)」と名前を変えて院内集会や要望書提出などの活動にも力を入れるようになった。私はASAJの活動に加えて、情報提供用に作ったホームページRHRリテラシー研究所を個人的な活動の母体とし、クラブハウスやツイッタースペースで数えきれないほど中絶問題について語り、ボランティアを募って2022年には毎月1~3回もの学習会を開催した。
そして再び12月23日が巡ってきた。ラインファーマ社が承認申請を行ってちょうど1年目である。私が中絶と流産を経験してから今年で40年、来年は私が中絶問題を本格的に研究し始めてから20年になる。この間に日本で行われている「そうは」が古い中絶方法である事実は、かなり知られるようになった。次は中絶薬がいかに安全で確実な薬であるのか、中絶ケアは望まない妊娠に直面した人々にとって不可欠であり、安全な中絶ケアを提供されるのは人権であるということを広めていきたい。年明けには念願の『中絶薬がわかる本』もアジュマブックスから電子書籍として刊行予定。来年も、中絶をめぐる不公正を正していきたい。


写真:©Kumi Tsukahara
オランダの病院で売っているバルーン(入院している人、出産した