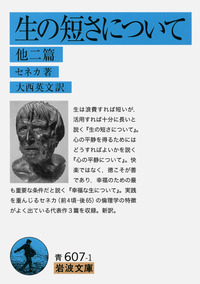年末、大きく体調を崩した。最初は昼ごろにフラっとするような感じがあり、すぐに座っていられないほどに熱が上がり、解熱剤を飲んでも一向によくならなかったので、その日の夜に都の発熱相談に電話をした。女性オペレーターは、具合の詳細やワクチン接種歴などを私に尋ねてから、住所(番地の前まで)を言うようにと言った。それから、いくつか病院の電話番号を教えてくれたが、自分で電話をして予約をしなければならないのだという。それに、紹介されたのはどこも徒歩では20分ほどかかる病院ばかりだ。公共交通機関を使ってはいけませんと強調され、「こんなに苦しくて、どうやって行けばいいんですか」と問うと、「ご家族の運転する車で送ってもらってください」という答えで、すぐに電話を切った(結局、翌日に解熱剤をたくさん飲んで、自転車で発熱外来へと行った。コロナではありませんでした)。
そもそも、息も絶え絶えで電話して、長々と事情を説明した上で、ウェブ上でわかるような病院の電話番号しか教えてもらえないって、どうなっているんだ。それに、どうしてこうも家族(おそらく電話のニュアンスからして、配偶者)がいることが前提なのか。病気による体力の消耗よりも体に堪えた。
まもなく確定申告も始まるけれど、去年の卵子凍結に関する費用を、未婚である私は医療費控除として届け出することができない。今年の4月から不妊治療の保険適用が始まるが、対象になるのは夫婦、あるいは事実婚のカップルだと報道されており、シングル女性や同性カップルははなから想定されていない。(女性が)一人でいると、一人の人間として認めらない……。そうした思いは、別の複数の出来事からも強まることになった。
出来事その1。
しばらく前から友人(女性)が自分で家を購入しようと物件も決め、購入したら私に一室を貸してくれると話していた。楽しみにしていたが、新卒からずっとしっかりした会社で働いている彼女でさえもローンが下りず(なぜ?)、今度は、彼女が見つけてきた山手線沿線の古い一軒家を彼女の名義で借り、そこに私も同居することになった。家は3階建てで、1階は広い共用スペース、2階を分けて友人と各自の部屋にする。一番上の屋根裏は雨漏りの跡などもあり、相当に手を入れないと住むことができない。借り主たる友人の男性の友達がそこに住みたいというので、結局女性2人・男性1人の計3人暮らしになる予定である。
3人で内見をした日の帰り、友人が「不動産屋さん、私たち2人には『親戚ですか? 友人ですか?』って関係性を聞いてきたけれど、【男友達】については聞いてこなかったよね。結局、男性だから、私と付き合っている人に違いないっていう思い込みがあるんだな」とぼそっと言う。確かに、そうだった。最初は2人で内見に行く予定だったので、私は「同性カップルだと思われたら、審査とか厳しくなるのかな」などと考えたりもしたが、今思い返すと、男性が来たことでかえって審査などがスムーズに済んだ面もありそうだった。
出来事その2。
去年、出版社から現在の職場に転職し、仕事内容は自分にとても合っていると感じる一方で、思いがけず人間関係で悩むことになった。そんな私を心配した知人が声をかけてくれて、仕事は続けながら、石原燃さん書き下ろし新作公演のお手伝いをすることになった。上演する東京演劇アンサンブルさんは、私がまだ大学院生だった頃から通い続けている劇団で、社会風刺のきいたドイツ戯曲や、パレスチナの劇団との共同制作、子どもたちが目を輝かせている隣で私が号泣してしまった児童劇など、思い出はつきない。舞台でキラキラとさまざまな人格・人生を身にまとっていた俳優さんたちと稽古場で顔を合わせることも夢のようで、稽古が始まった今でもまだ信じられない。それに石原燃さんも、『津島佑子コレクション』に寄せていた「人の声、母の歌」という文章が私はとても好きで、もう優に50回は読んだし、最近も友人と、男性の性暴力被害者をテーマにした演劇「蘇る魚たち」を見に行ったばかりである。
今回の演劇「彼女たちの断片」のテーマは、中絶。7人の、中絶経験があったり・なかったり、アセクシャルであったり、年代もバラバラな女性たちが2時間、自分のことについて、日本で認められている/認められていない中絶の方法について、ひたすらにおしゃべりを続ける。聞いているこちらの側も、その話の輪に入っていきたくなるような濃密な台本を手にし、ともかく自分には知識が足りないと反省して、表参道にあるウィメンズプラザの図書館に駆け込んだ。私は去年、3人ほどの友人から「私、中絶したことがある」と打ち明けられたけれど、それでもモテない私には関係のないことのように思い込んできた気がする。ウィメンズプラザの蔵書は古いものが多く、最初に手にとった堀口貞夫・堀口雅子『避妊の教科書』(自由企画、1994年)には「中絶の薬はありません」(p.170)、さらに、中絶したいという女性に対し「きちんと避妊をすべきでした」(p.172)と書いてあった。中絶の項目は、こんな記述から始まる。
「妊娠していることがわかれば、中絶を希望する人に対しても、妊娠を継続できない理由は何かを考え、そして妊娠を続けられない原因は本当に取り除くことができないかを考えます(中略)。それは医者の仕事が人間の生命を助けることにあるのであって、法律的にはまだヒトと認められない、受精直後のやっとできたばかりの小さな小さな生命であっても、それをなんとか助けられないかと考えるからなのです。」(p.155)
法律でヒトと認められないものをどうして生命と呼んで、妊娠主体である女性の意思より医者個人の意見を優先させようとするのか。妊娠している本人に人格はないのだろうか。そもそも北半球のユーラシア大陸やオーストラリア、北アメリカ大陸では妊娠初期の中絶について理由を問われたりしない、とは『中絶がわかる本』で知った(アジュマブックス、2021年、p.93。ものすごく勉強になったのでぜひ読んでください!)。
そんなトンデモ連発の避妊本で、私が一番読んでいて傷ついたのは、短いけれども、中絶手術時に「相手の人につきそってもらった方がよいでしょう」(p.159)という一文であった。妊娠の可能性は、本人の意思や性自認・性的指向にかかわらず、たとえば性暴力によって生じることもあるし、DVの加害者が相手を逃げさせないようにするために妊娠させる、あるいは中絶を強制するというのは周囲でも聞いたことのある話である。私も、一人で子どもを産みたいと思っているけれども、今回、職場の人間関係でつまずいたことで、経済状態の急激な悪化が自らの身にふりかかる可能性についても考えざるを得ず、たとえ妊娠したとしてもそれを継続できない事情が急にできることもあるだろうと感じた。どうして「相手につきそってもらう」(「もらう」、って!)と単純に書けるのか、それが当たり前に許容されていたことがとても残念で、また、発熱時に「家族に車で送ってもらってください」と言われた時の悲しさなどが蘇ってきてしまった。
一方で、同じくウィメンズプラザの図書館にあった、同時期にアメリカで書かれたものの翻訳『避妊ガイドブック』(文光堂、1999年)には、「中期中絶は外科的にも、薬物的にも処置できる」(p.372)という記述のほか、以下のような目をみはる事実も書かれている。
「中絶後の女性の方が出産後の女性よりうつ状態になる頻度は少ない。また中絶を拒まれた女性はその後何年にもわたって怒りを経験し、中絶を拒まれたのち産まれた子どもたちは、成人してもしばらくは職場や人間関係全般でつまずくことが多いという明白な証拠がある。」(p.353)
その後いろんな書籍も読み、やはり妊娠主体である本人の意思が何より優先されるべきだと私は思ったが、ぜひ演劇を見てそれぞれの立場から考えてみてほしい。
チケット情報は→ https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=64346&
(公演ごろに、アジュマブックスさんから石原燃さんの戯曲集も刊行されるそうです! 楽しみ!)
私は一人の人間なのか、意思や人格を持つ資格があるのか……。社会のさまざまな扱いによって確証を持てなくなる瞬間はやっぱりあるけれども、「おかしい」と思う気持ちを忘れずにいたいと思う。そこで声を出せば、どこかにいる同じような一人の誰かにも、おかしいのは自分の側じゃなく社会の側でありシステムの側だと、背中をなでるように励ます、ちょっとした助けになるはずだ。