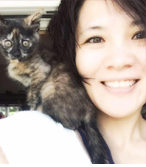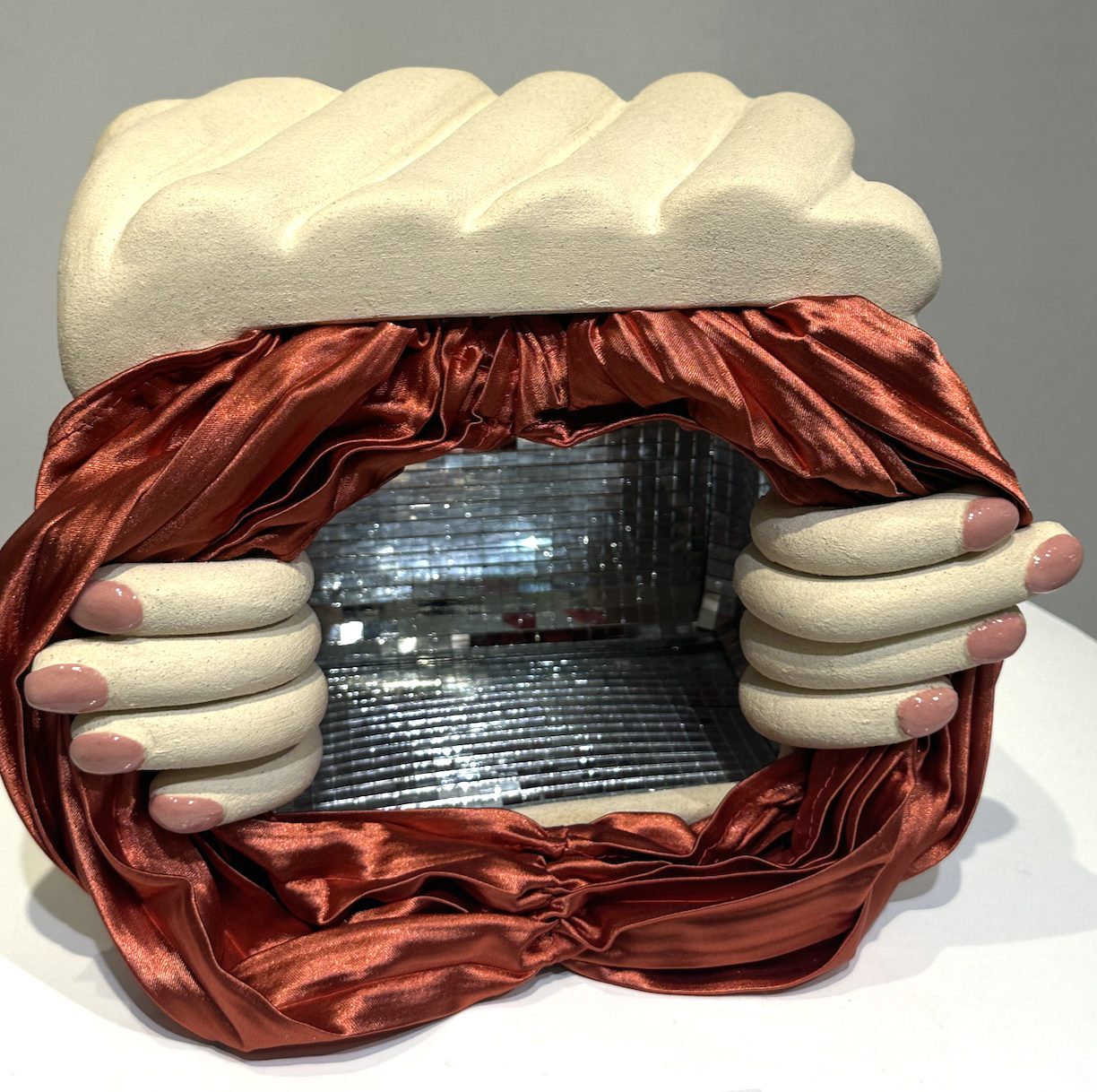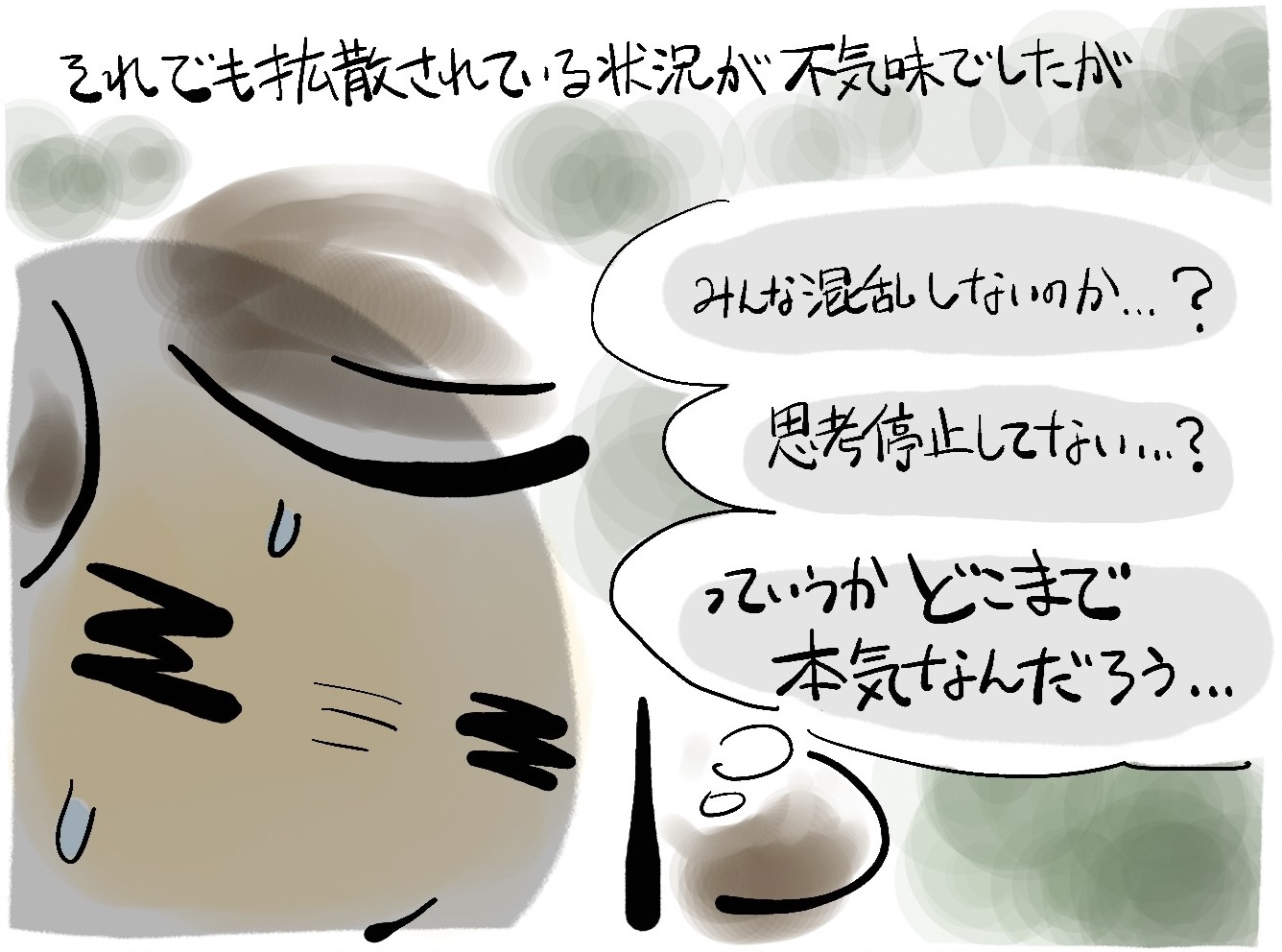オンラインイベントのご案内「井田真木子とフェミニズム」です。2015年に出版された「井田真木子と女子プロレスの時代」に寄稿した初稿原稿をみつけたのでここに転載します。明日(7月18日土曜日19時〜) まだ予約受け付けているそうです。詳細はコチラから
以下は、5年前出版された「井田真木子と女子プロレスの時代」(イーストプレス)に寄稿したものです。
「井田真木子と女子プロレスの時代」(イーストプレス)への北原みのり寄稿文
もちろん「プロレス少女伝説」からだった。20代から10度近く引っ越しを繰り返してきたけれど、一度も手放さずに持ち続けてきた。家を変える度に書棚を整理したが、私にとって「プロレス少女伝説」は、どうしても手元においておきたい本だったのだと思う。なぜかといえば「これは私の物語だ」と思えた、初めてのノンフィクションだったから。
「プロレス少女伝説」は、中年男性たちが野卑な視線で消費していた女子プロの世界を、少女たちが自分たちの力で「これは私たちの世界だ」と声をあげた、革命のその瞬間からはじまる。井田さんはその場にいた。少女でもなく、中年男性でもない者として、少女たちの足踏みが地を揺らすのを感じ、「帰れ」という強い意志の声に包まれ、そこにいた。
井田さんの緻密で臨場感ある描写から、「自分も目撃者であった」という錯覚をした読者は少なくないのではないか。少なくとも私は錯覚した。地鳴りの中の少女たちの声を聞いたような気持になった。というか、私自身が足踏みをして「帰れ」と叫んでいる少女の一人だった。
「プロレス少女伝説」を読んだのは20才の時だ。1989年に「終わった」とされる女子プロブームを支えていたのは、私たちの世代だった。ビューティーペアを幼い頃テレビで見ていた世代の女の子たちが、今度は主人公になった。女が女をその格好良さ、強さ故に憧れるような下地が、私たちの世代にはあったのだと思う。それでも、なぜ彼女たちに憧れるのか。なぜクラッシュギャルズでなければならなかったのか。なぜ神取忍に痛みを感じ、えぐられるようにひきよせられるのか。なぜ男の子のアイドルではなく、女子プロなのか。誰も言葉にしていなかったそのことを、井田さんは私たちに見せてくれた。評論家として分析するのではなく、彼女たちに語らせることで。少女のブームなんて、そして「いかがわしい」女子プロの世界だなんて、それまでプロレスファン以外、誰が言葉にしようとしただろう。何より当事者の女子プロレスラーと少女だった私たち自身が、自分たちが物語の主人公になることなど、考えてもいなかったはずだ。
社会的を賑わした事件や、大きな出来事を描くわけじゃない。それでも、人に向きあい、人を書くことで、時代の空気と社会の輪郭を描くことができる。そして「女」を描くことで、私たちがこの社会でぶちあたっている「性」というものの正体を見極めることができる。私はクラッシュギャルズのファンというわけではなかった。デラックス・プロレスは読んだことがなかった。それでも井田さんが物語る世界には確実に私がいる、と思えた。そのことは、私が今、書き手側になった時も常に意識していることだ。女を描こう、「ここに私がいる」と思ってもらえる世界を描こう、自分の目で物語ろう、と。
4年分の「デラックス・プロレス」での井田さん連載を一気に読んだ。井田さんは四年間の連載の後に、こう自身に問いかけている。「女子プロレスジャーナリストは何をどう書くべきか」と。そして答えが出なかったことを残念だと記している。そうなんだろうか。一気に読んだ後、そこでようやく、私は立ち止まった。
井田さんがいなくなってしまった2000年代、私は熱心に女子プロの試合に通うようになった。80年代と変わらないメンバーが、現役としてリングに仁王立ちし観客を熱狂させていた。30代や40代の女がリングで闘うことなど、かつて、誰が予想しただろう。観客席が中年の女で占められるなんて、誰が予想しただろう。私自身が、その「新しさ」に圧倒されながら、女子プロの世界にはまっていった。
井田さんが見られなかったリアルを生きる私には、だから、こんな風に思うのだ。80年代、多くの女子プロレスラーが自らの言葉で井田さんに物語った体験がなければ、また、井田さんが彼女たちを通して物語った世界がなければ、このように女たちは闘い続けただろうか。このように私たちは、リングに赤いテープを投げ続けただろうか。
誰も語らなかった、語る価値などないと思っていた、語ってもしかたがないと思っていた、そんな世界を井田さんは根気強く言葉にしていった。井田さんが言葉によって変えた未来を、私は生きたのだと思った。井田さんが出せなかった「答え」の世界を、私は知っているのだと思った。言葉によって、人がつながること。物語ることによって、生を実感できること。
井田さんの物語が、今、改めて多くの人に届きますように。あなたの物語として。(2015年)