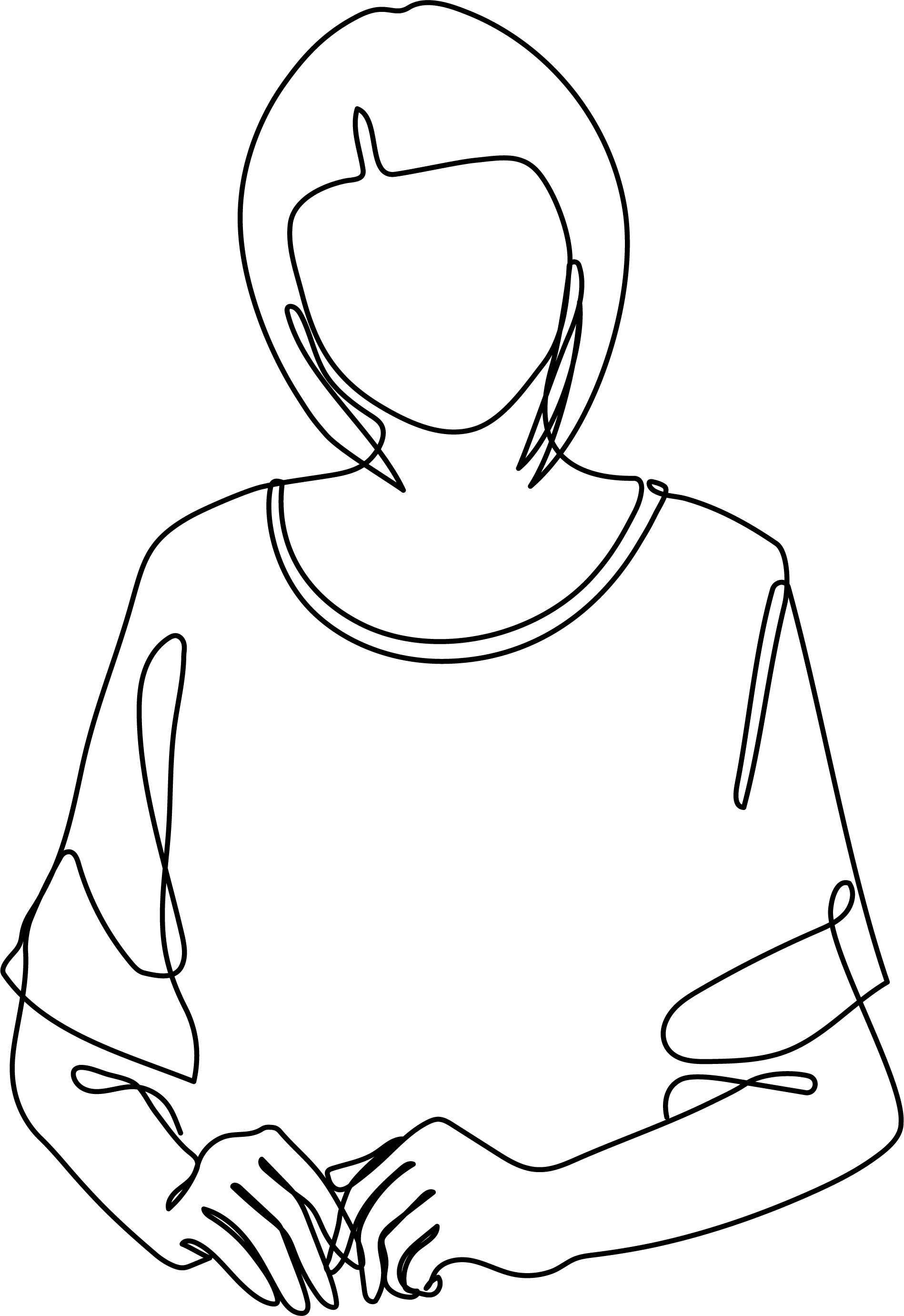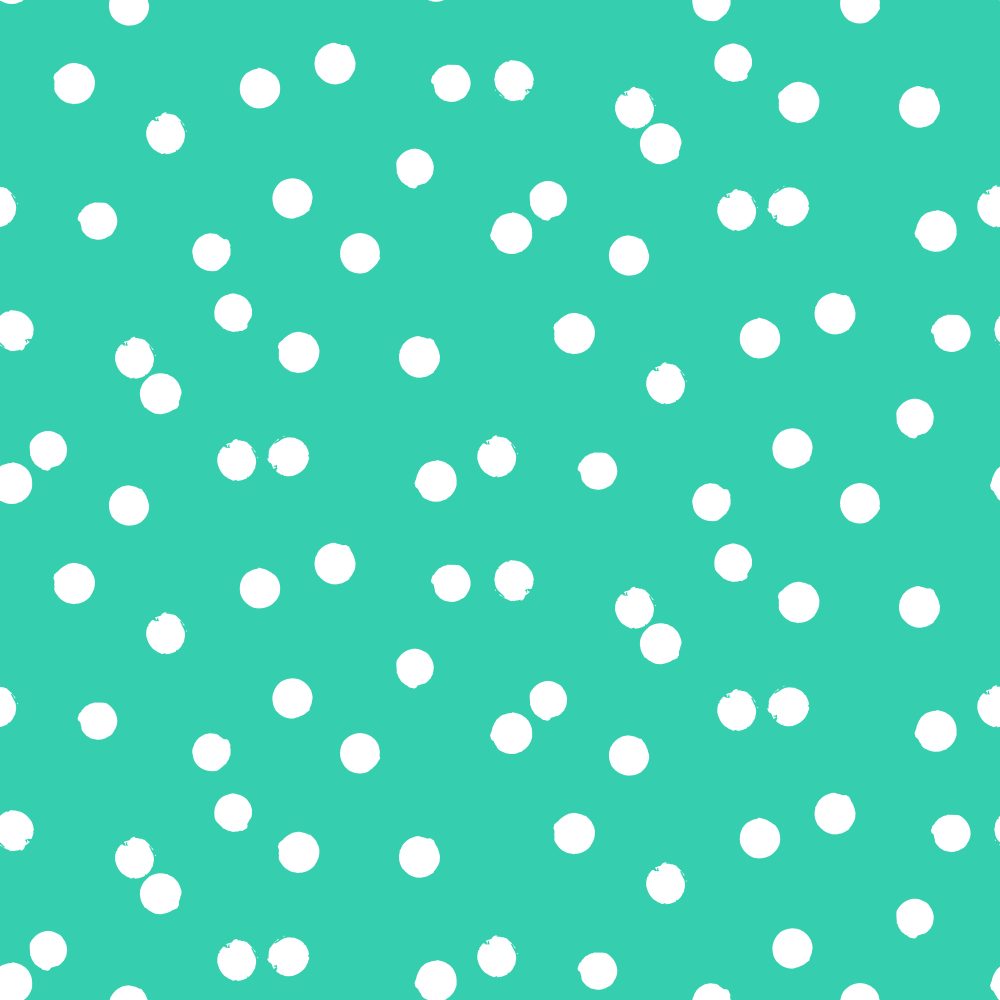ここ数年、何度か中絶問題の紹介や特集の企画をもちかけられながら、問題意識のすりあわせができずに話が消えた苦い経験をしている。いくら話し合っても、「中絶」に関する企画提案者の認識の甘さや偏った見方を修正できず、わたしが応じられなかったり、相手の方が下りてしまったりしたためである。どの媒体も大手だったゆえに、中絶問題をきちんと取り上げてもらえたら、差別や偏見をなくすためにきっと良い効果があっただろうと思えば、とてももったいない気がする。でも、偏見やスティグマを広められるよりは、まだマシだったのかもしれない。以下、主なできごとを3つ紹介しよう。
一つ目は、大手ネットニュース配信会社から「中絶の是非を論じる特集」を持ち掛けられた時のこと。その企画者は、わたしが「中絶賛成派」だと思い込んで声をかけてきて、他に同じ立場の人は誰がいるかと尋ねてきた。「中絶反対派」はすでに確保しているとのことだった。中絶に対する両方の言い分を「中立的」に取り上げて、ネット上で論争させたいのだという。
ちょっと待って。わたしは、そもそも自分は中絶そのものに賛成しているわけでもなければ、中絶すべきと言っているわけではない。現に日本で行われている中絶が、女性の健康と権利を守らず、スティグマの強いものになっていることを批判しているのにすぎない。確かに中絶をスティグマ化してくるプロライフの言説に対しては反対したいが、それは「中絶擁護」ではない。
企画者には、プロアボーションとプロチョイスの違いをまずは理解してもらおうとしたが、それがなかなか伝わらない。「塚原さんが嫌なら、当事者で中絶があって良かった、助かったという人はいませんか?」と言ってきた。
中絶があって良かった、助かったと思っている女性は大勢いるだろう。しかし、だからといって公の論争の場で、「中絶擁護派」の代表として、当事者としての思いを証言できる人なんてまずいないだろうとわたしは答えた。プロライフ派に「罪悪感」を掻き立てられ、誹謗中傷され、一方的にぼこぼこにされるのが目に見えているような証言台に、いったい誰が立てるだろう。
そもそも日本には「中絶のスティグマ」があるために、「中立的」な言論の場は保障されていないのだと、わたしは説明した。「中絶」という観念自体にスティグマが張り付いているこの社会で、二項対立的に「中絶の是非」を論じうると信じていること自体、すでに中絶批判の側に立っている。自分事でない第三者は、「中絶は悪だ、罪だ」と延々と論じることができる。いくら「中立性」を装っても、すでに決着はついているのだ。
だから、わたしは中絶擁護派として証言することはお断りだし、だれも紹介することはできない。問題の立て方を変えてほしい、権利の問題にするか、あるいは当事者の現実に大幅に寄り添った形にするのでもなければ、公正に中絶の問題を取り上げることはできないと主張した。
企画者にそこまでの熱意も関心もなく、結局、この企画はお流れになった。
二つ目は、大手出版社が大学受験用の現代国語の問題集で、わたしの訳したジュディス・ジャーヴィス・トムソンの「妊娠中絶の擁護」の一部を問題文として取り上げたいと言って来たことがある。
実はこの論文は、バイオエシックスの発端の頃に「中絶の是非」をめぐって様々な賛否両論をもたらした超が付くほど重要かつ有名な論考である。なのに、日本で翻訳紹介されたときには、原文の論旨がまったく分からないほどズタズタに切り裂かれ、日本人生命倫理学者が主張したい内容=「中絶した女が悪い」を言うがためにつぎはぎ細工の加工を施されていた。その問題に気づいたわたしが全文を翻訳しなおしたのが、新しい論集に掲載されている。それを読んだ編集者が、トムソンの冒頭の設定部分を「面白い」と思って連絡をしてきたのだ。
実際、とても面白い……SFチックで突拍子もない内容なのだ。トムソンはこの論文の冒頭で、世界的に有名なバイオリニストの生命を救うために、音楽愛好家たちがこの世でその役目を担えるのは「あなた」だけだと突き止め、あなたが寝ている間に勝手にバイオリニストの身体にあなたの身体をつないでしまった……という設定を示している。もちろん、バイオリニストは胎児であり、その命を救える唯一の存在とは、その胎児を宿している女性である。音楽愛好家たちというのは、プロライフ派の人々と考えればよい。
トムソンはこの設定を用いて、音楽愛好家たちが自分の信念(そのバイオリニストはかけがえのない大切な存在である)を貫くために、「あなた」の身体を勝手に用いることの倫理的・哲学的な問題を様々な形で指摘している。それ自体面白いのだが、ここで論文の内容を細かく紹介はしない。
ともかくその問題集の担当編集者は、上記の設定の部分を問題集に載せたいと思い、で訳者のわたしに引用の許可を求めて来たのだ。そこでわたしは、引用すること自体は構わないが、これが「中絶」に言及していることに気づく受験生もいるかもしれないので、くれぐれも慎重に扱っていただきたいし、問題文を作成したら、必ず確認させてほしいとお願いした。
やがて、外部のライターさんが書いたという「原稿」が届いた。問題文、読解問題の項目、回答……の後ろにくっついていた「コラム」を読んで、わたしは仰天した。そこでコラム執筆者は、
「中絶は胎児を殺すことであり、いかに悪いことか」を軽い調子で、だけどあからさまに論じていたのである。
わたしはすぐさま批判のメールを送った。「受験生の中には中絶を受けた女子学生だっているだろう。貴社はその子たちを傷つけるつもりなのか。こんな扱いをするなら、わたしの訳文の引用は一切お断りする。中絶問題を勉強し直して、コラムを書きなおしてほしい」と。
結局、ライターさんはコラムの書き直しができなかったということで、わたしの訳文はその問題集に載らないことになった。
三つ目は某テレビ局のドキュメンタリー番組のプロデューサーである。その人は「中絶問題」をかなり勉強してきて、中絶に関してシリーズで番組を作りたいのだと熱く訴えてきた。本気なのだと信じたわたしは、何度も長い時間を割いて取材に応じた。わたしはその人に、これまでも中絶を取り上げた番組はあったが、常に当事者に対して「可哀想」というスタンスに立つことで、結果的に「中絶のスティグマ」を強化する内容になってきた。だから、そうしたスタンスを踏襲しないでほしい、社会や医療の問題を分析することで、日本の中絶の問題に切り込んでほしいと、わたしはある限りの情報を提供し、さまざまな形で協力した。
ところが、最初の番組が形になりつつあった頃、そのプロデューサーから、突然、「塚原さんは番組に出しません」との連絡がきた。どちらかといえば画面に映りたくないと前々から言いつづけてきたわたしは、そのこと自体はむしろほっとしたくらいだった。ただし、彼女が「代わりに好感度の高い〇さんを出す」と言ったことに、わたしは一抹の不安を抱いた。
つい数か月前、この問題を知ったばかりで、中絶のスティグマから抜け出ているとは思いがたい〇さんで、「中絶問題」をきちんと訴えられるのだろうか。長年この問題に関わっていた人々はもっと他にいるだろうに……と。
わたしの不安は的中してしまった。放映された番組では、中絶当事者の女性たちの苦悩に満ちた証言や痛ましい手術の様子、その女性たちを「救う」医師の苦闘が描かれ、結果的に、「中絶のスティグマ」を強化する内容になっていたのだ。
テレビという媒体の限界なのだろうか。そういえば、上司が「中絶」を扱うこと自体を嫌っていると言っていた。そのプロデューサーからは、以来、何の連絡もこない。
他にも、取材したきり何も書いてもらえなかった経験もしているのだが、企画者やプロデューサー個人の認識の甘さだけではなく、男性優位のメディアの体質も影響しているのではないか。実際、三大紙の一つで記者をしていた優秀な女性が、「自由に書けないから」と言ってネットニュースに転職した例も知っている。
イギリスのBBCは「平等と公正さでリードしたい」と決意したゼネラル・プロデューサーのトニー・ホールが、トップダウンで「50:50プロジェクト」を開始した。社内のジャーナリズムやメディア・コンテンツに寄与する男女比を半々にしようという試みで、昨年の5月に最初の報告書が出ている。
このプロジェクトの結果、女性が半数を超えるプログラムが倍増したばかりか、下請け会社や他のテレビ局、新聞社、雑誌社にも波及しており、「視点が多様になった」と好評を博しているという。
実際、最近、”abortion”のことを検索するとよくBBCが引っかかるなと感じていたんだけど、このプロジェクトの影響があったのかもしれない。
日本のジャーナリズムもぜひ真似てほしい。