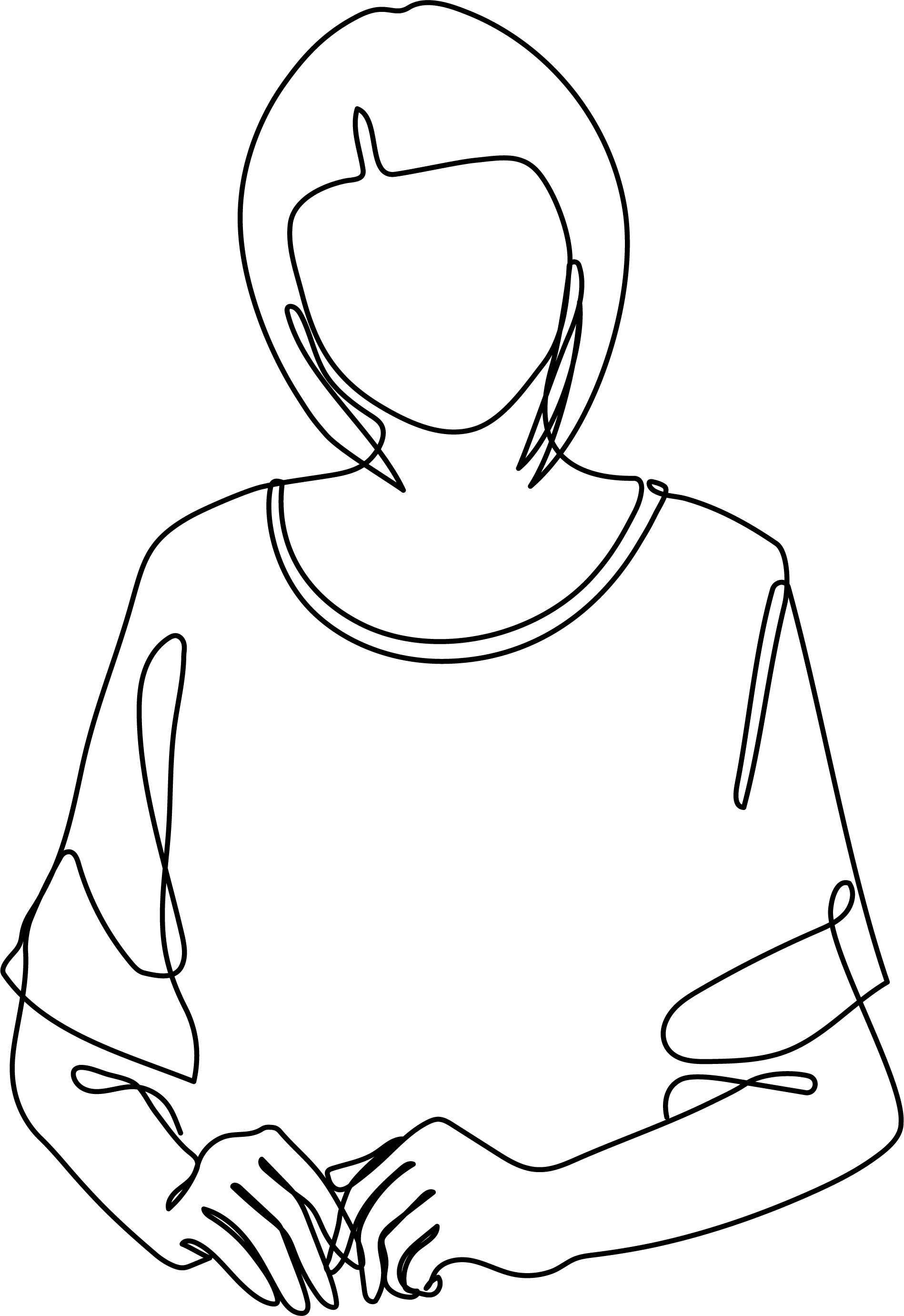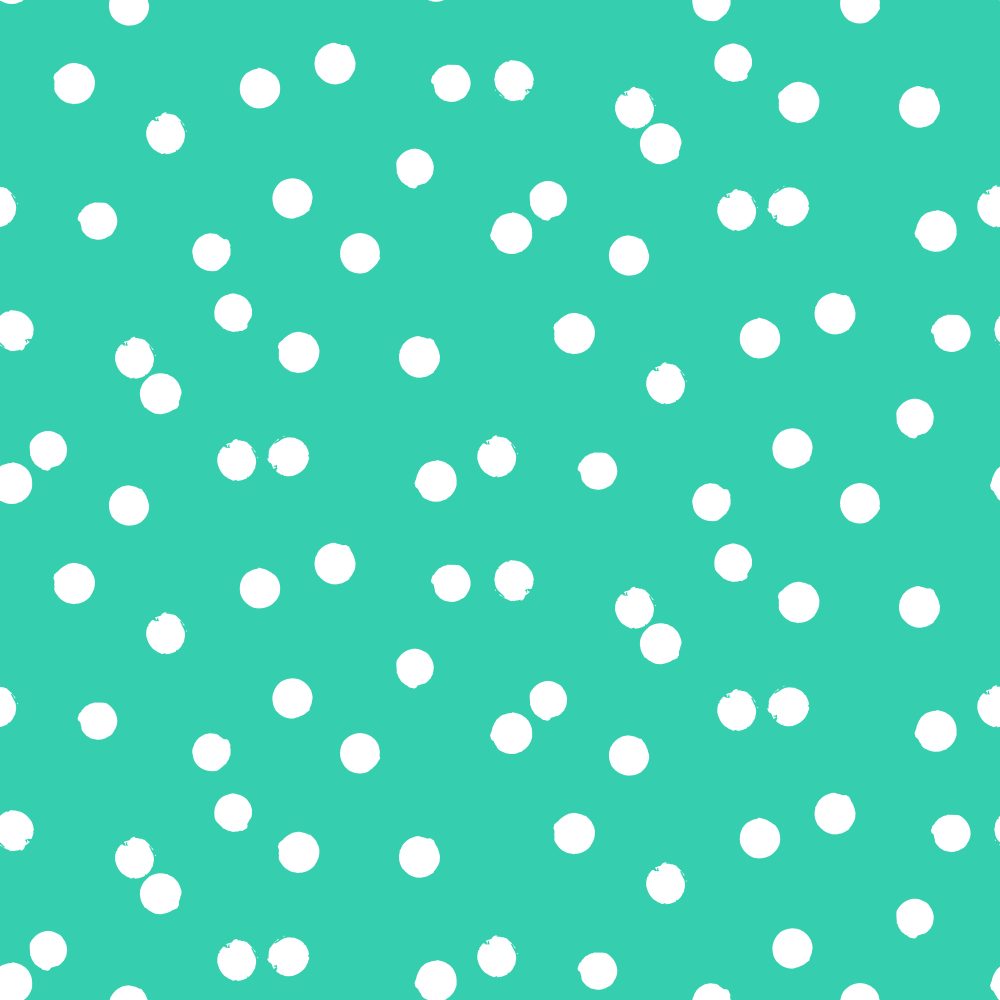中絶再考 その9わたしは中絶サバイバーだ
2020.03.13

去年の秋、仕事で東京に行っていた日にフラワーデモがあり、初めて参加した。性被害のサバイバーたちが次々とアピールしていった。北原みのりさんから、「久美さんにアボハラのこと話してほしい」と言われたが、わたしはどうしても、その場で中絶について語ることに抵抗があった。言い訳をしてしりごみし、ひとかげに隠れた。結局、最後まで何も言えずじまいに終わった。あとで、ちょっと自己嫌悪に陥った。
今年になって、性暴力被害者支援を行っているレジリエンスの講習会で話をしてほしいと代表の中島幸子さんに頼まれた。わたしが話す直前に、「性暴力被害より、中絶経験の方が話しにくいかもしれない」と幸さんがおっしゃったのに対し、「ああ、わたし一人ではなかったか」と少しほっとした。
実は以前からそれをずっと感じていた。レイプでもセクハラでも「被害者」が名乗りを上げるのはとても勇気のいることだと思うけど、性被害を受けた女性は「あなたは悪くない」と言ってもらえる。悪いのは一方的に暴力を加えた加害者であり、彼女たちは「被害者」だからだ。
だけど、今の日本で中絶を受けた女性たちが体験を語るのは別の難しさがある。わたしたちは中絶そのものに反対しているのではない。罪悪視されスティグマまみれの中絶に反対しているのだ。中絶経験者を苦しめている中絶をめぐる社会の通念や常識や制度や慣行等々に暴力性を感じていて、それに「No!」を突きつけたいのだ。
一般に、今の日本において中絶は「胎児生命を奪う行為」ゆえに悪だとみなされている。刑法堕胎罪の第一の保護法益は胎児生命だとされており、女性自身が自分の妊娠を終わらせる行為は自己堕胎という犯罪だとされている。そうした中絶観の下では女性は加害者の側に立たされてしまうし、そんな状況で中絶の苦しみを訴え出ても、「あなたが悪い」「あなたの自己責任だ」と切り捨てられてしまうのがおちだろう。
そんな風に思うから、中絶の経験はなかなか語ることができなくなる。沈黙によって断絶させられた女性たちは自分のパーソナルな痛みに囚われて外に踏み出せなくなり、社会構造の問題に気づきにくくなるため自責から抜け出せなくなってしまいがちだ。だけど実際には、わたしたちは中絶によって被害を受けたのではない。中絶は産むわけにはいかない「妊娠」をした女性にとっては一種の恩恵であって、それ自体が悪いわけではない。今の社会で「罪悪視されている中絶」であり中絶にスティグマを与えている文化社会のありようが、中絶を経験した女性たちを苦しめている。
わたし自身、中絶をめぐる「苦しい」と「自業自得」のジレンマに長く苦しめられてきた一人だ。中絶をしたくなかった……なのにしてしまった……選ばざるをえなかった……でも自分で選んだ……他に選択肢なんてなかった……自分が弱かっただけではないか……産み育てていきたくても支援も資源も制度も何もなかった……どうして妊娠してしまったのか……彼まかせだった避妊……まともな性教育なんて受けてない……なぜ女ばかり苦しむのだろう……男にとって子どもとは……赤ちゃんが欲しかった……無理にきまってる……できれば産んであげたかった……産んであげたかったのか自分が産みたかったのか……別のタイミングで妊娠していたら……女の犠牲……母性愛があるから苦しいのか……愛に飢えていたからか……わたしがもっと強ければどうにかなったのか……選んだのはわたしだ……わたしの人生……産まなかった子の命……何が正解だったのか……延々と自問自答してきた。
いろいろ考え、学んできた末に、今では中絶を経験した女性の罪悪感や自己否定は、社会から無意識に受けつづけてきた不当な攻撃、糾弾、怒号等々を内面化した結果だと理解している。そのように理解したことで、今は「中絶の苦しみ」そのものからはほとんど回復することができている。心の平安を得るまでにずいぶん長い月日を費やしてしまったが。
苦しみを深める個人的な要因もいろいろある。わたしの場合、子どもの頃から「お母さんになる」ことに大きな意味付けをして育ってきたことが、苦しみを強めたように思う。いい悪いではなく、単に行きがかり上そうだったということだ。もちろんそんな信念を形成するために、「女性なら産み育てるのが当然」とする文化や通念、社会に満ちている母性愛神話、子どもを「愛の結晶」とする観念、「受精の瞬間から命」といった教えなども大いに影響していたことは間違いない。
実際には、「母親になる」ことは数ある選択のひとつにすぎないのだし、女の人生は出産の有無のみで測れるわけはなく、「母性愛」は女性を自縄自縛にしている作られた何の根拠もなく相対化可能な神話であって、受精卵から胎児へと発達していく途中のどこで「人間の命」になるかというのは恣意的な線引きでしかなく、仮に受精しても三分の一は何らかの形で流れてしまう……といった知識を得てきたことで、わたしの妊娠や胎児に対する認識は大きく変容したし、社会文化的な視点から自分の「中絶意識」を相対化できるようになった。
とりわけ、男性中心主義的でミソジニーが蔓延している今の文化の中で「女」であること自体が格下に位置付けられており、パワーをもつ人々が「中絶」を罪悪視してみせることで女たちに罪悪感を抱かせ、女が自らの力を自発的に封じ込めていくようにコントロールしていることが見えてきたことで、わたしの中の「罪悪感」はある種、中和されていった。代わりに、そうした家父長制的なパワー構造の理不尽さ、不当さに気づくことでエンパワーされてきたように思う。
中絶にまつわる苦しみは人それぞれで、その人の性格によっても受け取り方はさまざまだから、わたしの悩みや苦しみが特別のものだったとは思わない。また、中絶を経験しただれもが深く傷つき悩むべきだとも全く思わない。
ただ、子どもの頃から偶然積み重ねられてきた経験やそこで考えてきたことなどが、それぞれの人の「苦しみ」を形成してしまい、どうしてもスルーできず、立ち止まり、うずくまって悩んでしまうことがあるということは、自分の体験からもよく分かる。それに、今の日本の社会が中絶を経験する人の苦しみをいや増しに増してしまうような問題をいくつも抱えていることをわたしは知ってしまったから、今、中絶で悩み苦しんでいる人がいるならば、自分の苦しみを楽にしてくれたあれやこれやの「気づき」をさまざまな形で伝えることで、次の一歩を踏み出せるような力を見出してほしい。女性差別は一朝一夕に消えるものではないけど、抑圧のあるところには必ず抵抗がある。ささやかな抵抗を続けていくことに、わたしは自分の存在意義を感じていきたいのかもしれない。
わたし自身が中絶を経験してからすでに40年近い年月が経った今、過去の自分に声を掛けられるものなら、「あなたは悪くない」と言ってあげたい。わたしたちは中絶が必要になり、それを求めた。あとは社会の側に問題があるのだ。悪いのは、「中絶」をことさらに「罪悪」だとみなすことで女性たちに罪悪感を植え付けている家父長制的な法であり、スティグマの強い中絶方法しか提供しないことで女性の心身を痛めつけている医療システムであり、女性たちを苦しめている性差別的な法や制度をなくそうとしない国の方なのである。この理不尽な状況に、女性たちはむしろ怒っていい。この国で中絶を経験した女性たちは日本の中絶問題の犠牲者なのだ。そのことを見据えた上で、わたしは個々の女性が中絶の経験からエンパワーされていく方向を示していきたい。
冒頭で紹介したレジリエンスでの講義の終わりに、中絶について新たなイメージを構築していくことをわたしは提案した。中絶とは、女性の健康と権利のために不可欠な医療ケアであって、不本意でネガティブな妊娠の経験を自己決定によってプラスの側に軌道修正するものであり、その場面で自律的に勇気をもって決断できたことは自負となって女性たち自身をエンパワーし、苦境から救われた喜びへの感謝と安堵の源泉となり、ひとつの人生のターニングポイントとして反省と成長をもたらし、今後の生き方や関係性について展望をもたらしてくれる経験となり、何よりも女性にとっては3~4人に1人が生涯に一度は経験するような日常的で当たり前のことなのだ。だからこそ、より良くより安全な中絶を求めていこう。それを妨害するあらゆる力と闘っていこう、と。
中絶に対する罪悪視やスティグマ、ポジティブな中絶観を抑圧してくる言動や考え方、イメージなどのすべてが女性たちを苦しめるハラスメントであり理不尽な暴力なのだ。だから、そんな力に屈していきたくはない。互いに経験した中絶の苦しみについて語り合い、共通項を見つけていき、仲間とつながっていくことで、アボハラの不当性と暴力性に気づいていこう。それを言語化していこう。内面化してしまったネガティブなイメージから脱していこう。
今はまだわたし自身、フラワーデモで叫べるような端的な「メッセージ」は持ち合わせていない。でも、それを見出していくためにも、まずは自由に中絶の経験を語りあえるような安全な場が必要とされているのではないだろうか。