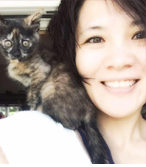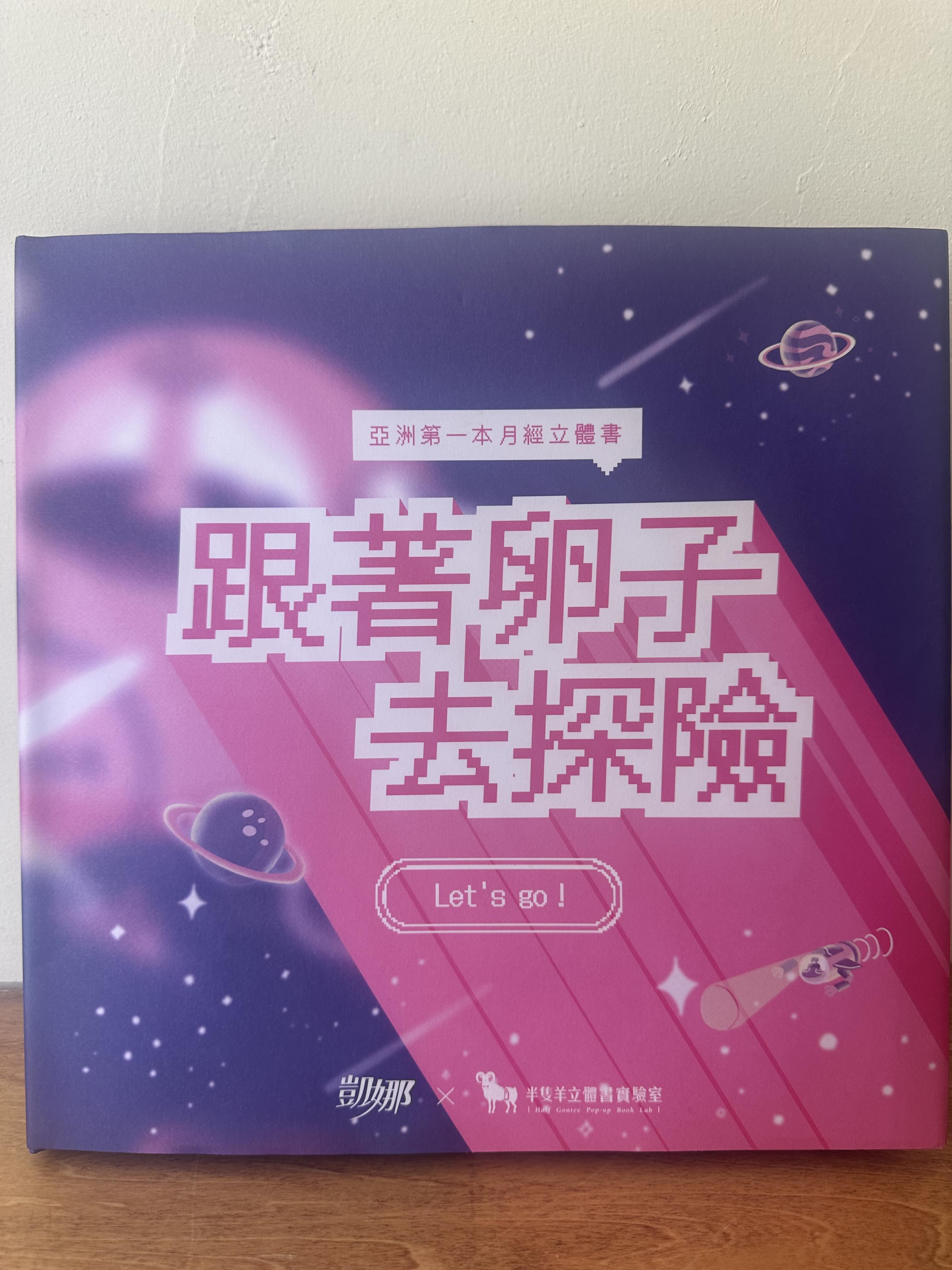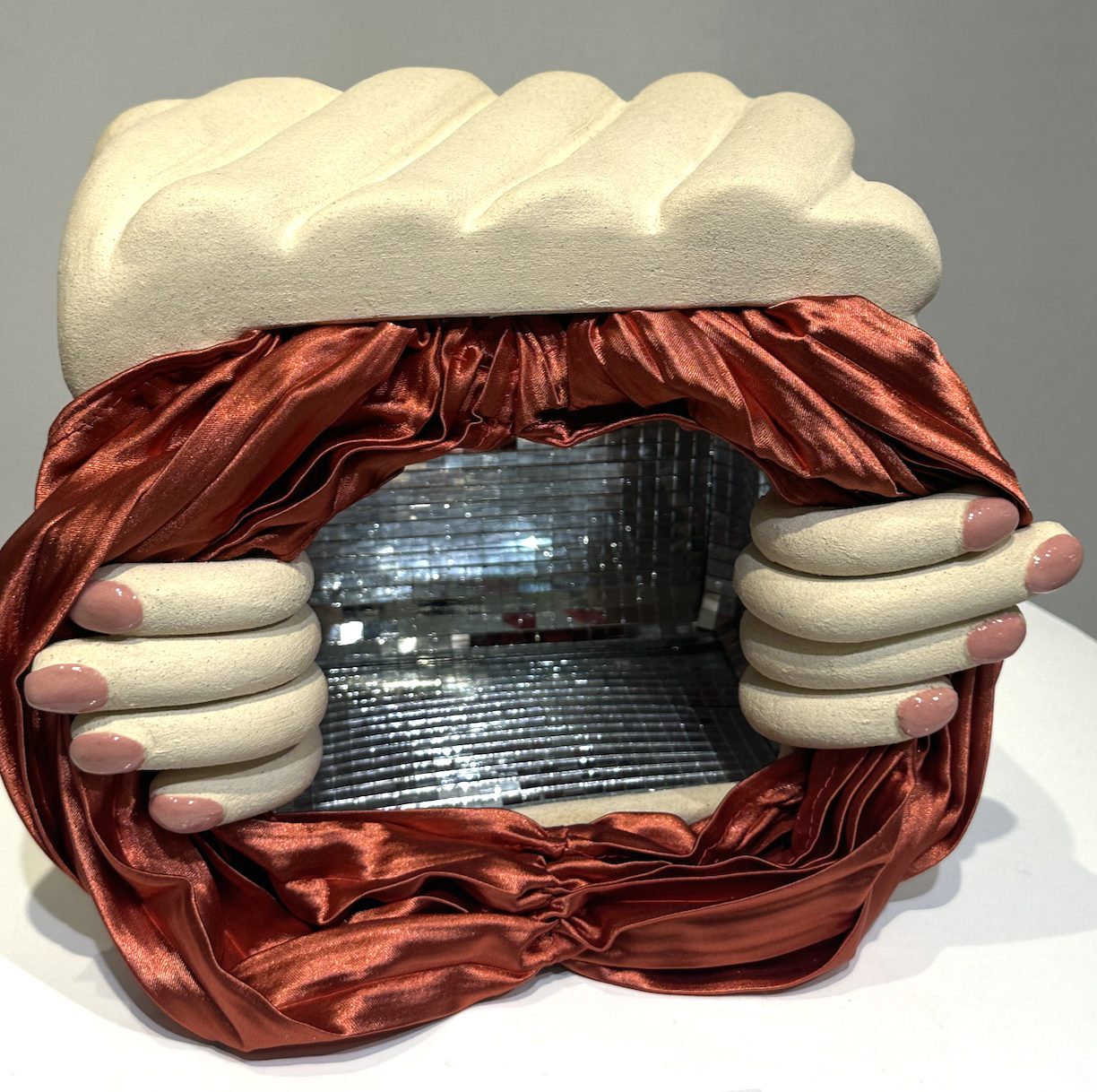2月のフェミ読書。性差別とエイジズムと”いかふぇみ” にのみこまれないために。
2020.02.17

忘れられない本を何冊かあげてと言われたら、「私の目を見て―レズビアンが語るエイジズム」を入れると思う。大好きな本というわけではないのだが、ただ文字通り、忘れられない。
「私の目を見て」は、80年代にソーシャルワーカーでありレズビアンフェミニストのバーバラ・マクドナルド(米国人)がエイジズムについて記した本だ。日本で出版されたのは1994年。私は20代で大学院に通っていたか辞めた頃だったかで、まぁ若かった。それなのに、アメリカに暮らす80代の女性が書いたエイジズムは自分の物語だとも思ったことも含め衝撃を受けたのだ。
それは、高齢女性が社会から受ける「まなざし」の物語だった。豊富な知識と経験を持つ高齢者が、敬意を払われるどころか保護すべき存在、嘲笑される存在になっていく。例えば病院にいけば医者が隣の娘に話しかけたり、自分に話しかけるときは大きな声で、幼い子に話す調子になるような屈辱的な現実。
同じだ、と思った。80代にならずとも、それは日本に暮らす20代の私の日常だった。例えばちょうどそのころ私は人生初のパソコン(りんごマーク)を買ったのだけど、買うのは私だというのに店員は一緒にいた男友だちにしか語りかけなかった。もう四半世紀近く前のことなのに、今でも悔しい。例えばあの頃、先に社会人になっていた友人が、会社で電話を取ると「男に替わって」と言われることがフツーにあると言っていたが、女として生きること、それは目を見られないどころか、透明人間になるような気分だった。
もちろん若さに過剰に意味を持たせる日本に生きてれば、若いというだけでちやほやされることもある。でもそれって今思えばちょっと面白そうなパーティーにただで入れる権利くらいのもので、どちらにしても若さへの過剰な礼賛はエイジズムの裏返でしかない。
・・・・・・・・・・・・・・・
そんなことを今、書きたくなったのも、私自身がアラフィフになってから、これは酷いわ、想像以上だわ、という気分にさせられることが続いているからだ。
先日、同僚男性との給与が15万違うことが発覚した! と知人の女性(48才)が教えてくれた。地方では名の知られたそれなりの会社だ。「妻子のいる男性が優遇される」という噂は聞いていたが、まさか同期の男性と15万円差がつくとはね。しかも、彼女の部下である男性たちが、彼女を通さず彼女の直属上司(男性)に直接話をつけてしまうような屈辱も味わいながら、「自分が女だからではない、自分の能力が足りないからだ」と必死に頑張ってきたけれど、もう無理、辞めると宣言した。
また別の日に聞いたこと。彼女の勤め先は、不況のあおりで早期退職者を募ったのだが、同時に女性の多い部署を真っ先に切った。そこを統括していた50代の女性(彼女が育てた部署だった)は当然行き場を失い早期退職の道を選んだ。
また最近聞いたのは政界の話。候補者を選定する段階で、50代以上の女性にはほぼチャンスが巡ってこないという。まるで女の候補者は40代までの美人じゃなければ価値がない、とでもいう暗黙のルールがあるかのように、男の有権者目線(ファンタジー上の)で候補者が選ばれる。
どんな地位にいようが、どのような職業にあろうが、組織の規模にかかわらず、わりとあっさりと切られていくアラフィフの女友だちは一人や二人ではない。彼女たちは合法的にスマートな方法で、あたかも自分の意思でそこから去るように(というか実際、「こんな職場いられねーよ!!!」と最後はみんな自主的に去るのだ)、職を奪われる。中高年男性の高い給料を守るために、組織の体力を守るために、新しい世代を入れるために、中高年の女の生活=人生が軽く見られている。
これから就職をしようとする女性に心から伝えたい。女性の顔が暗い会社には入らない方がいい。2020年現在、女性の人生を軽視し乱暴に扱う会社は、10年後には生き残っていないので。
・・・・・・・・・・・・・・・
そんなエイジズムの話をした時に、編集者の友人にすすめられて手にしたのが塩沢美代子・島田とみ子共著「ひとり暮らしの戦後史〜戦中世代の婦人たち〜」だ。
塩沢さんは、1924年生まれ、ソーシャルワーカーとして、またジャーナリストとして、生涯独身で生きた女性たちの言葉を聞き取ってきた。島田さんは1927年生まれの朝日新聞記者で、71年退社後にフェミニズムに関する本を多数記している。
1920年代生まれの女性は、突出して、一人暮らし率が高い。
戦争で夫が死別した者も多く、結婚しようとも男性が少なく、経済的保証としての結婚を諦めた世代だ。とはいえ、この国に独身女性に寄り添う制度はなにひとつなく(今もです)、自分のために使われる税金はほぼゼロで(今もです)、男性より賃金が低いのは当然とされ、女性の定年は45才とか50才というのが一般的だった。経済とはまさに命の問題。そこでの機会が圧倒的に不平等であることで、女性たちが強いられる屈辱、命の危機、恐怖、不安は、決して昔話ではない。「昔の本」としてではなく、今につながる女性差別史の記録として読んだ。
読みながら、じわじわと幼い頃の記憶が蘇ってきた。そういえば私の幼い頃、一人暮らしのおばあさんが、周りにたくさんいた。駄菓子屋を営んでいるおばあさん、タバコ屋をやっているおばあさんは大抵みんな一人暮らしだった。というか、私の祖母も、そして祖母の妹も非婚組である。
特に旅館を経営していた祖母のまわりには、身寄りのない女性たちが集まっていた。当時"仲居さん"”女中さん"という仕事は、“そういう女性たち”のものだったのだ。
本を抱きしめるように読みながら、私はたくさんの「おばあさん」に育てられたのだと気がつかされる。美味しいお握りの握り方、そろばんの使い方、シーツのたたみ方、お節料理の種類、花札のあそびかた、夏の海での過ごし方、浴衣の折り方、花火大会でのかけ声、少し猥雑な冗談、勢いあるお商売の空気。仲居さん、女中さん、芸者さんたちが忙しく仕事をする日常のなかで知っていった。
なぜ私が、女であることを卑下せずに生きてこられ、すくすくとフェミになったのかと言えば、フェミニズムを勉強したから〜ではなく、女であることがそもそもフツー、そもそもおばあさんが私の“人間の基準”だったからなのかもしれない。社会保障もないなか必死に生きる女性の日常に守られていた私の幼少期。一人暮らしの女たちだから、男に威張られる姿も、媚びる姿も、自分のことをほっぽり出して男を世話をする女の姿もみることなく、女たちのあたたかいおしゃべりに包まれた空間で、私は柔らかく守られ育ったのだ。
1925年生まれの祖母は「40代が一番楽しかった」と言っていた。祖母の40代とはウーマンリブ真っ盛りの1970〜80年代のことだ。祖母とウーマンリブはまったく縁はないようだったけれど、それでも生き方はシスターフッドそのものだった。旅館を畳んだ後も、身よりのない女性(私にとっても、もうひとりの祖母だった)を自宅の離れに住んでもらい最期を看取った。一緒に働いていた女性の多くは祖母より早く逝ってしまったが、交流はずっと続いていた。そんな風に、一人暮らしの女性たちの生き方、やさしいつながりが昭和の真ん中頃にあったのだ。大きく語られることもなく、偉大化されることもなく、差別に喘ぎながらも手をとりあって生きようとした女性労働者たちの人生。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ひとり暮らしの戦後史〜戦中世代の婦人たち〜」のなかに、こんな女性の声が残されている。
成績が良かったが戦中のため進学を諦め、結婚。なかなか子どもを授からず、そのうち結核であることが分かり、離婚。「嫁の仕事」は子どもを産むこと、家のための無償労働とされていた田舎で(民法変わったことを知らない人が、今も昔もいるのです)、慰謝料もなく自ら身を引く形になったが、離婚後、長い鬱病に苦しめられた。その後、病院の炊事係などを務めるうちに、看護師への酷い扱いや、男女賃金格差を目の当たりにし、ずっと自分がダメだから離婚された、自分がダメだからこんな給料で仕方ないのだ・・・と思っていたことが社会の問題だと気がつき、労働運動に関わり自身の権利のために闘い、生きる力、尊厳を取り戻していく。
塩沢さんたちが聞き取った、そんなひとりひとりの命の声が、ここにある。読みながら突きつけられるのは、これが過去の話ではなく、むしろ唖然とするほど「今の問題」であること。そもそも日本社会は、経済も、組織も、家族も性差別をベースに設計されている。だからフェミは設計そのものが間違っていますよ! と言い続けてきた。今も同じことを言い続けなければいけない現実に絶望したくもなるが、そこはこらえて今こそ、塩沢さんのような仕事を改めて手にする時間が必要なのだろう。本気で変えるために。
フェミ本が売れているという。だからこそ長い長い長いフェミニストたちの戦いを無効化せず、本気で変えていけるかが今、問われているのかもねと思う。「”古いフェミ”を否定することで”今のフェミ”の新しさをアピール」みたいなフェミの悪循環(80年代あたりからの)からそろそろ脱却しなきゃまずい状況にも思うし。フェミを無効化する”いかふぇみ”(笙野頼子さんの造語=原初的な女性の戦い、怒り、悲しみを乗っ取ってその本質や大切な部分を無効化してしまう捕獲装置。フェミな顔しているので要注意)や、”ちかんやろう”(笙野頼子さんの造語=”知と感性の野党労働者党”の略語。いわば児童虐待表現を、"ひょうげんのじゆう"と言いはり、いかふぇみと一緒に女の痛みを嘲笑する輩のことです)にのっとられそうな危うさを、”フェミブーム”のなかにうっすら感じつつ、自分の手足をもぎ取られないために。フェミニストの根幹にある、怒り、悲しみ、悔しさの言葉。ずっと昔から私たちと一緒に歩いてきたフェミの言葉を、手にしたい。