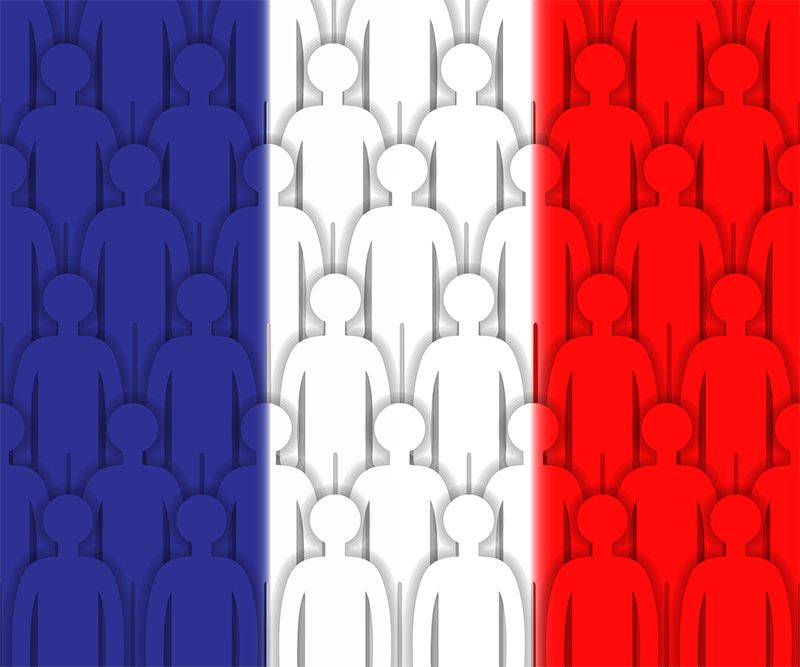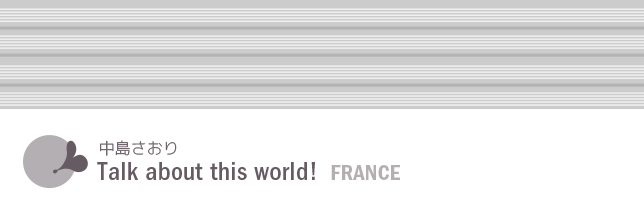
社会の意識が変わる時、それはパタンと変わる。今まで目に見えなかった少数意見が積もり積もってある限界を超えた時、突然、今度はそれが、人々を吸うようにして多数派になる。すると後はドミノ倒しのようにすべてがパタンパタンと倒れて風景を一変させてしまう。
2020年の1月2日、一冊の本が出版された。グラッセ社から出た『Le Consentement(合意)』というその手記は、著者ヴァネッサ・スプリンゴラ(現在47歳)が、14歳の少女だった80年代の数年間、当時50代だった著名作家ガブリエル・マツネフ(現在83歳)の愛人だった経験を、フィクションを交えずに書いた実話小説だ。両親が別れ、読書に孤独を癒していた少女は、夕食会で出会った作家(本の中ではG.M)の好意を受け入れ親密になるが、この作家が少年少女を渉猟するので有名で、またアジアで未成年の買春旅行を常習としていたことを知り、関係を断つ。しかし作家は彼女との体験を小説に書き、それが彼女を後々までも苦しめる。その苦しみから逃れるため、彼女は自分を支配した男の武器を逆手に取って闘うことにする。すなわち書くこと、その結果がこの本だ。
そこには中年作家がどのような方法で少女に近づき、どんなふうに性関係を許容させたかが書かれている。彼女はたしかに「合意」した。しかし14歳の少女に、本当の、自由な判断力はあっただろうか。
この本が出版されるや、出版界は騒然とした。マツネフは自分の小児性愛を隠したことはなく、何十年も延々と発表してきた『日記』に、何をしてきたかは事細かに書かれている。それを、「自らをドリアン・グレイとドラキュラを混ぜたようなものと定義する悔い改めない誘惑者」(フレデリック・ミッテラン評)、「ラテン文学の教養のある遊び人、知的な誘惑者、形而上学の栄養士」(ジャン・ドルムソン評)、「安全に悦楽を発見する知的な少女たちの永遠の師は、彼を小児性愛者に類別しようとする人々からの制裁に遭う」(「ルモンド」評)などと持ち上げて来たのは文学界だったからだ。つまり批判の矛先は、未成年者に性行為を繰り返した人物だけでなく、その行為を書いた物を発表して文学者として厚遇してきた文学・出版界にも向けられているのである。
マツネフは、フランス学士院賞とルノドー賞エッセイ部門を受賞し、文化省から勲章を授与され、国立書籍センターの助成金も受けている。
しかし検察が、時効になっているスプリンゴラの事件以外にも被害者はいると見て取り調べを開始した今、もう擁護する者はなかった。『日記』の版元であるガリマールはすぐ販売停止の決定をした。他の出版社も次々に続いた。文化大臣は彼の給付金を停止すると決めた。
今や、マツネフを擁護する人はほとんどいない。初めはポランスキー事件に継ぐ「魔女狩り」だと言った人も二、三いたが、現在、編集者、作家のほとんどは沈黙しているか、マツネフを断罪している。
いったいなぜ小児性愛者が犯罪を問われもせずに何十年も作家として尊敬を受けてきたのだろうと、悪い夢から覚めたように人々は疑問に思い過去を振り返った。
読書の神様のように尊敬されて悠々、リタイアし、平穏な日々を送っていた文芸ジャーナリスト、ベルナール・ピヴォは、突然、激しい批判にさらされた。彼は1975年から1990年まで、新刊書の著者を招いて座談会をするテレビの人気番組「アポストロフ」で司会を務めたのだが、1990年、今から30年も前に、マツネフを招待した回のワンシーンがネットで流れたのである。「真の性教育の先生」と冗談半分に持ち上げ、マツネフの小児性愛趣味に寛大な態度を取っていた姿が、現代の人々のひんしゅくを買った。他の出席者もマツネフの言葉ににこやかに笑うなか、カナダ人のジャーナリストでフェミニストのドニーズ・ボンバルディエだけが、マツネフを「子どもを飴で誘う代わりに文学のオーラで誘っているだけ」と看破し、「マツネフ氏は読むに耐えない。13、14の子と肛門性交したなんて。文学は口実にならない」と違和感を述べたが、番組のなかでもその後の新聞などでも冷笑されて終わった。今の眼でみると、彼女だけが理性的に見えるのだが。
ピヴォは、はじめ、ツイッターで「70、80年代には芸術が道徳に優先し、今は道徳が芸術に優先している。道徳的には、それは進歩だ。我々は知的、道徳的に、多かれ少なかれ、国の、またとりわけ時代の影響を受ける」と言って火に油を注いでしまい、その後、「当時のジャーナリストが馴染んでいた自由の逸脱から距離を取る明晰さを欠いていた」と言い直した。たとえ小児性愛を描いた芸術が成り立っても、犯罪者が芸術を理由に制裁を免れて良いわけはない。しかし時代が変わったというのは事実だろう。
1977年にマツネフは、未成年への強制猥褻罪に問われた被告を擁護する署名文を起草し、69名の著名人が署名している。アラゴン、ボーヴォワール、サルトル、バルト、ソレルス、ドゥルーズ、グリュックスマン……そのそうそうたる名に驚く。これだけの人たちが、なぜ「子ども、青少年が、自分の選んだ大人と関係を持つ権利」を刑法は認めるべきだと訴えたのか。
それは68年五月革命以降の、性のタブーを破って行くことがすべて肯定されていた時代の雰囲気を知らないとわからないかもしれない。性的に寛容であるほど良く、保守的、道徳的であることはネガティブに評価された。マイノリティの性を認めていく中に小児性愛も紛れ込んだのだろうし、子どもの人格を認め大人扱いするという流れが、子どもが自由意志で大人と性交するという幻想を作り出したのかもしれない。
しかし自由奔放なセックスの時代は、エイズの到来とともに終わりを告げ、2000年代の初めになると、少女たちを監禁して数人を死なせたマルク・デュトルー事件がフランスを震撼させ、小児性愛は断罪される。
少しずつ、新しい世代が成長してくる。性革命の時代に青春を送った世代は今や60、70代、もっと落ち着いた性行動をするようになったと言われた世代がすでに50代、40代……さらに若い世代は高齢世代の「性の自由」への熱狂を共有しておらず、そのネガティブな、ハラスメントである部分の方がむしろ意識される……。
≪Le Consentement(合意)≫は、♯MeToo以前、つまりほんの3年も前に出たら、これほどの反響を呼ばなかっただろうと著者は言っている。さらには、実は90年代に、マツネフの犠牲者の一人がやはり告発本を書いたが、出版されることがなかったことも明らかにされた。『合意』を出したのと同じグラッセ社で、編集者の目には留まったが、上司に潰されて刊行されなかったそうだ。今はその上司も現役を退いている。
最後に、タイトルの「合意」について。主人公Vは、決して暴力的に強姦されたわけではなく、GMが恋愛関係と思い込む(Vも当初はそう思っていた)関係がそこにはあった。けれど、知的文学的オーラを纏った大人と未成年の力関係の中で、少女の「合意」とはなんなのか。
このような構図は、♯MeTooを経験した今、フランスのみならず、日本の人々にも理解しやすいに違いない。日本でもちょうど性交同意年齢が13歳に据え置かれていることが問題になっている。性交同意年齢以下の子どもに対しては、「暴力・脅迫」がなくても強姦とみなす、そのような基準になる年齢が、13歳ではあまりに低く過ぎるだろうという議論である。
しかしフランスではそもそも、「性交同意年齢」というものがない。2018年に性暴力法を定めた際、「挿入があった場合、15歳未満であればひとしなみに強姦とみなす」という性交同意年齢の規定(フランスでは「想定不同意」と言う)が検討されたが、結局、盛り込まれなかった。コンセイユ・デタ(国務院)が、「想定不同意」は、防御の権利を尊重しないため憲法違反と考えたらしい。「成人と一定年齢未満の未成年との性関係が全て強姦であるとは言えない」と反対したためだ。
しかしマルレーヌ・シアパ男女平等問題担当国務大臣は、≪Le Consentement≫の刊行は、社会の意識を変え、2020年の改正時にはこれを盛り込むことができるだろうと発言している。
「誰も、子どもと自由に性関係を持てると思うことができないように」