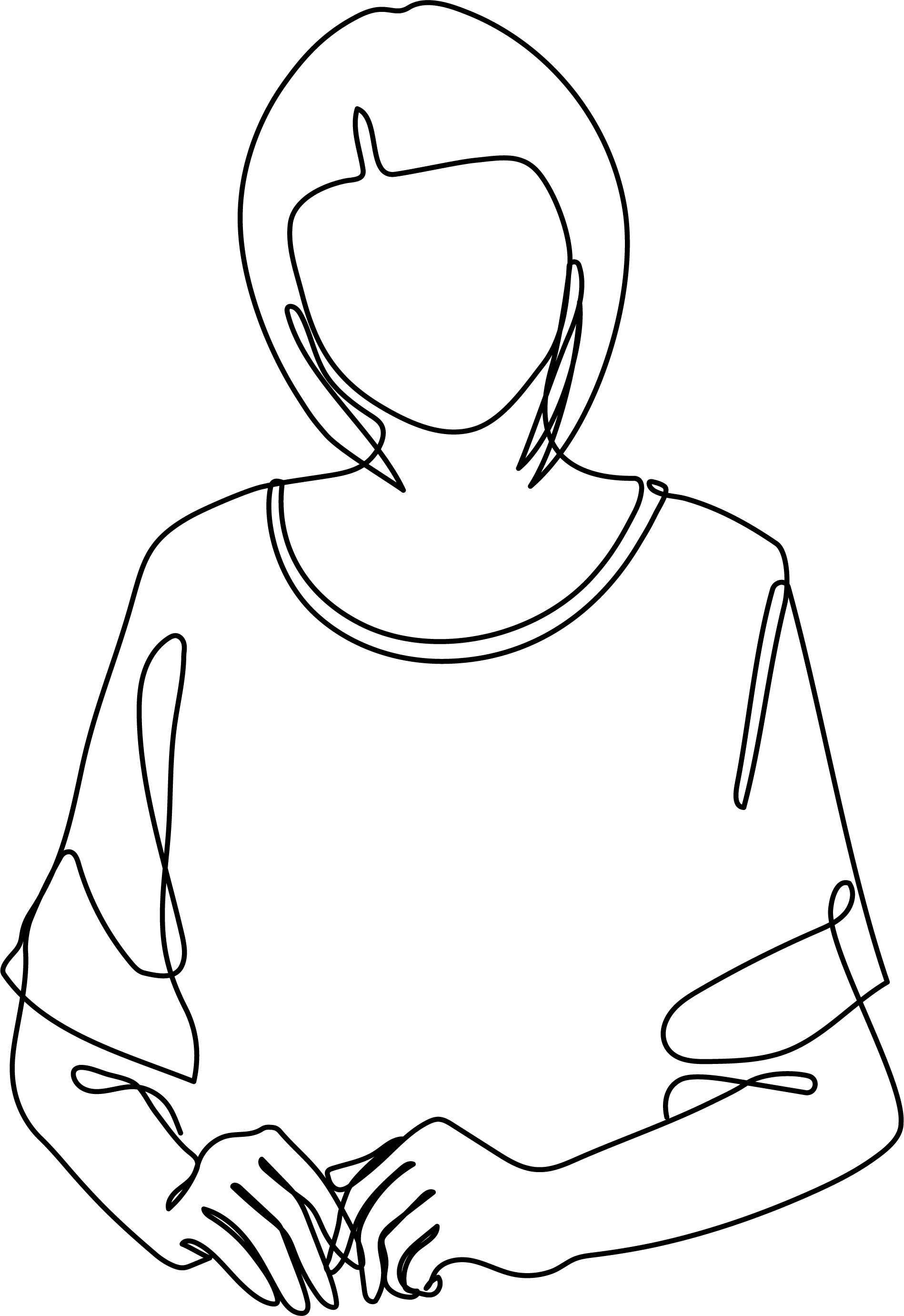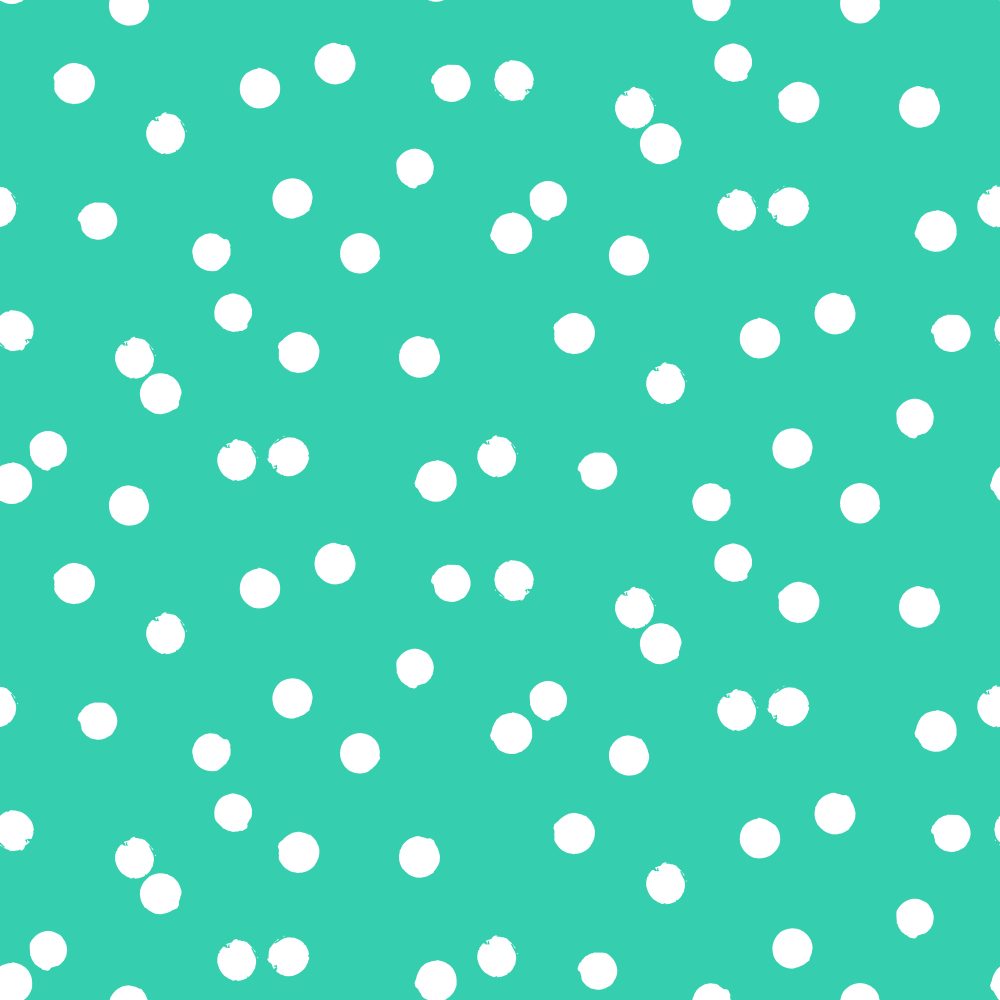中絶再考その7 日本の女性たちはもっと怒っていい
2020.01.08

2019年、性と健康を考える女性専門家の会の避妊・安全な中絶プロジェクトの一環としてワークショップを始めた。12月22日、今年最後となった第4回ワークショップでは、「中絶―ザ・パーソナル・イズ・ポリティカル」というタイトルで話させていただいた。
中絶、流産、不妊の心配、助産院での高齢出産といったパーソナルな経験を通じて、わたしが日本のリプロ医療に疑問をもつようになったこと、フェミニズムを学び、中絶問題を研究していくうちに、自分一人の経験だと思っていたことが、実は他の女性たちの経験と地続きでつながっていて、その裏にはポリティカルな「不公正」があるとはっきり見えてきたこと、そうした「不公正」を突くために、最近、韓国の女性運動から学んだリプロダクティブ・ジャスティスという考え方に惹かれていることなどを一気に話した。その後、1時間ほど参加者の皆さんと意見や経験をシェアすることができた貴重な会だった。
だけどワークショップ後に残ったメンバーは、来年はいったいどこから何をしよう……と、頭を抱えてしまった。日本の中絶問題はあまりにも難問が山積みで、したいこと、すべきことがありすぎる。いったいぜんたい、どこから手をつけたらいいものか……戦略的にも悩ましいところだ。
堕胎罪の撤廃、中絶薬の認可、搔爬から吸引への移行は、いずれも当然求めていきたい。吸引への移行を求めるのなら、金属製の管ではなくプラスチック製カニューレも導入してほしい。かといって、日本では避妊も中絶も値段がそもそも高いので、これ以上、アクセスが悪くなったり、コストが上がったりするのは困る。それ以前に、性教育がぜんぜん足りてなくて、自分の身体を自分で守るという意識が育っていないし、スティグマも無茶強い。そればかりか、フェミニストのあいだでさえも、中絶はまだまだ「タブー」とされている……。
まったくもって日本の女性運動は、世界の女性たちとは全く別の道を歩んできてしまったのだなぁと、改めて思わずにはいられない。まさしくガラパゴス状態が続いていて、過去の遺物を引きずっている。他の国を手本にしたくても、あまりに状況が違いすぎる。どうしたものか。
大きなボタンの掛け違いの始まりは、第二次世界大戦後に制定された優生保護法だろう。優生保護法は国の人口抑制策――つまり、生まれる子を減らそうとした対策――として制定された法律で、「堕胎は犯罪」としたまま、一部の「中絶」を医師の裁量で合法的に行えるという形にしたものだ。現行の母体保護法も、中絶に関する条文は優生保護法からそっくりそのまま受け継いでいる。女性の権利や尊厳などまったく考えてなくて、むしろ「産む/産まない」を自己決定する女性を「コントロール」する気満々の法律だ。
それが今もまだ使われているんだから、女性の自己決定権なんて元々入り込む余地がない。自分の都合で中絶をする女を犯罪者扱いする刑法堕胎罪をそのままにしながら、医者や夫に許可を求めなければならないシステムになっている。自分の身体に起きていることなのに、自分一人ではどうにもできないというのが、今の日本の中絶を巡る法制度なのだ。
しかも、第二次世界大戦直後の1948年という非常に早いタイミングで中絶を合法化したために、日本の合法的中絶では、流産の後処理として用いられていたソウハ手術が定着してしまった。「赤ん坊を子宮から掻き出す」方法としてイメージされた日本の「中絶」は、強いスティグマを伴うものになっている。(実際には、まだ「赤ん坊」とは言えないような段階で手術を受けることが大多数なのに。)
優生保護法はその名の通り、優生でない者――障がい者と貧乏人――の子孫を淘汰する目的も併せ持っていた。さすがに障がい者差別にあたる部分は批判を受けて削除され、1996年に母体保護法と名前は変わったものの、あいかわらず中絶を一部の医師しかできない独占業務と定めているため、医師でなくても行えるより手軽で安全で安価な中絶方法への移行をはばんでいる。
優生保護法という最初のボタンの掛け違いは、1970年頃に日本で始まったウーマン・リブの議論の方向性をそらすことにもなった。リブの女性たちは当初は勇ましく「刑法堕胎罪廃止」を訴えていたものの、プロライフ派の議員たちから優生保護法の「経済条項撤廃」という「法改正」が提起されたために、「優生保護法」を「守る」立場にならざるをえなくなった。現実的に「経済的理由」による中絶を受けている女性が圧倒的多数を占めていたためである。そこで女性たちは、「改悪阻止」と叫んで優生保護法の続行を求めるはめになってしまったのだ。
一方で、海外だったらプロライフ派(胎児の生命尊重派)しか語らないような非常にスティグマの強い中絶観が、女性運動の側からしばしば提示された。それにはいくつかの理由がある。何よりも、ソウハが浸透していたという事実がある。また、1960年代くらいから出回りはじめた「胎児写真」や産婦人科におけるエコーの広まり、さらに日本のリブに顕著だった強い母性主義などの影響もあるだろう。
さらに、日本文化特有の現象として、1970年頃から始まった「水子供養」の言説が強く影響したと思われる。「赤ちゃん、ごめんなさい」と中絶した胎児に謝罪し、供養するという1970年代に作られた新しい風習は、女性の心に「罪悪感」を植え付け、刑法堕胎罪と共に、中絶は「悪いこと」「罪である」と人々にイメージさせる源泉になっている。(キリスト教文化圏で、中絶が「宗教的罪」と見なされているのに対し、日本ではそのような宗教的な罪悪視は元々存在していなかった。詳しくは、わたしが監訳した『水子供養 商品としての儀式』明石書店刊を参照してほしい。)
もうひとつ大きな要因は、コントラセプティブ・メンタリティ(避妊は自分の身体を守る正当な手段であり、それを奪われてはならないとする考え方)が日本の女性たちには根付いていないことだろう。海外では、1960年代に登場した避妊ピルは女性たちから大いに受け入れられ、女性の自己決定意識を養っていった(同時に、社会の中に女性の自己決定の権利を認める意識を広めていった)。一方の日本では、女性グループ同士の対立や一部の先鋭化と、それを面白おかしくはやし立てたメディアの影響、ピル擁護派への反発、副作用の認識が広まっていったこともあって、結局、ウーマン・リブの時代には避妊ピルの導入には至らなかった(その結果、「女性の自己決定」を正しいものとみなす社会的風潮も育たなかった)。
1999年に(バイアグラ認可の後で)ようやく避妊ピルが導入された時にも、アクセスしにくい価格や条件が付けられたため、今でも日本人の使用率は他国に比べても非常に低いままだ。ピルが定着していないという事実は、日本の女性たちの性や生殖に関する自己決定意識が今も低いことにかなり影響を及ぼしているだろう。
だけど、世界からさまざまな情報が入って来る今の時代になって、日本の性と生殖のありかたはおかしいんじゃないか、これは女性差別ではないのか、などと気づく若い世代の女性たちが出てきているのを人生後半期に入ったわたしとしてはとても頼もしく感じている。
折しも、今年の世界経済フォーラム(WEF)のジェンダー・ギャップ指数で、日本のランキングは153カ国中121位だったことが報道された。122位以下はすべてイスラム教の戒律が厳しく女性差別がはなはだしい国か、アフリカのサハラ砂漠以南の最貧国がずらりと名を連ねている。同じイスラム国家でも、多少なりとも経済的に強い国々は日本より上にランクされている。
これは日本政府が男女格差に何の対策もしてこなかった結果であって、あまりにもひどすぎる。日本の女性たちはもっと怒っていい。不当に扱われている社会の現実に一緒に声を上げていこう。そのために、まずは世界とのギャップを伝えていきたい。そんなことを、年明け早々から改めて考えている。