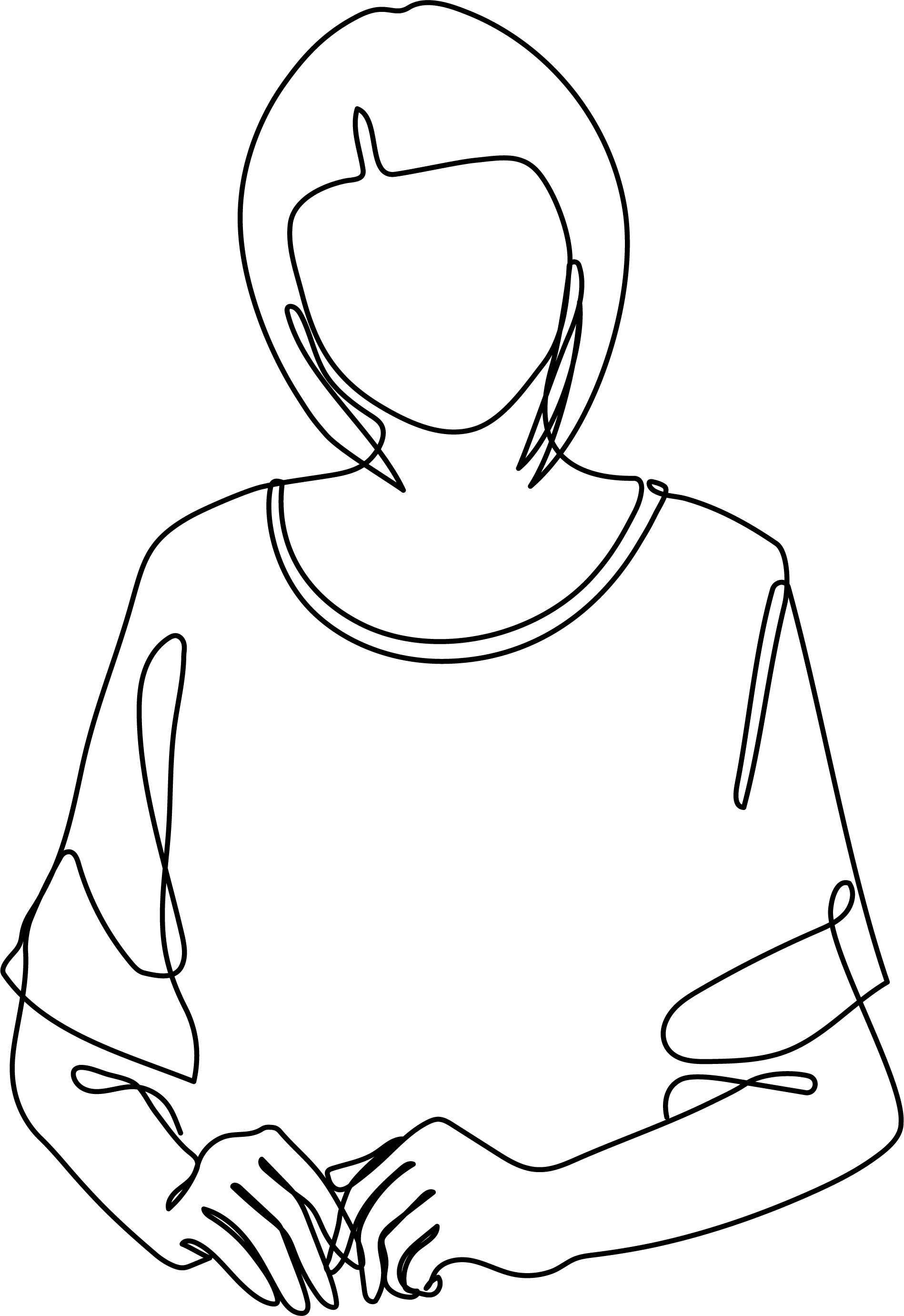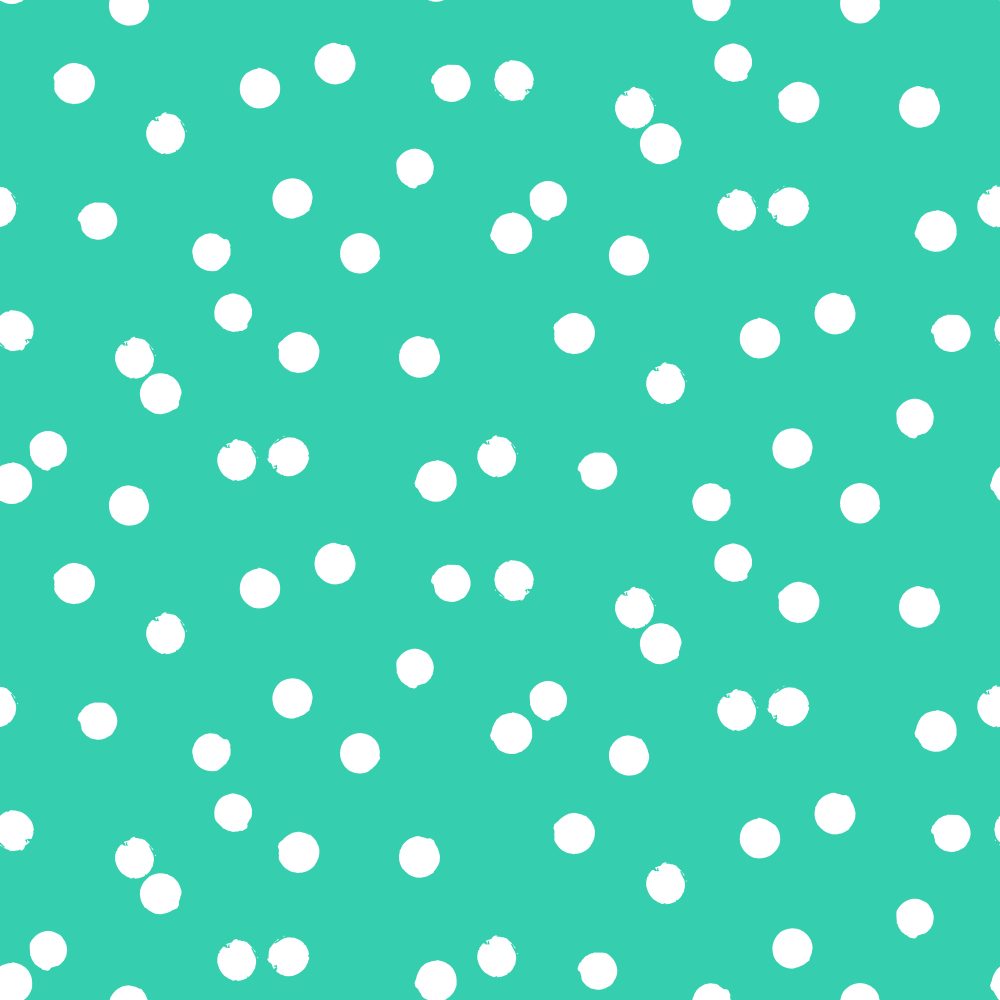中絶再考 その5 国際アボーションデー
2019.11.17

9月28日は元々1990年に中南米で中絶が脱犯罪化されたことを祝した日だった。それが2015年からは、毎年、国際セーフ・アボーション・デーとして、全世界の女性たちが安全な中絶を受けられることの重要性をアピールするために、さまざまなイベントがくり広げられるようになった。各国のイベント情報を集めたセプテンバー28.orgによれば、今年は85か国でおよそ400のイベントが開催され、合計1220万人が参加したという。でも、わたしたちのようににわか作りで行ったイベントもあるはずなので、現在、実態を調査中。きっと実数はこれより多くなるに違いない。
知る限り、日本でも今年はJOICFPが非公開ながら中絶に関する学習会を開いたと聞いているし、UMIのいえでもイベントがあったそうだ。そして早乙女智子さん、北原みのりさん、わたしの3人も、わずか2週間足らずの準備期間でトーク・イベント「なくそう、アボハラ」を京都男女共同参画センターで開催した。
このイベント開催は、「アボハラ」という新語を得たわたしたち3人が、この言葉を広めようという思いで突っ走った結果なのだけど、じつはこの時、まだ「アボハラ」について定義もしてなければ、きちんと吟味できてもいなかった。実際、これまでわたしは、「中絶のタブー」、「中絶罪悪視」、「中絶のスティグマ(化)」、「中絶医療の問題」、「リプロダクティヴ・ヘルス&ライツ」などさまざまな論点から中絶を論じてきたけど、こうした論点とアボハラとの関係もまだ明らかになっていなかった。そこで今回は、「中絶ハラスメント」略して「アボハラ」とは何なのか、ちょっと考えてみたい。
じつは英語には「アボーション・ハラスメント」という言葉はない。その代わり、アボーションの前に「反対する」「敵対する」「排斥する」といった意味の接頭語アンチ(anti-)を付けて、「アンチ・アボーション・ハラスメント」という言葉が使われている。この言葉には、反中絶派による中絶当事者に対するハラスメントの意味合いもあるが、それ以外にも、中絶を禁止したり(たとえば法的な禁止)、より受けにくくしたり(中絶可能期間を短縮したり、価格を吊り上げたり)、受けた人がより苦しむようにしたり(より劣悪な中絶環境にしたり、中絶を罪と位置付けて当事者を責めなじったり)するなど、中絶環境を劣悪化させることで中絶を妨害するあらゆる個人的/集団的行為が含まれている。
わたしたちの「アボハラ」ということばも、英語圏で言われるアンチ・アボーション・ハラスメントと同様のことを想定していたように思う。そもそも日本では、刑法堕胎罪で中絶(堕胎)を罪と位置付けている。その上で、一部の中絶(とはいえ、妊娠期間の縛り以外はほとんど全部に近い)を合法化している母体保護法は、中絶を「選択」したはずの女性自身に「決定権」を与えないことで医師や男性に従属的な地位に女性を置き、結果的に中絶を選ぶ女性の自己決定権を否定し、その尊厳を脅かしている。しかも、日本のバカ高い中絶費用はすべて自費であり、女性にとって中絶へのハードルは非常に高い。さらに、中絶が「罪悪視」されているがために、当事者は「中絶した女」というレッテル貼りを恐れて、自らの経験を恥じ、ひたすら隠し、自己否定を続けることになる。
でも、ここで英語圏の「アンチ・アボーション・ハラスメント」をわたしたちの「アボハラ」と同じものとみなすことはできないと、ひとつ注意しておきたいことがある。「中絶」――英語でいう「abortion」――は、決して万国共通のイメージを伴う言葉ではないということだ。時代や社会背景、文化によっても、これらの言葉の意味やニュアンス、罪悪視の度合いもまったく違うからだ。
実際、他の国々には見られない非常に特異な経緯で中絶が「正しいもの」として合法化され、時代の変化によって今度は「悪しきもの」として断罪されていった歴史をもつ日本では、この国特有の事情が現代日本の「中絶観」に大きな影響を及ぼしている。
その変化をわたしが目の当たりにしたのは、日本国内で中絶が最も広く行われていた1950年代から60年代にかけて中絶を行った世代の女性を対象に調査したときだ。調査票には女性たちの切実な声があふれていた。(中絶した)当時は「子どもにかわいそうなことをした」とは思いながらも「何の罪悪感も覚えなかった」「誰でもやっている当たり前のことだと思っていた」と語る何人もの女性たちが、後になって「自分は悪いことをした」「罪悪感を覚えるようになった」などと証言していたからだ。
中絶が「当たり前」から「悪いこと」へと急変したのは、1970年代に入った頃だと考えられる。当時、全国各地の寺社に「水子供養」が急速に広まり、明治期以来の刑法堕胎罪の裏打ちもあって、中絶を罪悪とする見方がみるみる広まっていったからだ。
水子供養の普及は今の日本人の中絶観に決定的な影響を与えているとわたしは考えている。しかも水子供養は、必ずしも中絶した女性たちの悲嘆や苦悩に宗教的な回答を与えるために導入されたものではない。むしろ中絶を悪と位置づけ、女性たちに罪悪感を植え付け、中絶しにくくするためにあえて導入されたアボハラ的な性格が強いように思われる。
たとえば、埼玉県の秩父に紫雲山地蔵寺という水子供養専門寺院が作られたのは、1971年のことだった。寺のオープニングセレモニーにあたる開山式の記念写真には、時の総理大臣佐藤栄作氏が初代住職の橋本徹馬氏と並んで収まっているのが、同寺のホームページで今も見ることができる。
実は1960年代の日本は、先進諸国の中では唯一の中絶を合法化していた国であり、非常に多くの中絶がほとんど何のおとがめもなく行われていた。堕胎罪は空文化したといわれ、中絶ツーリズムも盛んだった。そのために、当時の日本は海外から「堕胎天国」と批判を浴びていた。
そこで、敗戦後の惨状から急速に高度経済成長を遂げ、人手不足がささやかれるようになったとき、長期にわたり政権の座についていた佐藤首相は、中絶しにくくすることで労働者の減少を食い止め、同時に堕胎天国の汚名をはらすことを狙ったように思われる。ちなみに、佐藤総理はプロライフ派であり、初代住職の橋本氏は右翼の大物だったといわれている。
詳しく知りたい方は、わたしが監訳している『水子供養 商品としての儀式』(明石書店)を参照していただきたい。
中絶のスティグマ化や罪悪視は自然発生的にうまれてきたものというよりは、日本特有の社会的、文化的、歴史的、政治的諸事情によってかなりの部分作られたものだと考えられる。実際、中絶を「罪」とする見方は永遠の真実ではないし、中絶に対する見方は歴史を通じて変遷してきた。文化によっても中絶への態度は相当に異なるし、現代日本の「中絶罪悪視」は、そもそも国家が国民の生殖活動を管理するために中絶を罪悪と位置付けた「刑法堕胎罪」に多くを負っており、それが今もアボハラの通奏低音になっている。
中絶をタブーとする根幹には「堕胎罪」がありながら、一部の事由(理由)に該当する中絶が(女性の権利としてではなく)合法化されている実態の裏には、国家と男性と医師から「許可」されることによって合法的に行われるという女性疎外的な仕組みがある。「中絶は悪であるが、場合によっては認めてやろう」という枠組みのなかでは、女性たちは主体になれず、受動的に「認めていただく」側になる。そのため、自らの権利として中絶を考えたり、中絶方法を選択したりするなど「主体的に中絶と関わる」という発想そのものがほとんど育ってはこなかった。
むしろ日本の女性たちにとって、中絶のスティグマ化により、「中絶」は触れてはいけない穢れたもの、あるいは恐ろしく見たくないものとなり、中絶罪悪視があるゆえに、それを正面から見つめたり語ったりすることができなくなった。そして中絶は、稀に一部の学者が論じることはあっても、社会的に議論されることはないタブーの地位を確立した。
そのタブーのベールの向こう側にある日本の中絶の現場では、前時代的で残虐なイメージの強いソウハが延々と使いつづけられてきたという信じがたい事実がある。「中絶」とはソウハで行うものであり、「子宮から胎児を掻き出すものだ」という認識が今も多くの人々に共有されている。そうしたイメージは中絶する当事者を責めさいなむアボハラを可能にし、当事者たちを精神的に苦しめ、罪悪感をかきたててきた。
ところが、海外においては事情が全く異なるのだ。海外では、ソウハは半世紀前に吸引に置き換えられ、捨て去られた外科的手術なのである。現在はより早期に行われ、その分、より受け入れやすい(残虐なイメージが少ない)手動吸引や薬による中絶が導入されている。むしろ、そうした「より残虐ではない方法」で中絶を行うようになったことで、海外では「中絶」のイメージが様変わりしたともいえる。要は、ソウハを使い続けることで、日本では「中絶は残酷なもの、悪いもの」といったイメージが産出されつづけ、のさばってきたのだ。これが「アボハラ」の原因の主要因のひとつだと言っても過言ではないだろう。
こうした中絶の法的な位置づけと、中絶医療の改善のおくれによって形成された「中絶はいけないこと、残酷なもの」といったイメージが、水子供養という作られた風習によって支えられ、増幅されている。ほかにも「胎児」や「母性」を巡る様々な事象が密接に絡み合って、今の日本の「中絶」イメージは形成されており、そのイメージを核に組み立てられたシステムのなかで、中絶する女性たちは身体的、精神的な苦痛や困惑、不快感を与えられている――つまりアボハラを受けている――のだ。
アボハラは人権侵害である。中絶しようとする女性たちは、不当に中絶を妨害されてはならないし、中絶することで一方的に断罪されたり、弁明を求められたり、苦しめられたりするようなことがあってもならない。
だけど、現にアボハラを行っている人々は、中絶当事者の人権を侵害をしているという感覚はまずないだろうし、むしろ自分は社会正義を体現していると思っているのではないか。
だからこそ、日本のアボハラをなくしていくためには、海外における中絶の位置づけや、中絶がいかに女性の人権尊重に直結しているということを「学ぶ」必要がある。
「やめよう、アボハラ」「なくそう、アボハラ」を広めていくために、やはり中絶にまつわる日本の問題をより多くの人々に伝えていくしかないのかなと、今は思っている。