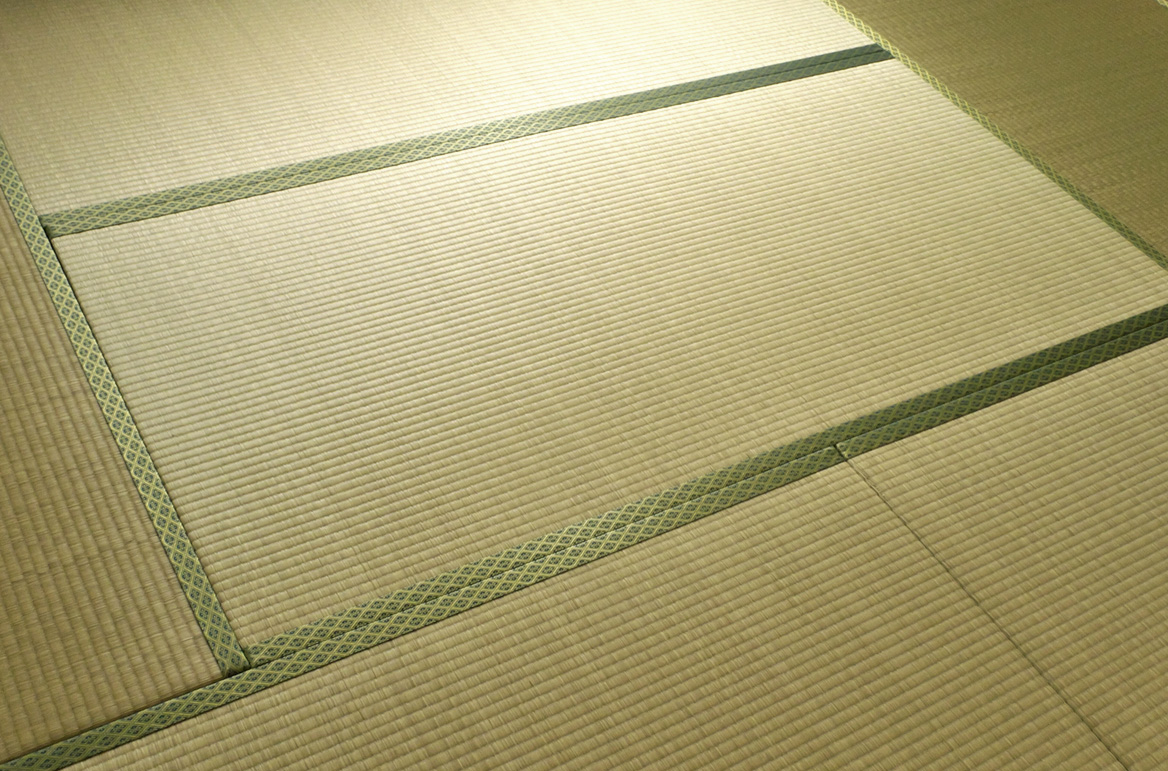結婚するふたりの新居は、どのように決まるのが一般的なんだろう。
身近なところで母に聞いてみたことがあったが、「パパとふたりで仕事中に見に行ったわねぇ」という答えが返ってきただけだった。
父と母は同じ総合商社に勤める上司と部下の職場結婚で、聞けば、そのころの商社はわりといろんなことが適当だったらしい。
仕事中にふたり一緒に2、3時間丸の内のオフィスを抜け出して物件の内覧に行っても特におとがめなしだったそうだ。
その日一日の外訪スケジュールを公開し、完全に把握されている銀行員からすればどう考えても実現不可能な気がしたが、そう言えば私も仕事を抜け出して恵美子さんとお嬢さんと三人で結婚指輪を選んだことがあるので、やろうと思えばどうにでもなるのかもしれない。
母は、やれどこそこの物件は近くに廃墟みたいな金物屋があってしんきくさかったとか、最寄の地下鉄ホームから見たドブネズミにぞっとしてその物件はやめたとか、ものすごく局所的なマイナスの思い出だけを大量に語り続けた後で「パパとママも結婚式のときにはまだ引越しがすんでなかったのよ。だから、ミナトちゃんもずーっと実家にいていいのよ。ねっ」と言ってにっこりと笑った。
口では無邪気なことを言っているふうだったが、媚びたような笑顔にも思えたし、懇願するようでもあった。
私は、母が金物屋とドブネズミの思い出を語り始めたあたりから意識がぼんやりして、あまり集中せずに聞いていたので、ぼんやりした頭の中で、「ずーっと実家に」なんてありえない、と漠然と思った。
結婚式を挙げても山田仕郎と私の連絡頻度は何も変わらなかった。
電話もメールも特にしない。
かかってくることもなければ、こちらからかけることもない。
送ることもないし、送られてくることもない。
連絡頻度が変わらない原因がもしこちら側にもあるとすれば、私は、震災の時のことを根に持っていた。
山田仕郎に、彼のことを心配するメールを送ったら「不要不急のご連絡はご遠慮ください」と返信されてしまったアレだ。私はそのメールを保護設定にし、時間の経過とメールの蓄積で消えてしまわないようにした。保護したからと言って読み返すこともないのだけれど、読み返す必要がないくらい、脳にしっかりと刻まれていたし、折に触れ思いだすことで、記憶が埋もれてしまわないようにした。それは、石に掘った文字が苔に埋もれてしまう前に、彫刻刀でより一層深く掘るような作業だった。
非常時以外にも、結婚式の準備で何かと確認や連絡を取る機会はあったのだけれど、何を送っても「了解」か返信がないかのどちらかだ。私は努力することをあきらめた。
ちなみに、もし山田仕郎のほうにも原因があるとすれば、たぶん彼に危機感が欠如していたことだと思う。
山田仕郎の当直がない週末は、実家に戻っている山田仕郎と、恵美子さんやお嬢さんたちと一緒に食事をすることが習慣になっていたので、食卓を囲んでいる間だけがコミュニケーションを取れる時間だった。まぁ、山田仕郎はほとんど私としゃべらないので、顔を眺める程度だが。
ともかくそういうわけで、「おうちどうしよっか」「このエリアに住みたいなぁ」みたいな会話は起こりようがないのであった。
新居が決まるまでは、こうだ。
結婚式があった次の週末、私は恵美子さんたちといつものダイニングでお茶にしようとしていた。
恵美子さんがいて、お嬢さんがいて、山田仕郎がいた。お嬢さんは結婚式に参列はできたものの、入退院と自宅療養を繰り返しているような状態で、現に式の最中も車椅子に積んだボンベから酸素を吸い続けていたし、そもそも式に参列できるかどうかもあやしい、と言われ続けていたのだ。
義妹と義父はいなかったが、特に何の説明もなかったし、聞いても脈絡のない悪口が始まるだけなので、私から尋ねることもなかった。
お茶の準備をしているときから気になっていたのだが、いつのまにか、食卓の目につくところにフルカラーの不動産チラシが置かれていた。中古マンションの物件名と間取り図、そして価格が見える。
“初掲載”という赤い文字、“2LDK”“予約制内覧会開催”、その他、重要なことや大事なことは全部、模様みたいな小さな文字だ。
「仕郎、ちょっと来なさい」
恵美子さんに呼ばれて、食後すぐマッサージチェアに納まってしまった山田仕郎はおとなしく立ち上がった。
「おっ、とらや」
私が切り分けた羊羹を眺め、山田仕郎がうれしそうな声をあげる。
おい山田仕郎、たぶん、今からどでかいショッピングが始まるぞ。
羊羹と不動産のチラシを眺めていると、恵美子さんがいきなり「新居のことだけれど」と切り出した。
「いい物件があったのよ」
私は山田仕郎を見たが、山田仕郎はぼんやりとテーブルの中央を見ている。と、そのテーブルの中央にチラシがぱさっと置かれた。
不動産チラシが入るのは、金曜が多い。グループ会社の不動産販売の担当者に聞いた。銀行のお客様を紹介することがあるので、月に1回は必ず会議で同席する機会があるのだった。金曜にチラシが入るのは、土日で家族会議にかけてもらうためらしい。
本当なんだなぁ、と思いながらチラシを眺めて気づいたのだが、予約制内覧会の日付は2週間前だった。
「あれ、これ、いつのチラシですか?」
今週のじゃないな、と思いながら尋ねると恵美子さんはちらっとお嬢さんを見て、「先に見てきたのよ。いい物件だったから、もう仮押さえしてあるの」と言った。
私は価格を見て、最寄駅の名前を見た。
別に、今、我々のいるエリアの隣の駅などではない。母が頻繁にたとえとして使う「スープの冷めない距離」というわけでもなさそうだった。もちろん、私の実家からはより一層離れているので、スープの冷めない距離どころの話じゃない。出前圏外である。
山田仕郎もお嬢さんも、チラシを前に、誰も何も言わない。
私も黙っていた。黙ったまま、担当として最後に確認した山田仕郎の残高を思い浮かべた。現金がどれだけあったか思い出せないけれど、たしか、あの時購入した劣後特約付きの債券は中途売却も可能なはずだ。手続きは面倒だが、まとまった額であれば売却できる。
だから山田仕郎にとっては非現実的な価格ではない。私にとっては非現実的な数字だった。
どうするのだろうか、と思って顔を上げたら、突然お嬢さんがキレた。
「仕郎ッ、何とか言いなさいッ、あなたが何もやらないから──」
お嬢さんは酸素を鼻から吸いながら、声を荒らげて怒っている。
「まだ一緒に住んでいないなんて、みっともないったらありゃしない!」
お嬢さんは、病状が悪くなるにしたがって、今みたいに感情的になることが少しずつ増えてきていた。
結婚式もそうだ。披露宴後、ゲストをお見送りするとき、突然、主賓の教授の手をつかんで「私はもっと生きたいんです!」と絶叫し、その場にいる全員が一瞬凍りついた。私は目の前のゲストのこわばった笑顔を眺めながら小さなギフトを手渡し、すぐ近くでドラマみたいなことが起きているな、と思っていた。
取り乱すお嬢さんとは対照的に表情を変えない教授のまわりでは、教授の取り巻きの“完全に隔離された安定して均一な空間”メンバーが「まぁまぁお母さん」「お気持ちはわかりますが」「お母さんの主治医ではありませんから」などとなだめまくり、「う、あ」とうろたえた声を出し続ける山田仕郎を「大変だな」とねぎらって去っていったのだった。
今回は、家庭の中だからか、山田仕郎も「う」とも「あ」とも言うことはなく、腑に落ちない顔をして「はぁ」とだけしゃべった。
「仕郎ッ、一括で買いなさい」
「はいはい」
仏頂面の山田仕郎が投げやりな様子で「わかりました」と言って、それで話がまとまってしまった。